七月十七日・日曜日、おりしもカジノに舞踏家一家が巡回公演に来ていた。
マンは妻及び何人かとつれ立って出かけた。
小さな一座で、アメリカでも会ったことのある女優のほか、
「サウス・ダコウタ出身の、才能は少ないが、魅力的な青年舞踏家」がメンバーにいた。
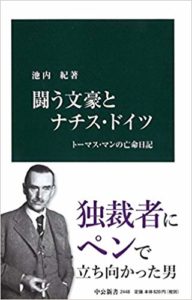
池内紀『闘う文豪とナチス・ドイツ トーマス・マンの亡命日記』(中公新書/二〇一七年)
九歳の時、自分がバイセクシュアルだと気づき始めていた私はトーマス・マンの『トーニオ・クレーガー』と『ヴェニスに死す』を同性愛小説として読んだ。同性愛への言及を避ける旧弊な解釈によれば『トーニオ・クレーガー』は芸術家と市民生活の葛藤を描いたものであり、『ヴェニスに死す』は美によって破滅する芸術家の小説だとされるが、二〇一七年の今日、このふたつの作品は同性愛小説の古典になっており、それを裏づける研究もさかんになっている。
『トーニオ・クレーガー』の主人公トーニオが恋するハンスにはマンの同級生だったアルミン・マルテンスという実在のモデルがおり、執筆動機はパウル・エーレンベルクという青年と恋に落ちたからだ。『ヴェニスに死す』の美少年タッジオにもモデルがおり、その正体はマンがヴェネツィアを訪れた時に出会ったヴワディスワフ・モエス男爵という十一歳の少年だった。タッジオのモデル問題についてはイギリスのホモセクシュアルの作家、ギルバート・アデアが『ザ・リアル・タッジオ』(未邦訳、二〇〇一年)というノンフィクションを書いている。マンと同性愛については福元圭太による『「青年の国」ドイツとトーマス・マン―20世紀初頭のドイツにおける男性同盟と同性愛』(九州大学出版会、二〇〇五年)という大著もある。
幼い私にはこういった裏話は知りようもなかったが、マンの小説の通奏低音である同性愛を敏感に察知していたことは確かだ。セクシュアルマイノリティは世間に大手を振って流通している異性同士のラブストーリーに共感できないどころか、疎外感すら抱く。私もご多分に漏れなかったが、そんな時に読んで救われた気がしたのが『トーニオ・クレーガー』と『ヴェニスに死す』だった。
初めてマンを読んだ二十二年後の二〇一一年、三十一歳になった私はアメリカ文学史上初めて同性愛を正面切って描いた『都市と柱』を代表作に持つ作家、ゴア・ヴィダルに会った。当時、八十五歳で翌年没する運命にあったヴィダルは『都市と柱』をマンに献本して手紙を貰い、後に公開された日記でも賞賛された、と誇らしげに話してくれた。
池内紀の『闘う文豪とナチス・ドイツ トーマス・マンの亡命日記』にも私は「同性愛者トーマス・マン」の肖像をいくつも見出した。『闘う文豪とナチス・ドイツ』は二〇一四年に翻訳が完成した『トーマス・マン日記』全十巻(紀伊國屋書店出版)の一九三三年から戦後の部分を扱ったものだ。帯に「独裁者にペンで立ち向かった男」とあるために、この本を手に取った人は生真面目で硬苦しいノーベル賞作家マンがヒトラーと丁々発止とやりあっているところを想像するかもしれないが、実のところそういったエピソードはあまりない。
一九三三年三月、講演旅行のためにドイツ国外に出たマンは、その年の一月に政権を奪取したナチスによって帰国を差し止められてしまう。その際、マンが気に病んだのは自宅があるミュンヘンに残してきた日記のことだった。マンは「妻でさえ中身を知らない私的な記録」がナチスの手に渡ってしまうことを危惧していた。池内紀は明言していないが、この「古い日記」には同性愛のことが書かれていたのだろう、とマンの研究者たちは推測している。マンはこの日記を取り戻した後、一九四五年に焼却しているが、焼却炉から戻るところを息子に見つかって「いささか狼狽」していたという。
亡命生活の困難は加速度的に進行する。さしあたってマンが滞在したスイスでは隣人の『西部戦線異状なし』で知られる小説家、レマルクの別荘で暗殺事件が起こる。ドイツに居残った妻の両親を国外に脱出させるまでの悪戦苦闘。ドイツ国籍剥奪とボン大学の名誉博士号の剥奪に加えて完全に濡れ衣である盗作疑惑までもが襲いかかる。切迫する状況のなかで、マンは一九三八年、遂にアメリカに渡る。
アメリカでの生活も平穏とは言い難かった。マンと同様にドイツから亡命してきた劇作家ベルトルト・ブレヒトとは対立し、友人だった作家のシュテファン・ツヴァイクは自殺する。マンは激動する時代の記録を日記にしたためながら、滅びゆくドイツを主人公に託した晩年の大作『ファウストゥス博士』を書き継ぐ。
一九四五年、戦争は終結するが、マンに心休まる日々は訪れなかった。一九四九年、息子であり、優れた作家でもあったクラウス・マンが自殺する。クラウスの自殺は同性愛に悩んでのものだった。トーマスとクラウスには親子揃って同性愛の傾向があった。ちょうど七十五歳の父マンもホテルのボーイに「熱い情熱」を寄せていたところだった。
マンの晩年は幸福なものではなかった。フランツ・カフカの死後の名声が高まっていくなかで、マンは自分の限界を感じざるを得なかったようだ。肉体的にも弱っており、日記では溲瓶にうまく放尿できなかったことを嘆いている。マンはその死までドイツに住むことはなかった。
池内紀はマンの最後のロマンスを活写している。一九五五年七月十七日日曜日、マンは冒頭に掲げた日記の日付にチャールズ・レスリーという舞踏家と出会った。チャールズは四十年後の一九九五年に研究者に宛てた手紙でこう書いている。「私が一歩前へ出るやいなや、トーマス・マンは、私の胸骨に頬を押しつけながら、私を短く、きつく抱きしめたのですが――それは私には強烈に感じられた抱擁でした」。当時八十歳になる高名な作家に突然抱きつかれた青年の動揺は想像に難くない。マンはこの一ヶ月後に没した。
池内紀はそれまで「情熱」や「ひそかな性癖」といった言葉で仄めかしていたマンの同性愛のエピソードを最後のクライマックスに持ってくる、という心憎い演出をしている。池内紀はあとがきで次のように書いている。「『トーニオ・クレーガー』や『ヴェニスに死す』でマンに親しんだ人には、この作者はあきらかに政治的人間などではなかった。頬を染めるようにして少年愛を語っている」、「その人がいや応なく、政治的発言をしなくてはならない状況に追いこまれていく」のを描いたのが、本書『闘う文豪とナチス・ドイツ』だ。ナチスはユダヤ人とともに同性愛者を強制収容所に送り、虐殺した。隠れ同性愛者だったマンにとってナチスが政権の座にあった時代は恐怖の連続だっただろう。自ら「非政治的人間」を任じていたマンがそうだったように、自分をノンポリだと思っている人間も自己の危機においては必ず政治に関わらざるを得ない時がやってくる。『闘う文豪とナチス・ドイツ』はそのことを我々に教えてくれるのだ。
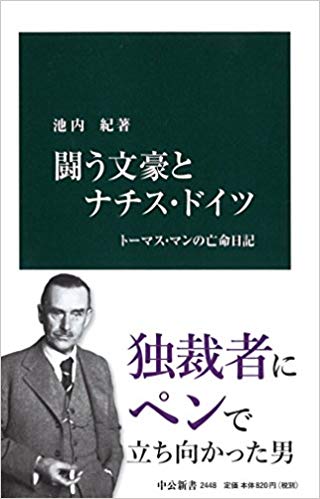
池内紀『闘う文豪とナチス・ドイツ トーマス・マンの亡命日記』(中公新書/二〇一七年)
バナー&プロフィールイラスト=岡田成生 http://shigeookada.tumblr.com

