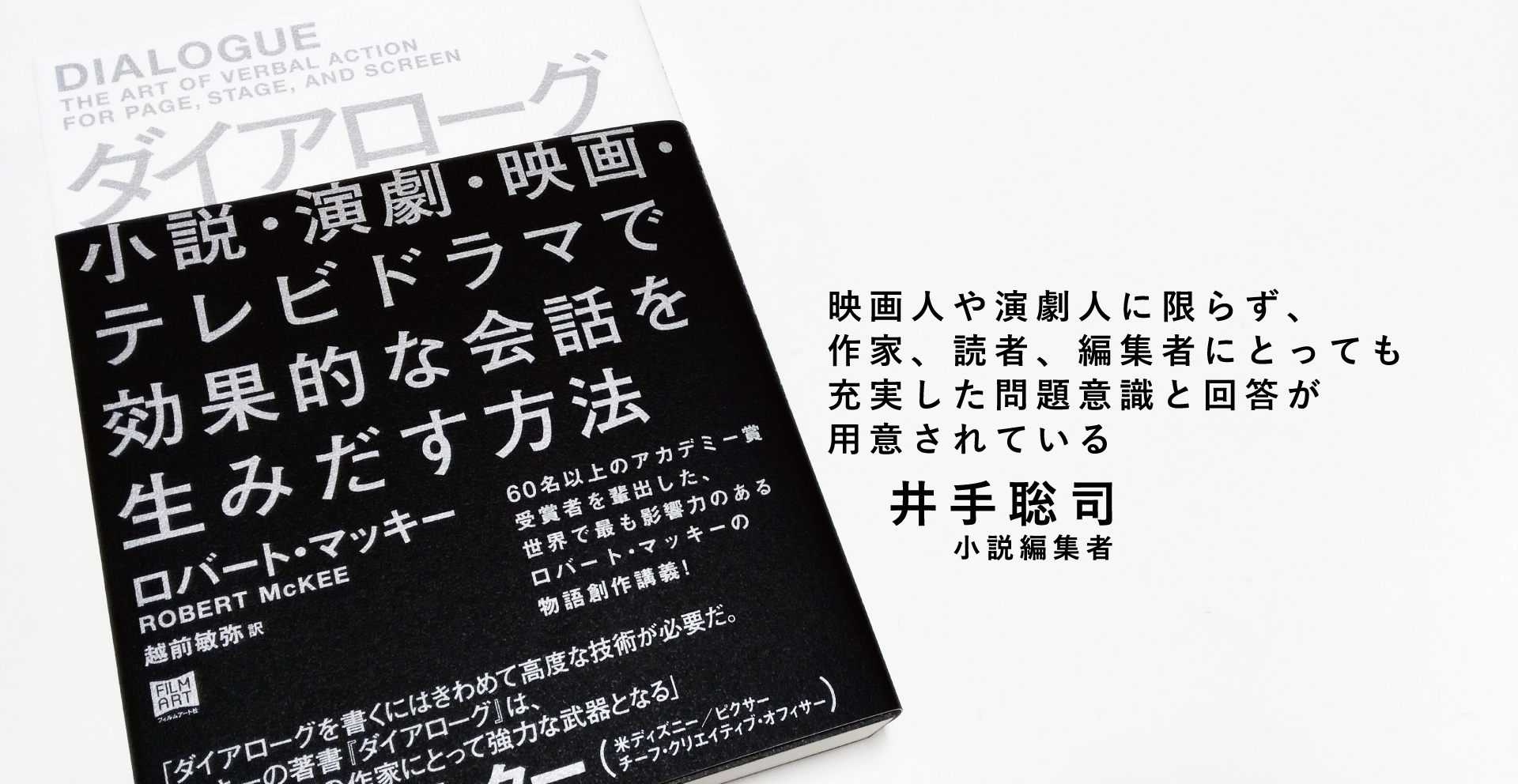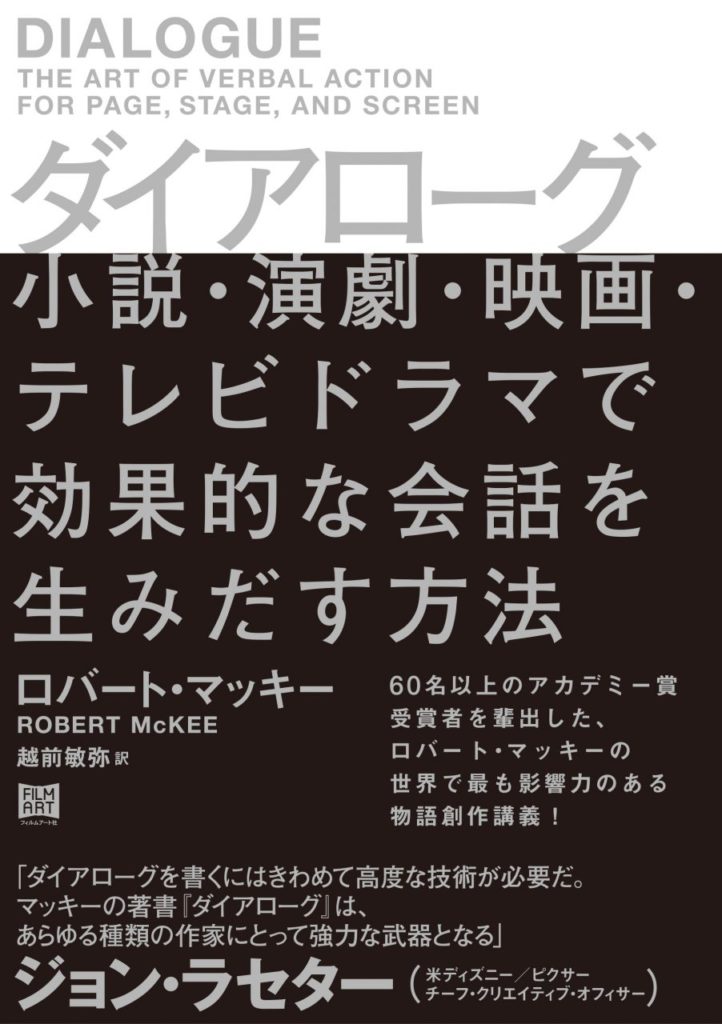物語を創作する際に最も重要な要素の一つが「会話」だ。ハリウッドに多大な影響を与え、アメリカのみならず世界中を飛び回りストーリーテリングのセミナーを開催しているロバート・マッキーの最新作『ダイアローグ 小説・演劇・映画・テレビドラマで効果的な会話を生みだす方法』(フィルムアート社)がついに日本で刊行された。本書は、会話=ダイアローグの創作に特化した、世界でも類を見ない画期的著作である。
これまで数々のヒット作を世に送り込んできた現役の小説編集者・井手聡司が本書の魅力とその意義について語った。
筒井康隆の小説作法をまとめた『創作の極意と掟』(講談社)に「会話」というトピックの章があり、文中に「会話文が下手糞な純文学系の作家もいる(中略)こういう人は戯曲やシナリオの勉強をしていなかったのだと思う」とある。
そう、実際に人が演じるために書かれた台詞ほど高度に設計された会話はない。小説家も戯曲やシナリオの勉強をするべきという考えは、学生時代に本気で役者を志し、後年プロダクションに所属して俳優として活躍してきた筒井氏にとって、まったく自然なことだろう。
そうは言っても、積極的に戯曲やシナリオの勉強をしているという作家志望者の存在はあまり耳にしないし、またそのために適当な作品も選ぶのも躊躇してきた。小説の表現にも目配りが利いた参考図書ともなると、ますます選択は困難となる。
ロバート・マッキーの『ダイアローグ 小説・演劇・映画・テレビドラマで効果的な会話を生みだす方法』は、その任に足るうってつけの本だ。
本書は、映画、TVドラマ、戯曲における会話、さらに独白、ナレーションなど物語を構成するすべての言語化された発話を扱っている。
そしてそれらに加え、小説における会話、地の文における視点人物の内面の言葉、回想といった、発話されない内面の言葉などのすべてを“ダイアローグ”の呼び名で同じ俎上に載せたうえで分類・整理し、それらに関するすべてのトピックと作劇上の失敗パターンが、前半分に相当する第1、2部にて体系化されている。
具体的な創作上の問題解決を求めるために本書を手に取った創作者にとって、この前半部分はやや冗長とも感じられるかもしれないが、ハリウッドにおいては様々な知識背景を持った大勢のスタッフが脚本開発に携わるため、議論の前提となる共通言語や概念の共有が必要であり、本書はその需要に応えているとも言える。
また読めばピンとくるが、ロバート・マッキーのダイアローグ分類はジェラール・ジュネット以降の物語論とも親和性が高く、小説の地の文における自由間接話法やジョイス、ウルフ等における意識の流れといった文体研究のトピックを実に満遍なく扱っているので、文芸専攻で物語論や言語学を学んだことのある者であっても、これまで培った知識とシームレスに接続し納得することが出来る。
現役の創作者のための実例を多用した説明は後半分にあたる第3、4部に収録されており、特定のシーンの会話劇を著者の解説と共に分析的に読み進めていくこのパートは、大変に緻密で丁寧な手続きである。
第3部では、ある登場人物がどんな文化背景と知識を持っているかによって、会話にどんな個性が生まれるかについて4つのケーススタディで説明する。
第4部では、会話のキャッチボールにおけるアクション/リアクションをワンセットにした「ビート」単位で注目していく方法論で、一連のシーンのシナリオを数行づつ分割し、ビートの積み重ねがどのように相手に影響をおよぼし、登場人物の意識や感情が変化していくかを、順追って示していく。
会話の構造を分析することは、このシーンがストーリーの中でどような機能を果たしているかを明確にしていくことと同義であり、それは物語全体の構造をどう作り上げていくかという問題意識と通じている。映画人や演劇人に限らず、作家、読者、編集者にとっても充実した問題意識と回答が用意された本である。
著者のロバート・マッキーは、アメリカでは故シド・フィールド(著書に『素晴らしい映画を書くためにあなたに必要なワークブック』など)と並ぶカリスマ的な人気と実績を持つシナリオ講師だ。西欧における物語論・演劇論・芸術論の祖であるアリストテレスの言葉を引き、物語とは、文学とは、作劇とは、会話とは何か、その本質を考え抜いていく深い文芸教養が彼の知識背景である。
高齢の大御所にもかかわらず、本書では最新の映画やドラマからも多く例を引いており、米国で刊行されてさほど間を於かずに越前敏弥氏による精妙な日本語訳で読めるのは画期的といえる。