金子文子と金素雲は、対極的な二人だといえる。女と男。日本人と朝鮮人。文子は二十代前半で死に、素雲は七十代まで生きた。
さらに大きな対照は、文子は反抗に生き、素雲は調停に生きたということだ。ご本人たちが聞いたら本意ではないと思うが、結果的にそうなっている。
文子はとても共感する力の強い人だった。だから馬鹿にされている朝鮮人を見ると自分の血が煮えてしまったし、誇り高い朝鮮人を見ると自分もそこに身を投じたくなったのだ。その高い共感能力のために、彼女は自分の足元の国に、国が拠って立っている天皇制に、がむしゃらに反抗した。
一方、金素雲は元来が反抗心の塊のような人だった。このことは自分でもたびたび書いているし、晩年につきあいのあった四方田犬彦氏のエッセイを読んでもわかる。簡単にいえばカッとしやすい、掘り下げてみれば誇り高い人だったのだと思う。日本の横暴に腹を立て、自国民の卑屈に腹をたてる。「そこを曲げてひとこと、形式だけでも謝ってくだされば――」なんていうのがいちばん嫌いだ。そのせいで非常に損もするのだが、曲げられない。
そんな金素雲が、生涯にわたる仕事の面から見れば、ほとんど誰もやろうとしなかった朝鮮・韓国文学の日本への紹介に尽力した偉大な調停者だった。ともすれば反発しあう両国の間を文筆によってとりなし、とりもち、なだめて回る、そんなことばかりしているうちに50年60年があっという間に経った。
では、金素雲とはどんな仕事をした人なのだろう。
彼は韓国と日本の両方で、戦前戦後を通じて多くの文学作品を翻訳し、編纂し、また執筆した。達意の日本語で記した随筆は今でも大いに読む価値がある。また、出版者としても志を持って働いた。
いま日本で、現役として流通している彼の本としては、岩波文庫の『朝鮮民謡集』と、岩波少年文庫の『ネギを植えた人』がある。
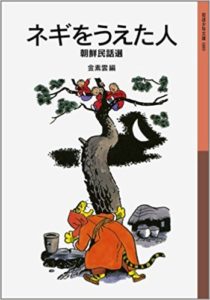
朝鮮民話を詩心豊かな日本語で伝えるロングセラー
「なんだ、その手つきは……口では言えんのか!」
「なんやと……キサマ、生意気なやっちゃ!」
売り言葉に買い言葉である。睨み合いのまま電車は終点に着き、素雲は電車の乗務員たちの詰所に連れていかれた。「やっちまえ、やっちまえ、生意気な野郎だ!」と殺気立った人々が取り巻いたとき、一人の紳士が「その人をどうしようというのだ。指一本触ってみろ、このわしが相手にしてやる」と乗り込んできた。どうやら事の次第をずっと見守っていた乗客らしい。彼の一喝で乗務員や野次馬は引っ込み、紳士は一枚の名刺を素雲に渡して、「きょうのことは私が代ってお詫びをする」と言った。その人はとある出版社の社長だったという。
大阪から朝鮮に戻った素雲は、年齢を偽って通信社や新聞社で働いた。やがて日本に再上陸すると、工事現場などで働く朝鮮同胞から口伝の民謡を採集することに熱中した。以後、朝鮮と日本を行き来しながら朝鮮民謡の歌詞を日本語に訳し、北原白秋に激賞された。20歳だった素雲はいきなり白秋の家に直行して、「先生に是非見ていただかねばならない原稿がございます」と原稿の束を差し出したのである。誰の紹介状も持たず、正式な高等教育を受けてもいないこの若者に、白秋は「こんな素晴らしい詩心が朝鮮にあったとはねえ!」と感嘆し、以後、助力を惜しまなかったという。
朝鮮が日本の植民地でなくなるまでに、素雲は10冊あまりの翻訳詩集、民謡集、童謡集、また童話集や歴史読み物などの本を日本で出した。中でも最も親しまれているのは、惜しくも現在は絶版になっているが、太平洋戦争を前にして1940年に岩波文庫に収められた名アンソロジー『朝鮮詩集』だろう。この一冊で朝鮮が、韓国が忘れ得ぬ国になったという人も少なくないのである。中から一つ、有名な作品を抜いてみよう。
南に窓を 金尚鎔(キム・サンヨン)
南に窓を切りませう
畑が少し
鍬で掘り
手鍬で草を取りませう
雲の誘ひには乗りますまい
鳥のこゑは聞き法楽です
唐もろこしが熟れたら
食べにお出でなさい。
なぜ生きてるかって、
さあね――。
原文を見なくとも、この流暢さはただごとではないことがわかるだろう。ちなみに、「法楽」とは「楽しみ」のこと。そして最後の一行「さあね――。」は、原文では「笑いましょう」である。これを「さあね」と訳した手並みが特に名訳の誉れ高く、『朝鮮詩集』を語るときに必ず触れられてきた一行だ。
金素雲の詩、民謡、童謡の翻訳は、日本翻訳史上に残る偉業である。彼は、出身大学を尋ねられると「図書館大学です」と答えていた。それはもちろん、今も日本にある図書館情報大学とは全く関係ない。仕事の暇暇に図書館に通って本に読みふけったことをさす。
図書館でのむさぼるような読書、各界各層の日本人との交流、そして滞日何十年も経た後でも、「広辞苑を引かない日は一日もない」と語ったほどの、一語をもゆるがせにしない姿勢。それは両国のことばに対して、否応なく抱いていた強い責任感のためだったろう。それが彼の翻訳を作り上げた。「愛憎」などという言葉を軽々とまたぎこしてしまうような迫力が、その日本語にはある。
金素雲の訳詩は長らく、驚異的な日本語力が惜しみなく発揮された至高の一例として、仰ぎ見られてきた。近ごろはその価値を認めつつも、あまりにも原詩に手を加えすぎているのではないかという声も聞かれ、詩人の金時鐘氏が新訳を試みている。二人の金詩人(金素雲自身も詩人である)の訳詞を並べてみると、詩の翻訳について実に多くのことを考えさせられる。このような試みが生まれること自体、金素雲の日本語の手並みがずば抜けていることの証拠でもある。
しかし金素雲は一生、「南に窓を」ののどかさとは対極の、危なっかしい橋を渡りつづけた。朝鮮で児童雑誌を創刊したが資金不足で廃刊したり、日本の特高に検挙され、護衛つきで下関から朝鮮に送還されるといった経験もした。食っていくことはまさに綱渡りで、看板書きからビラ配りとどんな仕事でもやったという。翻訳をやるため、お金もないのに江ノ島の旅館に長期滞在し、主人の信用を買うためにブリタニカの百科事典一そろいを古本屋からただで借りて持ち込んだこともある。そんな一切をしたためた自伝『天の涯に生くるとも』(講談社学術文庫・絶版)は無類に面白い。
1945年2月、朝鮮に帰り、解放は慶尚南道の金海で迎えた。
しかし綱渡り人生は変わらない。朝鮮戦争が勃発して2年後の1952年、金素雲は久々に来日した。ユネスコの招請で、イタリアで開かれる国際芸術家会議に韓国の文学者代表として出席するため、途上で日本に寄ったのである。そのときたまたま朝日新聞のインタビューを受けた。ところが「最近の韓国事情」と題するその記事が舌禍事件に発展、パスポートを没収されてしまったのである。
何がそんなに問題となったのか。本人が記しているのは、以下のような発言だ。
「レーションの空箱でつくったバラック群――共同水道にならぶバケツの列――密航船で運ばれるおびただしい日本商品――銀座並みの豪奢な衣裳と、喫茶店に群がる幼い行商人たち」。
要するに、戦争下の韓国の世情を具体的に話したことが、国の恥をわざわざ日本に漏らしたと受け取られたわけである。当時の韓国の新聞には、「金素雲の妄言」「非国民的行為徹底糾弾」といった見出しが踊ったという。
会議を終えて戻ってきた東京でパスポートを没収された。翌年、とある役所のトップが東京に来た際、詫びを入れにホテルに来れば許してやるというようなことをほのめかしたようだが、素雲は「私の祖国に私が帰るのに何ヤツが指図をするか!」と返答して顔を出さなかった。この文の最初の方に書いた、「形式だけでも謝ってくだされば」というのが、このことである。そして以後10年以上、韓国に帰ることができなかった。
記者の質問に答えて話したことのうち、重要ではないことの方が切り取られて記事になる。そういうことはいつもある。金素雲もこの記事に感心はしなかった。また、韓国側がこれを見て神経を尖らせるのもわかる。だが、よく確かめもせずにいきなり「妄言」「非国民」と決めつける韓国の報道と、それを真に受ける当局に彼は怒った。何しろ、掲載されてしまった発言も嘘ではないのだから。「役人は賄賂を取らず民意は尊重され、衣食住は足って余りあり、青年学徒は希望に燃えているなどとは、口が裂けても言えぬ」と彼は後に書いている。「糞溜に香水をふりかけて、それが愛国だというのなら、<非国民>こそ望むところ」――こういうのが、金素雲の日本語の真骨頂の一つだ。
彼が記者に対して、本当に言いたかったことはその先にあった。
「こうした混乱と窮乏の中でいま私たちは戦っているのです。明日を信じて――。さて、八年ぶりの日本へ来て私の感じることは、表裏一致のない上っ皮の癒着を急ぎ過ぎはしないかということです。(中略)失礼な譬えですが、韓国を悪性の皮膚病に見たてるとすれば、日本は骨膜炎の患者――、それがクリームを塗り、白粉を刷いて、しきりに化粧をしてるといった感じです。オキシフルと、よい塗り薬、それに包帯があれば皮膚病は癒る。骨膜はそうはゆきません。なまじ上っ皮の癒着は、本当の治療のためには帰って邪魔になりはしませんか。
韓国の青年たちが日本を憧れているのは事実です。但し、日本の善政が忘れ兼ねるなどとうぬぼれてはいけません。彼等のいま当面している現実があまりに苛烈なのです。歴史の不幸が拍車となっている――、それを計算に入れて考えるべきです」
これが、活字にならなかった、記者との談話の後半だそうである。
ともあれこのようにして金素雲はパスポートを失い、ようやく取り戻したのが13年後の1965年。もう57歳になっていた。以後、韓国語・日本語の両方で旺盛に随筆や自伝などを書き、韓日辞典を編纂し、また『現代韓国文学選集』(冬樹社)全5巻を個人全訳した。一人でよくここまで、と思うほどたくさんの仕事をした人である。
だが、私生活の年譜は、もっともっと濃密だ。
紹介し始めたらきりがないが、素雲20代半ばのころに起きたことをかいつまむと次のようになる。「19歳で結婚した日本人妻と別れる→朝鮮人女性Hと急接近して婚約→Hが他の男になびいて破局→Hの妹が急接近してくる→H本人からも復縁したいと手紙が→姉妹と三角関係、実家も巻き込んで大騒ぎ→妹と結婚を決めるが、式の前日に素雲が急病で入院→病院で姉妹対決→妹と結婚を強行するも二ヶ月で破局→姉が急病で死亡」ということになる。わけがわからないかもしれない。それらのすべてのプロセスに、往年の韓流ドラマファンなら想像のつく、「よくわかんないけど決然と言い放たれるせりふ」「何だかわかんないけど思いつめた表情」がついてくるだろう。こういうのが事細かに書かれているので、やっぱり自伝『雲の涯に生くるとも』はお勧めなのである。
しかも、このことすらごく一部にすぎない。その後の素雲の恋愛行脚には、上野公園も登場する。なんと素雲は、自分に「処女を捧げる祭壇になってください」と哀願する若い日本人女性を振り切るために、不忍池を全速力で半周したというのである。なんだかなーと思うけれども、本人がそう書いているんだから仕方がない。
その上彼は結局のところ、不忍池の周りを走らせた女性の願いを聞き入れてあげたらしい。かくして彼女と素雲との間には息子が生まれるのだが、何だかんだあったあげく、彼女は他の男性と結婚してしまう。この息子は親戚の家に預けられて育つが、戦後、中学生のときに初めて父親に会う。ちょうど、素雲がパスポートを取り上げられたころのことである。
威厳を持って現れた父親は息子に涙を見せて謝り、上野の松坂屋に、学生服を買うために一緒に行く。ところが息子の回想録によれば、いざ会計のときになって、なぜか父は忽然と姿を消してしまった(!)というのだ。
まだまだ続く。息子の回想録を信じるならば、彼らはその後もう一度、まさかのことに留置所で再会しているという。息子は交通事故の加害者として、父親はおそらく詐欺罪で。
ちなみに、この息子はのちに作家になった。ペンネームを北原綴という。童話などを書いていたが、1987年に殺人事件の主犯として逮捕され無期懲役刑を宣告された。現在は80歳になっているはずだが、今もおそらく刑務所にいると思われる。
一方で金素雲には、日本の敗戦後まもなく、釜山で結婚した女性との間にも二人の娘がいた。父が韓国に長く帰れなかったので、この家族は大変な苦労をしたことだろう。上の娘の櫻(ヨン)は牧師である。日本人神学生と結婚して来日し、小岩教会の牧師をつとめ、『チマ・チョゴリの日本人』という著書も持つ。そして、韓国に残った母と妹は朴正煕・全斗煥体制に抵抗して懲役刑まで受けた人。
ちなみに、キム・ヨンさんの娘が、シンガーソングライターの沢知恵さんだ。
殺人犯から牧師、反体制活動家まで。なんという子どもの経歴の幅広さであろうか。金素雲の一筋縄で行かないところが、ここにも現れているように思う。
こう見てくると、墨の尽きるところまで一筆書きで描ける金子文子の人生と、紆余曲折が重なるだけ重なり、地上も地下も這いずり回った金素雲の人生の対比が胸にしみる。日本と韓国、もつれあったこの二つの国を二つともに、踏み抜くほどよく知ったために、金素雲の生涯は(私生活も含めて)人の二倍も忙しいものになった。
そして、その割の合わないことといったら。日本にいれば韓国の代弁をしなくてはいけない。韓国にいれば日本の事情を説明してやりたくもなる。どうにも進まない両国の理解を促進するため、日韓の文化交流の拠点として、韓国文化資料センター「コリアン・ライブラリー」を構想をし、雑誌の刊行、録音教材の製作などを手がけたが、資金不足などにより、始動からまもないうちに頓挫している。
人生73年、そのうち日本に暮らした年月は約32年。「イタチごっこの人生遍路」素雲自身はそう評した。
仮住まいにつぐ仮住まいで、2年間に7度引越したこともあるという。だから素雲の、とくに戦後のエッセイは、あわただしさの只中で、縁側に腰かけたままのような姿勢で書きつけられることもあっただろう。けれどもそれらは、今日の、質のまったく違う忙しさの中で読んでも、いつも変わらない角度で切り込んでくる新鮮さをもつ。
金素雲の名前を尊敬と懐かしさを持って口にする日本人は多い。しかし韓国では、上記の舌禍事件がなくとも彼のことを批判的に見ている人の方が多い。太平洋戦争の時代に「鉄甚平」というペンネームで、山本五十六を讃える詩を書いたことも、関係あるだろう。
だが、学歴とは縁がなかった彼は生涯、学問に深い尊敬を抱くと同時に、権威の高みで惰眠をむさぼる者に対しては、辛らつな批評眼を失わなかった。終始一貫して、日本人の韓国への偏見と、韓国人の日本への偏見を、徹底して、激越にしかも優雅に、糾弾しつづけた。
その原点が1921年の上野にある。 新聞に泥を跳ねさせて平気で通り過ぎた「乱暴なる、富める彼等」に真っ向から挑んだ1921年の気概は、死ぬときまでそのまま保たれたと思う。また、そんな「乱暴なる、富める彼等」にも わかることばで故国の人々の思いを伝えられまいか、またそれを読んだ人が、かつて自分を救ってくれた出版社の社長にように、自国の「乱暴なる彼等」を一喝する背骨を持ってくれまいか――そんな思いが行間から滲んで見える。忍の一字を胸にたたんでやっかいな調停の労を惜しまなかった、そんな横顔が見える。
若いころに読んでずっと忘れられない金素雲の一言がある。
「全世界を住家とするがよい。コスモポリタン結構である。だが、アドバルーンの一本の綱――それが郷土なのだ。」 (『日本という名の汽車』)
金素雲の味わい深い随筆の数々はいま、残念ながら古書や図書館でしか読むことができない。それは、たぐいまれな優れた日本論でもあるのだが。

