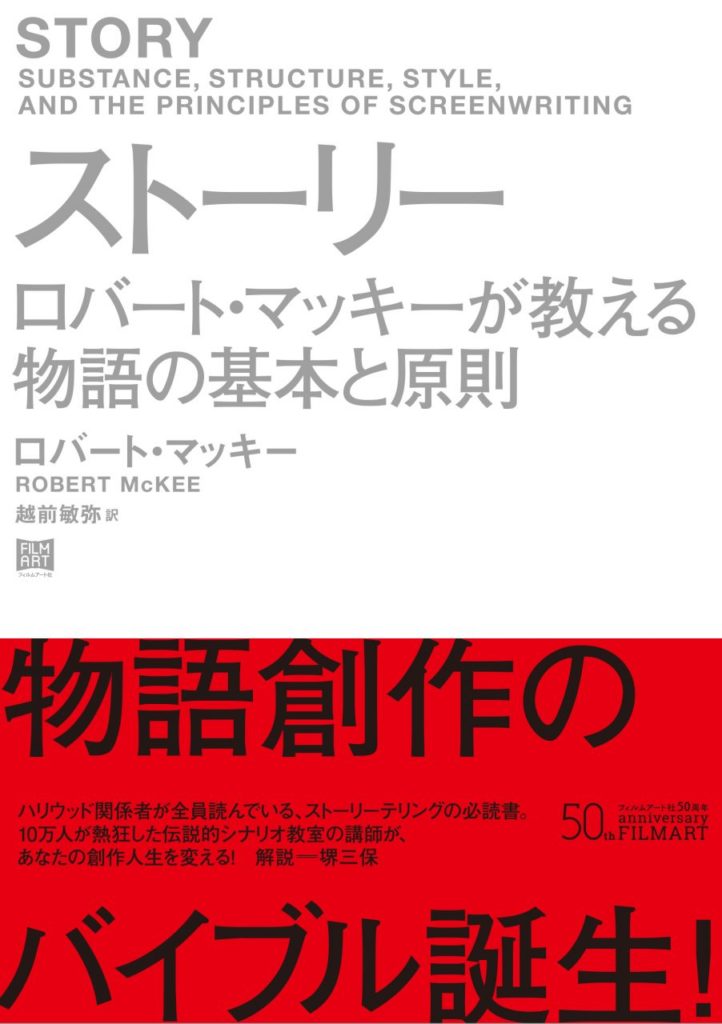山下敦弘監督とコンビを組んだ『リンダリンダリンダ』『もらとりあむタマ子』といった作品で知られ、映画『聖の青春』『ハード・コア』などの脚本も手がけてきた向井康介さん。2018年には自身初となる長編小説『猫は笑ってくれない』(ポプラ社)を発表し高い評価を得ています。
現役の脚本家として活躍する向井さんに『ストーリー ロバート・マッキーが教える物語の基本と原則』の読みどころについて聞きました。
――まずは『ストーリー ロバート・マッキーが教える物語の基本と原則』(以下『ストーリー』)をお読みになった率直な印象をお聞かせください。
向井康介(以下:向井):実はロバート・マッキーのことは知らなかったんですが、映画『アダプテーション』(2002年、スパイク・ジョーンズ監督)に出てくるシナリオ講師のモデルになっていた人なんですね。僕はシド・フィールドの本(『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと シド・フィールドの脚本術』)で物語の構造について勉強しました。
まず、この二人が述べている物語の基本的な構造や枠組みは同じなのだなということが確認できました。シド・フィールドの本は三幕構成に特化している本といえると思いますが、『ストーリー』はそこを踏まえつつ、物語をつくるさまざまな要素についてかなり網羅的に分析・解説している本だなという印象でした。
――そもそも物語の作り方を「学ぶ」ということが必要なのか、あるいは可能なのかということについてどのようにお考えですか? 本書の解説でも堺三保さんが「アマチュアはもちろんプロの間でも、脚本や小説の執筆に関しては『教えられない』ものであるとして、教育不可能論や教育不要論を唱える人たちがいる。」と書かれています。
向井:自分の過去をふりかえってみて、学生時代にもっと積極的にこういう本を読んでおくべきだったと思いますね。僕が最初に体系的に脚本のことを学んだのは、大阪芸術大学の学生だった頃です。「シナリオ創作論」という授業で、講師は中島貞夫さんでした。ペラ20枚、60枚、90枚と毎年分量を増やしながら脚本を書いていくのですが、そこでは「ストーリーから書くな」と教えられるんです。「ストーリーではなく、キャラクターを作り出すんだ」と。A4の紙にこの人間がどういう生い立ちでどういう人間なのか、というのを徹底的に書いてこい、といわれるんです。それができたら物語は勝手に生まれるんだ、という教えでしたね。なので「そうか」と思ってずっとやってたんですけど、なかなかうまくいかなかったんですよね(笑)。
――それはなぜだったのでしょうか。
向井:その時は自分が悪いと思っていたんですよね。キャラクターの掘り下げが足りないからストーリーが出てこないんだな、と。学生時代には自主映画をつくっていましたが、自主映画時代は、脚本の体系的な知識を学ばなくてもセンスで通用したんですよ。山下くん(映画監督の山下敦弘)と僕がつくる会話とか日常の切り取りかたとか、そういうセンスで評価されていた部分があります。でもいざ別の監督で商業映画ということになったとき、全然勝負できなかったんです。「こんなにできないんだ」ということを痛感して、そこからシド・フィールドの本などを読み始めたんです。
――その時期というのは、作品でいうと『リアリズムの宿』(2003年)あたりですか?
向井:いや、『リアリズムの宿』のときは、まだセンスが通用していましたね。明確に意識が変わったというのは『リンダリンダリンダ』(2005年)くらいでしょうか。20代後半あたりですね。『リンダリンダリンダ』も最初はセンスで勝負しようとしていたんです。あとこれまで観てきた映画を参考にしながらなんとかしようとしていました。ロバート・マッキーがやっちゃダメといいそうなことを全部やっていました(笑)。
でもシド・フィールドを読んで、「あ、三幕構成なんだ」ということを知り、これはずいぶんと便利なものだなと思いました。もうちょっと早く知っておけばよかったなとその時に思いましたね。
僕はシナリオ講座で講師をやっていたことがあるんですが、周りの先生の中には「これは教えられるものではないんだ」ということをおっしゃる方もいました。確かにそういいいたくなる気持ちもわかります。例えば「いま自分がこの世界をどのように見ているのか」といったようなことはやはり教えられないものだと思っています。でも「何をどう書くか」の「何を」の部分は教えられないかもしれませんが、「どう書くか」については教えられるんじゃないかなと思っています。
脚本を書く上での「テクニック」みたいなものは確かに存在するわけです。例えば小さなテクニックですが、説明台詞を説明っぽくなく処理する方法。説明台詞は自分でしゃべるとシステムになってしまうので、あえてその人物にしゃべらせないで、第三者にいわせるとか。銀行強盗をするシーンで、事前に段取りを説明するシーンがあると、本番では必ず失敗する、という伏線の作り方とか。そういう細かいテクニックは撮影所システムの頃はみんな教わっていたはずなんですよね。もしくは先輩から盗む機会を与えられていた。そういうものを「教えられない」といってしまうのもちょっと違うんじゃないかなと思っています。
大きな枠として三幕構成というものを利用して、そのうえで細かい実践的なテクニックもどんどん教えていくというスタイルなのが、三宅隆太さんですよね。以前、三宅さんと対談させていただいたことがあったのですが、多くの気づきがあってとても面白かったです。

――本書『ストーリー』やシド・フィールドの著作などはいわゆる「ハリウッド式」の脚本メソッドですが、それが日本でも通用するのかということについてどう思われますか?
向井:通用しますし、ものすごく使えるものだと思いますね。というのも例えば小津安二郎の野田高梧脚本の作品なんかを見ても、わりとハリウッド式の物語構造に当てはまりますからね(野田高梧の脚本メソッドがわかる本として『シナリオ構造論』がある)。脚本をトレースしてみると、物語の構造はもちろん、登場人物の出し入れ、それと葛藤のつくりかた、[父/娘]、[嫁ぐ/嫁がない]というような対立構造は、『ストーリー』でいっていることとびっくりするくらい似ています。日本の昔の映画人は当然ハリウッド式の脚本メソッドなんか知らないで映画をつくっていたわけですが、それでも似てくるということは、やはり2時間でお話を完結させないといけない場合の、人間が心地よいと思えるような物語の大きなうねりというのは世界共通なんじゃないかなと思います。それが物語の世界で「起承転結」とか「三幕構成」という言葉で表現されているのかなと。
「起承転結」は日本では馴染みがあります。「起」と「転」と「結」はいいんですが、「承」が難しいんですよ。何をやっていいのわからなくなるんです。でも「三幕構成」だとそこがすんなりと通るようになりました。
――用語についてはどうですか? 『ストーリー』の中でロバート・マッキーはストーリーの構成要素を大きい順に【ストーリー>幕>シークエンス>シーン>ビート】と整理しています。これもやはりハリウッド式なのでしょうか。
向井:「ビート」という用語は使いませんね。「シーン」、「シークエンス」などは普通に使いますが。そういえば、日本の脚本の世界で「箱書き」という言葉がありますが、これはハリウッドでいうところの「ビートシート」に相当するものなんじゃないかなと思います。付箋を壁にペタペタ貼って順番を入れ替えたりする作業を僕もやっています。
――ロバート・マッキーはジャンルを意識することの重要性を説いていますが、向井さんはどのように思いますか? 「観客が予想していることを予想するためには、自分のジャンルとその約束事に精通しなくてはならない。」(本書113頁)
向井:僕がジャンルを本当に意識して書いたのはホラーだけなんですよね。Vシネみたいなので。でも大失敗してしまいました(笑)。僕にはホラーは書けないなと思いました。僕の中ではジャンルは「ホラーかそれ以外か」という感じなんです。ホラーだけは方法論が違う感じがする。観るのは大好きなんですけどね。ホラーは「見せ方」が大事なジャンルだと思うんですよ、視覚的に。
僕が映画を観るときは、それがどんなジャンルであれ、この映画が本質的なところで何をどう描いているのかに注目して観てしまうので、ジャンルはあまり気にならないんですよ。ジャンルというのは、ある種の洋服のようなもので。それよりも裸が見たい、というか。
――初期の向井さんは山下監督とともに「青春映画」のジャンルの人という認識をされていたように思いますが、向井さんには青春映画をつくろうという明確な意思はなかったのでしょうか?
向井:確かにそういう言い方をされてましたね。特に『リンダリンダリンダ』でそのイメージが強まったのかと思います。でも僕は全然意識はしていなかったです。『どんてん生活』(1999年)の頃からそうなんですが、それしかテーマがなかったというだけなんです。引き出しも何もなくて。なんの挫折もしていないし、失恋くらいでしょ、経験といえば。だからどうしても青春モノになってしまう。
――本書の大きな特徴として物語の構成と登場人物の関係性を以下のように整理したことが挙げられると思います。「構成と登場人物のどちらが重要かという問いには意味がない。というのも、構成が登場人物を形作り、登場人物が構成を形作るからだ。このふたつは等しいものであり、どちらが重要ということはない。」(本書125頁)とあります。
向井:まったくその通りだと思いますね。学生時代に中島先生の教えに従ってキャラクターを徹底的に掘り下げるという方法論で物語をつくろうとしましたが、やっぱりうまくいかなかった。
例えば、ある殺人事件が起こったとします。この殺人事件でどのようなことが起こったのか、ということを知りたいと思って映画をつくることもあると思うんです。その場合は、事象というか側(がわ)から入ってキャラクターにクローズアップしていくことになると思うんです。そうではなく、昨年の出来事ですが、行方不明になった子供を見つけたボランティアのおじさんがいましたよね。あのおじさんというキャラクターから入って物語を作り始めることもあるわけです。なので、やはりどちらが先ということではなく、お互いが関係しつつ物語ができているということなのだと思います。
おそらく中島先生も、ロバート・マッキーと同じような考え方をしていたのだと、今振り返って思いますね。だけど、若い学生に脚本を書かせるときには、お話優先よりもやはり人間を掘り下げなければならないんだと、物を語るためにはまずはキャラクターを立てるのが基本なんだと、そういう意図があったんだと思います。
――向井さんはどのようなところから物語を作り始めることが多いですか。
向井:プロの脚本家というのは、基本的には受注の仕事なので、こういう話を書いてくれ、この俳優のために書いてくれ、というオーダーがあることがほとんどです。『ストーリー』やシド・フィールドの著作などは、ゼロから物語をつくろうとしている人たちに向けて書いているので、その点が日本とハリウッドの違いなのかもしれません。
アメリカでは純粋にいい脚本を書いて、それを売って生計を立てている人がいますよね。脚本は売れているけど一本も映画化されていない、でも生計は成り立っているという人もおそらくいるわけです。
――例えば『リンダリンダリンダ』の場合は、どのようなオーダーで書かれた脚本なのでしょうか。
向井:そもそもはコピーバンドのトーナメント戦でブルーハーツのコピーバンドをしている女の子たちが勝ち上がって優勝する、というような物語でした。でもなかなかうまくいかず、山下くんもその物語に面白みを見いだせずにいました。
でもよくよく話を聞いてみると、「ブルーハーツ」「女の子」「コピーバンド」という3点を守れば、あとはどんな話でもいいということがわかったので、だったら高校の学園祭でしょ、ということになり、学園祭での3日間という物語の軸ができたんです。そこで初稿を書き始めたという感じです。
――ゼロから話を立ち上げることとプロになって受注で物語をつくることに違いはあると思いますか?
向井:あまりないんじゃないかと思うんですよね。ゼロから何かやってください、といわれたときでも、結局題材を探すことになると思うんですよ。向こうからくるのか、こっちで探すのかの違いはあるにせよ、物語をつくるという本質的なところではまったく一緒だと思います。僕の場合、ニュースを見ていても、本を読んでいても「あ、これ映画になるな」というのを見つけるときがあるんですよ。「ここさえあれば、できる」というようなものが。それを見つけられると安心しますね。例えば、大きな事件でも全然物語にならないなというようなものはよくありますし。その見つけ方や気づき方がその人の脚本家としての個性になっていくんじゃないかと思うんです。
――日々の読書もやはり脚本家目線になりますか。
向井:なりますね。ノンフィクションは特に大好きなので、そういう読み方になってしまいます。でも自分が好きだと思ったものはだいたいダメなんですよね。プロデューサーが乗ってくれないんです(笑)。
――『もらとりあむタマ子』(2013年)はオリジナル脚本ですよね。
向井:そうですね。あれは前田敦子さんで何かやってくれ、というオーダーでつくった作品です。山下くんは女性を色っぽく撮るタイプの監督ではないので、その逆で行こうと思いました。最初は、前田敦子さんと子どもを撮りたいと思っていました。『なまいきシャルロット』(1985年、クロード・ミレール監督)みたいな感じで。で、宝探しをするという。結局全然違う映画になってますけど。
でもどうもうまくいかなくて。当時前田敦子さんはAKB48を卒業したばかりだったので、本人の環境に重ね合わせて、地元に帰ってモラトリアム状態にあるという物語にしようと思いました。実家で就職せずにダラダラしているという、自分たちのなかでは定番の設定なんですけどね(笑)。
最初はオムニバム作品だったんですよ。秋・冬・春・夏の四季をテーマにした15分×4本の。映画を撮るつもりはなかったんです。でも、最後の夏のパートを撮るときに、少し長くしてくれといわれたんです。そうすると、まとめて70分くらいになって上映できるということで。なので、夏のパートだけ急にドラマが始まるんです。お父さんの再婚話があって、自分の世界が脅かされるという。そこには当然「葛藤」も盛り込んでいます。
――120分というような長尺のストーリーではなくても、物語の中に葛藤の要素は必要ですか。
向井:そう思いますね。おそらく30分を超えたあたりから、物語の構成を考えないといけませんね。『深夜食堂』のときもそうだったのですが、そこでは三幕構成を意識しますね。
――葛藤というお話が出てきましたが、マッキーはこのようにいっています。「わたしの経験から言うと、ストーリーを設計するうえで最も重要でありながら、最も理解されていないのが、敵対する力の原則だ。脚本とそれに基づいて制作された映画が失敗する最大の理由は、この基本原則を顧みないことにある。」(本書380頁)
さきほど小津の映画にも葛藤がある、というお話をされましたが、向井さんが葛藤や対立について意識的になったのはいつ頃でしょうか。
向井:それはシド・フィールドの本を読んでからですね。例えば、『ハード・コア』(2018年)では、主人公の権藤右近に敵対する存在として「社会そのもの」があります。そしてもっとわかりやすいものでいえば水沼というキャラクターが存在しています。やはり葛藤や対立というのは物語をつくるうえで絶対に欠かせないものだと思っています。

――本書には「映画のダイアローグを書くにあたっての最高の助言は、『書かないこと』だ。映像で表現できる場合には、台詞を一行も書く必要はない。」(本書474頁)とありますね。
向井:台詞のない脚本が一番素晴らしいと思います。といいつつ僕はダラダラ書いてしまうんですけど。でもその場合でもできるだけ本音をしゃべらせないように気をつけています。つまり本当のことを台詞でいわせず、いかに遠回りさせるかということを考えます。台詞ではなく、アクションとシーン運びで分からせることができれば、それが一番素晴らしいことですよね。昔からそうですよね、『丹下左膳余話 百万両の壺』(1935年 山中貞雄監督)とか、お宝をめぐってあれこれしているのが面白いという。
要するに「映像で語る」ということです。映像で語れなくなったときに、台詞が出てくるというのが理想でしょう。でも最近は少し変わってきているのかもしれません。僕も海外ドラマは好きでよく観てますが、延々しゃべってますもんね。
それでも上手い台詞の使い方ってあるはずなんですよ。よく例えに出すんですけど、「君のことが好きだ」としゃべらせてキスをする、というシーン。この場合、台詞は要らないんですよ。キスをすればいいだけなので。「好きだ」といわせておいて、キスをしないのであればまだいいのですが。二つあることで意味が重なってしまっているんです。
でも「君のことが嫌いだ」といってキスをすれば両方に意味が生まれますよね。観ている人が「あれ、何だろう」と考えますよね。そういうのが上手い台詞なんじゃないかと思います。これは『恋人たちの予感』(1989年、ロブ・ライナー監督)のラストなんですけど。
――マッキーは「文才とストーリーの才能はまったく別物であるばかりか、互いの関連もない。ストーリーを語るには、書くことは必須ではないからだ。」(本書40頁)ともいっています。
向井:そうですね。必要なのは文才ではないですよね。台詞は文才じゃないですしね。小説家の書く台詞というのは「読ませる台詞」だと思うんです。僕らが書いているのは「しゃべらせる台詞」です。小説『猫は笑ってくれない』(ポプラ社)を書いているときに、自分の書く台詞って軽いなと思いました。小説家の書いている台詞はしっかりしていると思いますが、その一方で脚本の台詞としては使えないな、とも思いますね。
――キャラクターについてお聞きします。マッキーは「登場人物の設計は、ふたつの重要な要素である『性格描写』と『実像』をどう位置づけるかからはじまる。」と述べています。「性格描写は、観察できるあらゆる特徴をまとめたものであり、その組み合わせによって、唯一無二の登場人物が作られる。」(本書453頁)一方「『実像』は窮地に陥って選択を迫られたときにのみ、明らかになる。緊迫した状況で対応の仕方こそがまさしくその人自身であり、重圧がかかるほど、おこなう選択はその人物の本質に迫るものとなる。」(本書454頁)
キャラクターを創作するうえで、「性格描写」と「実像」を意識して書くことはありますか?
向井:そこまで分析的に考えたことはないんですが、実際には頭の中で同様のことをしていると思います。例えば、ある登場人物を考える際に、この人物はこういう職業「なのに」こういう行動をとる、とか。そういうことをキャラクターづくりの際にまとめてやっていますね。
あるいは、こういう「実像」を描きたいから外面(そとづら)をあえてこのように設定する、ということもあります。すごくみんなに慕われている町医者なんだけど、実は藪医者だったとか。これは『ディア・ドクター』(2009年、西川美和)ですが、それがそのままストーリーに絡んでくる話になるので、やはり物語と登場人物は相互に関連しあっているといえると思います。
――小説『猫は笑ってくれない』を執筆され、脚本と小説という異なる表現方法で物語を創作されていますが、両者の違いのようなものはありましたか?
一度雑誌『文學界』で短編小説を書いたことがあって(「あと一匙」2014年11月号掲載)、その編集者の方に、次作として提出した作品があったのですが、ボツを喰らってしまったんです。それ以来その作品には手をつけずにいたのですが、もったいないなという気持ちもありましたし、もう少し書き足したい部分もありましたので、知り合いにポプラ社の編集者の方を紹介してもらい、まずは季刊誌で連載、その後単行本化という形になったのがこの作品です。なので、もともと存在していた作品にいろいろと付け加えていったという経緯があるので、『ストーリー』やシド・フィールドの本のようなメソッドは使っていませんね。
――この小説では、作中にシド・フィールドの名前が登場したり、三幕構成とは何かということについて登場人物が言及したりしていますが、作品自体を三幕構成でつくるというアイデアはありませんでしたか?
向井:そういうメタ的なことをやろうと思ったのですが、うまくいかなかったです(笑)。頑張ったんですけどね。そういうことをやる余裕がありませんでした。僕は今回できなかったですけど、『ストーリー』を読んで小説を書く人は絶対今後たくさん出てくると思いますよ。ミステリなんかは特に。
それは僕の今後の課題でもあるんですよ。『ストーリー』やシド・フィールドのメソッドで小説を書くということを今後やってみたいなと思っているんです。『文學界』に小説を書いたときには、担当の編集者の方から「書きたいことから書き始めていって、もうこれ以上書きたいことがなくなったら終わればいい」というアドバイスをもらって、「ああ、そうか。まあそりゃそうだな(笑)」と思った記憶があります。純文学の人は大変だなと思いました。
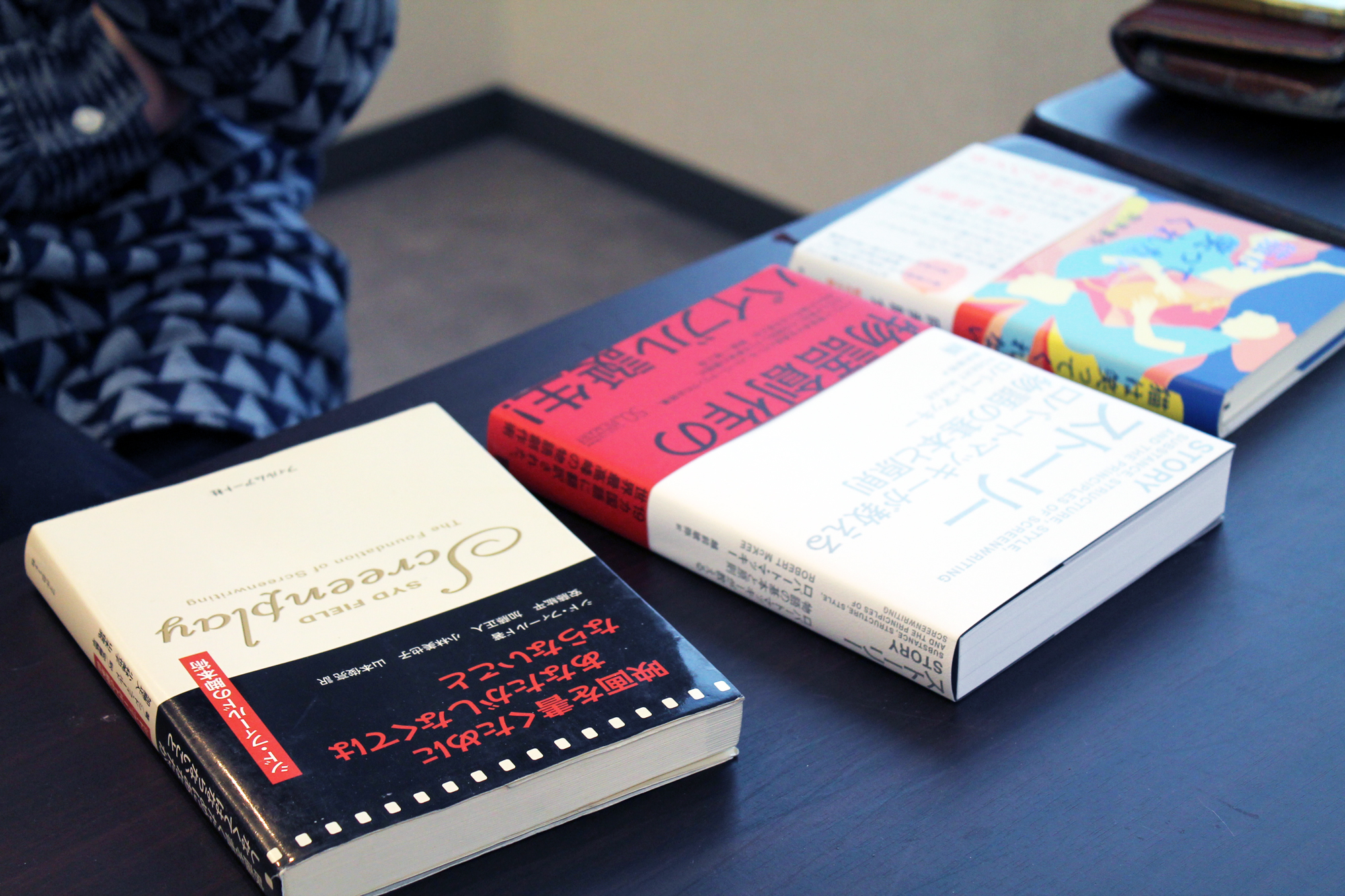
――これから脚本家になりたいと思う方は、本書『ストーリー』をどのように読めばいいでしょう。アドバイスがあればぜひ教えてください。
向井:この『ストーリー』は創作をするうえで、間違いなく大きな手引きになってくれるものだと思っています。僕自身の読み方・使い方をいうと、僕はある程度自分のキャリアなり方法論がありますので、まず自分なりに書いてみるんです。そこからその初稿に、本で書かれていることをあてはめてみるんです。例えば三幕構成であれば、「ここがプロットポイントなのか」とか「ここが2回目のプロットポイントで、真ん中はどうなっているのかな?」とか。そういう使い方をしています。もしあてはめてみた結果、プロットポイントが遅いなら、直すのか、あえて遅くするというのか、という選択をすることが可能になります。
みなさんもまずは『ストーリー』を最初から最後まで読んでみて、実際に出来上がったものをもう一度この本にあてはめてみるという作業をしてみるといいと思います。そうするとものすごく大きな気づきがあると思います。特にゼロからオリジナル脚本をつくろうと思っている人はものすごく参考になると思いますよ。
2019年1月12日 京都出町座にて