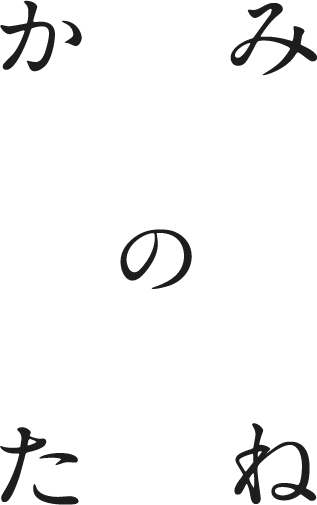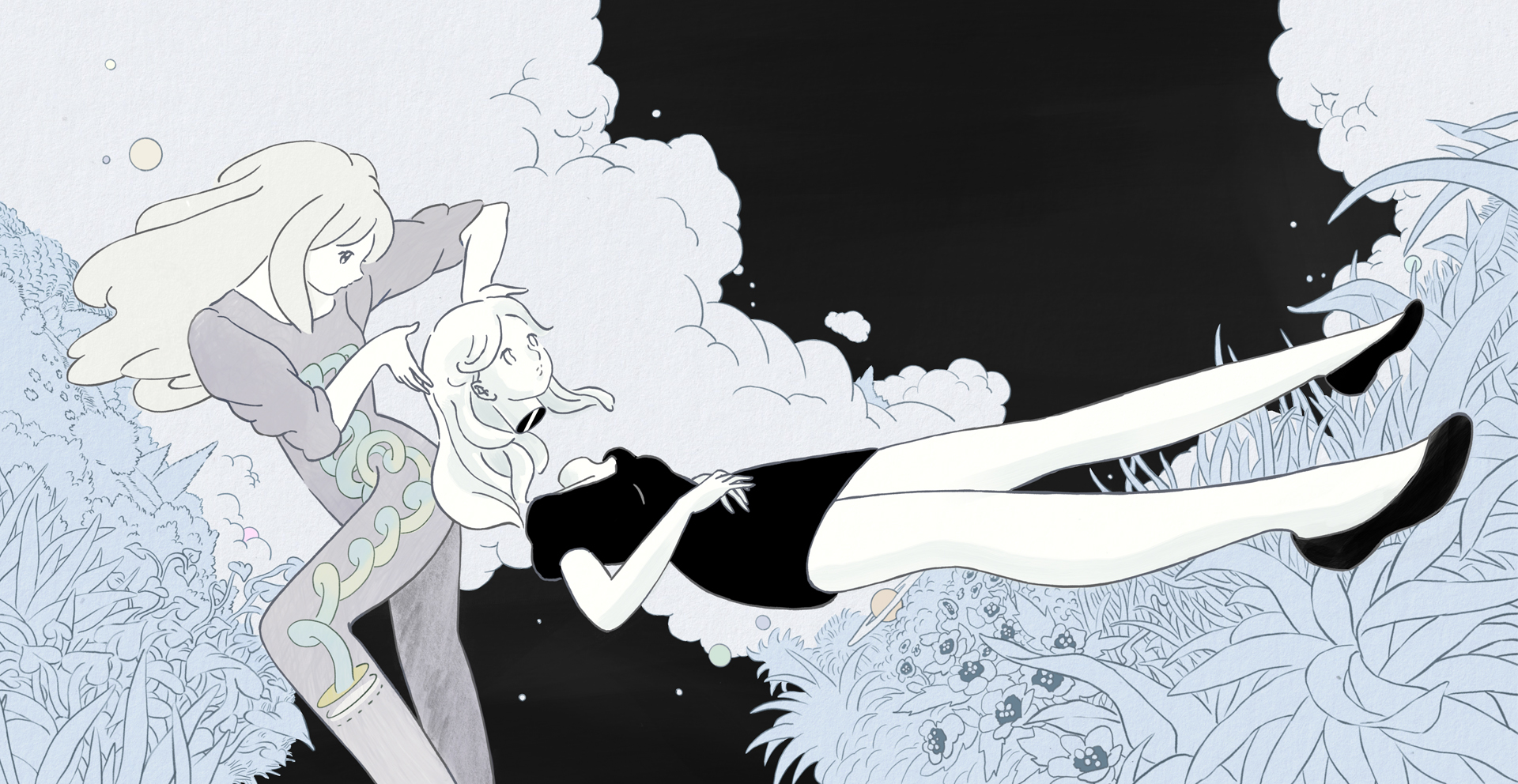我々はもう、持って生まれた自分の身体で踊らなくとも構わないのかもしれない──3DCG、VTuber、アバター、ゴーレム、人形、ロボット、生命をもたないモノたちの身体運用は人類に何を問うか? 元ダンサーで医師でもある若き批評家・太田充胤が、モノたちと共に考える新しい身体論。
─
複製される芸術作品はしだいに、あらかじめ複製されることを狙いとした作品の、
複製となる度合を高めてゆく。[1]
──ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術作品』
新しい身体
アプリケーションを立ち上げると、画面には真っ白な空間が現れる。
いや、正確には、画面の中央に表示されたのは白い四角形、そしてそこに引かれたいくつかの線である。しかし直観的には、その奥に果てしない空間がひらけていることが明らかだ。水平面には碁盤の目状に線が敷かれ、原点からはXYZ方向に赤・青・緑の3本の矢印が伸びている。マウスでドラッグすると、原点を中心として碁盤とXYZ軸がぐりんぐりんと回転し、画面の奥の白い空間が天地の別を失う。
それが空間であることを確かめるのに飽きると、「ファイル」のタブから3DCGモデルのファイルを呼び出し、白い空間上にモデルを展開してみる。原点上に、両腕を左右に広げ十字のようにして直立する「初音ミク」のモデルが現れる。再びマウスでドラッグすると、今度はモデルが画面の中で縦横無尽に回転する。
モデルの肢体をカーソルでなぞる。モデルは内部にいかなる構造物も持たないが、仮想的な骨格を仕込まれている。骨格同士をつなぐ関節をカーソルで触れると、球体状の矢印がポップアップする。右前腕が、右肘関節を支点としてレバーのようにあらゆる方向へぐにゃりと曲がる。あちこちの可動関節で角度を調整し、モデルを粘土のようにこねくり回すうちに、だんだんとそれらしいポーズが出来上がる。仮想空間における身体運用とは、粘土細工のごときものであると知る。
ポージングにも飽きると、今度はインターネット上に流通するモーションデータを漁り、適当なものをダウンロードしてモデルに割り当てる。どこかの誰かのダンスをトレースして作られたモーションデータには、モデルが1コマ毎に動かすべき関節とその角度がくまなく書き込まれている。読み込みが終わった瞬間、ぱっ、とモデルの体が反応し、まるで音楽が鳴りだすのを待つようにして、いつのまにか新しいポーズを取っている。はやる気持ちを抑えて楽曲データをダウンロードし、アプリケーション上にドロップする。再生ボタンを押すと、モデルはついに私の手を離れ、ひとりでに踊りはじめる──。
新しい身体論を書いてください、といういささか荷の重いお話をいただいてまず想起したのは、どういうわけかゼロ年代の終わりに見たあの光景だった。
デジタルとアナログが混ざりあい、機械と生体が混ざりあい、そのあわいであらゆる手段を通じて身体が運用される今日、わざわざ身体について語るというのならば、まずあの奇妙な光景、無機質で無表情な3DCGのボディが生命の躍動を獲得するあの瞬間について、語らないわけにはいかないような気がした。
くだらないと思うだろうか? そうかもしれない。たとえば自分の身体で踊ることに生涯をかける人たち、あるいはそのような身体表現を好み語る人たちは、CGのダンスなど語るに値しないと一笑に付し、そんなものをダンスと呼ぶことすら嫌悪するだろう。逆に、CG映像やアニメ表現を普通に消費することに慣れてしまった人たちには、もしかしたら画面の中に「身体」があるという感覚すらピンとこないだろう。
ただ、あのとき私が踊る3Dモデルを眺め弄りながらたしかに感じたのは、我々はもう持って生まれた自分の身体で踊らなくとも構わないのかもしれないという、解放感にも似たなにかだった。
件のアプリケーションの名は「MikuMikuDance」という。通常、頭文字をとってMMDと略される。
魂の実装
お示ししたのは、2011年にMMDで作られた動画のひとつである。「初音ミク」を使って作られた「可能世界のロンド」という楽曲に、「初音ミク」の3Dモデルを使った動画を合わせたものである。
「初音ミク」とは2007年に発売された音楽編集ソフト「VOCALOID」シリーズの一商品であり、同時にその商品のイメージキャラクターの名称でもある。床まで届きそうな緑色の長髪、手首より長い袖にミニスカートにサイハイブーツ。いかにもアニメ然としたこの16歳の女性が、仮想楽器となってインプットされた通りに歌う……という設えの人工音声ソフトで、発売わずか半年で3万本という異例の売り上げを記録した。ヒットの背景には技術的な目新しさもあっただろうが、近未来感のあるキャラクターの造形もその流行に一役買ったのは間違いない。実際、多くのユーザーが「初音ミク」に歌わせてみたいと考えた。同ソフトを用いて制作された楽曲は、当時黎明期にあった動画共有サイト「ニコニコ動画」に投稿され、しばしば数百万の再生回数を達成した。
人工音声だったはずの「初音ミク」が現れるところは音楽にとどまらなかった。あるユーザーが「初音ミク」の3Dモデルを制作してネット上に公開すると、他のユーザーたちがそれをダウンロードし、「初音ミク」が歌い踊る3D映像を作ってニコニコ動画に投稿するようになった。それはまるで、パソコンの中に生息するホムンクルスのようだった。いつしか「初音ミク」はネット上を独り歩きし、ネット上に遍在するようになっていた。
「可能世界のロンド」もそんな無数の動画のうちのひとつで、当時の驚きと興奮がわかりやすく視覚化されているよい例である。
冒頭、真っ白な大きい部屋の奥でポーズをとる、機械のような「初音ミク」モデルのロングショット。両脇には人形使いの手のように、天井から一対のマシーンアームが伸びている。長くミニマルなイントロのリズムとともにゆっくりとカメラがクローズアップ。ピアノのアタックを合図に、マシーンアームにぐりぐりと操られてモデルがロボットダンスを始める。
ボーカルが入ると画面が一転し、今度は図書館のような温もりのある部屋で、表情豊かで生き生きとした別の「初音ミク」が歌っている。その動きの自然さは、一ユーザーが無償のツールで作ったものとしては驚くべき水準で、当時この動画には敬意をこめて「魂実装済み」のタグがつけられた。「魂実装済み」とはVOCALOID楽曲やMMD動画に対してよくつけられていたタグで、デジタルの表象に人間のような息吹を感じ取ってしまう視聴者の感慨を言い表したものである。「可能世界のロンド」に関してもう一歩踏み込むならば、この短い動画のなかに我々が見出したのは、機械あるいはCGオブジェクトに過ぎない「初音ミク」が魂を獲得するプロセスであっただろう。
間奏、カメラは再び白い部屋に戻ると、中心にモデルを捉えたままゆっくりとズームアウトする。ロボットアームは天井に畳み込まれ、モデルは動力源を失ったかのようにぱたりと動きを止める。カメラとモデルのあいだに、一枚、また一枚とシャッターが下ろされる。何枚かのシャッターが下ろされると、今度はカメラがズームをはじめ、シャッターは一枚ずつ上がっていく。
最後の一枚が開き、カメラがふたたびモデルを捉えた時、彼女はすでにロボットアームの元を離れ、ひとりでに踊り始めている。クラシックバレエの型で、ぎこちなく、しかし軽やかに踊るさまに、たしかに我々は魂に限りなく近いなにかを感じとる。そしてその後も繰り返される白い部屋と図書館のモンタージュを通じて、機械の「初音ミク」と魂実装済みの「初音ミク」が、おそらくは連続した同じ個体の過去と現在であることを直観する。
操り人形やロボットが人間の手を離れ、「魂」を宿し、それ自身の身体運用を始める──モチーフ自体は、むしろ極めて古典的である。「魂実装済み」という驚きも、一ユーザーがMMDで作ったからこそのものにすぎない。CGを駆使して作られた「自然な」映像表現は、当時の感覚でもさして珍しいものではなかった。
しかし、その魔法のような技術が自分の手中にあるとなれば、話はまったく別である。MMDの登場とはつまり、オブジェクトに生命の息吹を吹き込む魔法が民主化されたことを意味するものであった。
仮想空間で踊る
MMDは名前の通り、そもそもの初めから「初音ミク」という存在しない身体に魂を与え踊らせるために開発されたソフトウェアである。
開発したのはVOCALOIDの版元ではなく、ニコニコ動画ユーザーの1人だった。そのユーザーはニコニコ動画で「初音ミク」のモデルを目の当たりし、どうしても自分の手で動かしてみたいと考えた。これまで3D映像など作ったことはなかった。既存の3D動画作成ソフトを使って試行錯誤したあげく、ついに「初音ミク」が踊る動画の作成に成功したものの、それがあまりに大変だったことから初心者でも使いやすいソフトを作ることにした。
こうしてゼロから作り上げられたMMDの操作性と手軽さは、画期的だった。知識のないユーザーでも、ウィンドウの中の白い空間にモデルを展開し、コマ毎にポーズをつけ、音楽を展開するだけで、簡単に「初音ミク」を踊らせることができた。2008年にMMDがフリーソフトとして配布されると、「初音ミク」を踊らせた動画は爆発的に増加した。
まるでそこにひとつの生態系が発生するように、無数のユーザーの手によって周辺環境が整っていった。「初音ミク」以外の豊富なモデルの制作、モデルが踊るための背景の制作、モデル編集や動画の映像効果のためのツール……。あまつさえ、既存のゲームデバイス「Kinect」を使ったモーションキャプチャ技術を、MMDと連携するユーザーまで現れた。存在しない身体を踊らせるだけではなく、自らもまた仮想空間で踊ることができるというわけだ。
当時ストリートダンスに熱中していた私もまた、そこに見え隠れする可能性に惹かれた。基本的に怠け者だった私はある日、MMDなら自分の身体で踊るよりも楽なのではないかという天啓を得たのである。
ぱっと思いつくだけでも、MMDにはいくつかの革命的な使い道があるように思えた。たとえば、振付や実際に踊られたものの記録媒体として。あるいは、自分の運動を理想的に調整したり、自分の身体を複数化することすら可能な新しい表現の媒体として。
ダンスを三次元の情報として記録する方法は当時なかった。3DカメラもVRゴーグルもまだまだ普及していなかった頃だ。記録媒体はもっぱら、スマートフォンについた二次元のカメラである。スマートフォンを鏡の下に立たせて、自分が踊るのを撮影したり、他者が踊るのを撮影したりするわけだ。ただ、二次元の動画は踊られたもののすべてを記録してはくれない。肉体に発生するテンションや力の向き、流れ、ニュアンスを記録するためには、まるでシャーロック・ホームズの『踊る人形』のようにメモ帳に棒人間を書きつけなければならなかった。もし、3Dモデルに(で)振付のメモを書きつけることができたなら、棒人間のメモよりもよほど解像度が高いだろう。
しかし無数の動画を眺めているうちに、もっと大きな可能性があることに気がついた。そもそも踊られたものをモーションキャプチャによって取り込むことが可能なら、記録や記述に関する悩みの大部分は解決する。いや、それだけではない。こうして記録された身体運用は、それ自体が編集し複製することの可能なデジタルデータでもあるはずだった。
身体運用の複製と編集
自分の身体を現実空間で運用することは、時として非常に難しい。出力を客観的に評価することすら容易ではない。歌唱なら自分で聴いて、音が外れていると思えば軌道修正したらよい。運動とその調整のためのフィードバックループは比較的自然に成立する。ダンスではそうはいかない。出力の評価は常に視覚に依存し、我々は自分の身体を直視できない。
第三者がいれば言葉によるフィードバックを受けることもできるが、自分ひとりなら鏡を見るしかない。困ったことに鏡というのはあまりアテにならないもので、そこに映る自分の姿はだいたいにおいて実際よりも理想化されている。
おそらく鏡に映った視覚的なイメージが、内的な運動のイメージ、言い換えれば頭の中の「かっこよく踊っている自分」、あるいはそのイメージの源流にある「かっこよく踊っていたあの人」のほうへと引っぱられて歪むのであろう。こうした自惚れからアマチュアダンサーが独力で抜け出すためには、普通は動画撮影を必要とする。自分が踊ったものを、動画に撮って確認しては絶望し、理想像とのズレを修正してもう一度踊りなおし、それをまた動画に撮って……というプロセスを繰り返すわけである。一応はこれをフィードバックループと呼ぶことができなくはないが、自然さとは程遠い。
しかし、もし仮に、踊られたものが三次元のモーションデータとして保存されるならば、運動と調整のループには新しい選択肢がひとつ加わることになる。踊られたものの軌跡は踊られた瞬間から自分の身体を離れ、仮想空間に複製される。軌跡をモノとして扱い、粘土細工のように加工することが可能であるならば、完成されたダンスパフォーマンスに至る工程のすべてを生身の体で完遂する必要はもはやなかった。ある程度のところまでは自分の肉体で踊り、以降はモデルの肉体で造形する……いわば身体運用のハイブリッドの可能性が、すぐそこに見えているように思われた。そして、そのようにして完成されたダンスもまた複製可能なモノであるとするならば、CDに書き込まれた複製音楽をあらゆるプレイヤーで再生できるように、私の身体運用を私以外の肉体で再生することができるはずだった。
私の身体運用を再生する身体とは、ある意味で私そのものであるように思えた。私は一つの画面上で複数の私が踊るさまを夢見た。完璧に調整された私の身体運用がデータとしてインターネットの海を漂い、やがて漂着した見ず知らずの誰かの端末で、私とも私のモデルとも無関係な肉体において再生されるのを夢見たのだ。
残念ながら、これらの夢は今日なお実現していない。
当時金のない学生だった私には、モーションキャプチャの環境を導入する余裕もなかった。もっとも今思えば、Kinectを導入したところで今度はモーションキャプチャの精度や解像度が問題になっていただろう。仮に踊られたものを首尾よくデータ化できたとして、それを調整する作業もまた思い描いたようにはいかなかっただろう。モデルを粘土細工のように捩じって1コマずつ動きを調整する作業は、予想をはるかに超えて面倒だった。同じ理由で、棒立ちのモデルにゼロから振付をつけていく方法も、私にとってはまったく現実的ではなかった。
ただし、それはあくまでも、私個人にとってはという話である。民主化された魔法と広く開かれたプラットフォームは、集合知的に、生態系的に、いつのまにか私の夢想をある程度は現実のものとしつつあった。
遍在する身体運用
MMDで生成される3Dモデルのダンスは、ざっくり分解すると「楽曲」「モデル」「モーションデータ」の3要素からなっている。現実空間で言えば「モデル」はダンサーの肉体に、「モーションデータ」は振付および運動に相当する。この3要素がインターネット上に安定的に供給され流通しているかぎり、仮想空間のダンスは事実上無限に生成され続けることになる。
MMDが公開された時点で、踊られるべき「楽曲」はすでに無数に存在し、日々増殖を続けていた。言うまでもなく、普及したVOCALOIDがその供給源となったからである。「モデル」について言えば、「初音ミク」以外にもたくさんの魅力的な「モデル」がデジタル人形師たちによって造形されるであろうことも想像に難くない。不思議なのは「モーションデータ」であろう。人形師や動画制作者が、ダンサーや振付師としても有能であったケースがそう多いとは思えない。さて、「モデル」の身体はいかにして運用されたのか。この問いは、実は二つのレベルを含んでいる。「モーションデータ」が振付と運動の二水準を内包しているからだ。まず、「楽曲」に対応する振付がいかにして市場に供給され続けるのかという問題があり、その振付がいかにして「モデル」の肉体において出力されるのかという問題がある。
MMDを開発したユーザーが初めての動画で「初音ミク」に踊らせたのは、当時放送されていたアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』のエンディングテーマに登場するダンスであった。気の遠くなることに、彼は平面のキャラクターが定点カメラに向かって踊る形式のアニメーションを、1コマずつ動きを「モデル」に写し取っていくことで「モーションデータ」を書きあげた。平面のダンス映像から振付を「初音ミク」に複写するこの作業は、のちにモーショントレースと呼ばれることになる。
一般に、CG映像にヒト型のモデルが登場する場合、モーションアクターと呼ばれる俳優の運動を複数のカメラやセンサ、パワードスーツ等で正確に補足してデータ化するモーションキャプチャの手法がとられる。言うまでもなくモーショントレースはモーションキャプチャと比較して量的にも質的にも困難だが、しかし、それでもゼロから振付を行う必要はないので振付師としての能力が問われることはなかった。
作中で登場人物が踊る形式のアニメはその後しばらく流行っていたが、こうした新しい振付の供給源は常にあるわけではない。しかし、「モデル」たちにとっては幸運なことに、当時のニコニコ動画では生身の人間もまた、平面の動画の中でコピーダンスを踊っていた。
MMDの黎明期から人気を博していたのは、素人が試みに何かを「やってみた」というジャンルで、その中に小さいながら存在したのが「踊ってみた」というカテゴリである。初めは素人の即興芸のようなものが多かったが、MMD公開とほとんど同じ時期、やはり『涼宮ハルヒの憂鬱』のダンスをコピーして踊り、アニメと同様の定点カメラで撮影してアップロードするユーザーが現れた。
この頃を境に「踊ってみた」のフォーマットはコピーダンス・定点カメラ・ワンカットという形式に画一化されていくのだが、次第にダンス経験のあるユーザーがこのジャンルに合流し、無数にあるVOCALOID「楽曲」に振付をつけて踊りはじめるようになる。この振付が、ミームとして拡散するわけである。あるユーザーが振付して踊った動画を見て、別のユーザーがそれをコピーして踊り……という循環によって、ひとつの楽曲・振付に対する運動(≠振付)もまた無数に発生した。
すでにお気づきの通り、こうして拡散した振付をコピーしていたのは生身のユーザーだけではない。「踊ってみた」の定点動画は次々とトレースされ、生身のユーザーの身体運用が「モデル」へと複写され、動画が作られた。動画の副産物として「モーションデータ」は必ず発生するため、多くの場合はこれをダウンロードするためのURLが動画に添えられ、これらもまたインターネットで流通することとなった。大半のユーザーは、自分で面倒な粘土細工をすることなく、手元のモデルに「モーションデータ」を流し込むだけで動画を作ることに興じていた。MMDの手軽さとは、本質的にはこの点を指していた。
魔法はしばしば思考も感性も介在することなく、半自動的に成立し、「魂」を吹き込まれたモデルたちがインターネット上にあふれかえっていた。こうして一部の「踊ってみた」投稿者たちの身体運用は、いつしかインターネット上に遍在していた。彼/彼女らの身体運用が、むき出しの身体運用そのものだけが、幽霊のように、いや、幽霊よりももっと無機質な物質性において、しかしたしかにオリジナルの身体の記憶をたたえた状態で、ネットの海をさまよい、n次的にあらゆる存在しない身体において顕現するようになっていた。特権化した身体の持ち主は、おそらくは本人の意図せぬうちに、場合によっては気がつかぬうちに、私の見た夢を大きな流れによって叶えていたわけだ。
魂、身体の記憶
身体運用の複製、流通、再生。デジタルとアナログの相互浸透。ミームとしての振付が、まるで伝染するようにして生身の人間と3Dモデルに注がれ再生されること。3Dモデルが生身の人間の身体運用を盗み取って踊り、「魂」を盗み取って実装すること。その網状の関係の中心にいる、特異点としての振付者。
あらゆる複製芸術と同様に、もはや身体運用も複製し流通することが可能なモノであるのだった。それは、そもそも振付がコピーされ踊りなおされるために存在するという事実とは本質的に異なる事態である。カラオケでの歌唱とCDの再生が違うのと同じことだ。
流通したモーションデータが、解像度の問題はあれど基本的には完全な複製である(CDのように)のに対し、振付は踊りなおされる過程で必ずダンサーの肉体による制約を受ける(カラオケのように)。かたちは身体運用を制約する。違うかたちが同じ振付を踊ったとして、出力された身体運用にはしばしばばらつきが生じ、視覚的な均質さを得ることは必ずしも容易ではない。大柄で筋骨隆々の男性と小柄で華奢な女性は同じようには歩かない。同じ振付を踊ってもすぐには同じニュアンスにならないし、同じニュアンスで踊っても同じ表現型にはならない。仮にモーションデータのように、ダンサーの関節の角度や筋肉の収縮率を厳格に指定できたとしても、この問題は解決しない。違うかたちが同じように踊るためには、年単位で踊る時間を共有する必要があるような気がする。逆に、かたちのほうを揃えてしまうのが、たとえばクラシックバレエにおけるダンサーの体型のセレクションである。
他方、留意しなければならないのは、身体運用の再生環境の特殊性である。
肉体によって踊りなおされることなくただ再生されるモーションデータは、モデルの肉体による制約を受けない。それは完全な複製の状態のまま再生される。しかしそもそも、かたちは身体運用をその発生段階において規定する。オリジナルの肉体を離れ複製された身体運用は、無関係な肉体においてただCDを再生するようには再生されない。結果として身体運用は、人類がいままでに経験したことのない奇妙な乖離を抱え込んでいる。
それはいわば、大柄で筋骨隆々の男性に小柄で華奢な女性の身体運用をインストールできる技術である。そこにあるのは、無関係な声と映像が結合されて提示されうるようになった時と同様の違和感であろう。たとえば「ジョジョの奇妙な冒険 MMD」でYouTubeを検索してみるといい。もともとは「初音ミク」や同様の10代女性のキャラクターの肉体において練り上げられたモーションデータを流し込まれ、しかめ面の屈強なスタンド使いたちが身をくねらせる文字通り奇妙な光景は、今もネット上でいくらでも見ることができる。
まあ、こんな例を挙げるまでもなく、モーションデータを流し込まれて動いているだけのモデルが自らの身体を運用しているとはもちろん言い難い。しかし、こうした奇妙なマッシュアップが時に「魂実装済み」として受け入れられるという事実のほうにこだわってみたいような気もする。粘土細工も流し込みも、出力され動画化されてみれば「魂」を伴うように見える。言ってみれば、こうして踊りながら魂を実装するモデルたちは、人間そっくりに振舞うが意識は持たない思考実験上の存在「哲学的ゾンビ」の亜型なのである。
いったい、「魂」とはなんであるか。それを見てとるのは我々の側である。それが生身の身体のモーションキャプチャであろうと、生身のダンスの複写であろうと、手打ちされたオリジナルのモーションデータであろうと、複製されたモーションデータであろうと、動画の形になってしまえば「魂」の存在可否にはあまり関係がない。それが自らの身体をほんとうに運用しているか否かと、その身体が「魂」を宿しているか否かということの間にも、おそらくはほとんど関係がない。モーションデータを流し込まれたことと生命の息吹を吹き込まれることとがほとんど同義であるとしたら、「魂」とはすなわち、身体のかたちとその運用についての記憶を指すことになる。
ヒトのかたちの魂
あれから10年もたった今、どうしてこんな話題を蒸し返す気になったのかといえば、いつのまにか時代が進んで、本稿で見てきたような状況が一歩進んでいるのに気がついたからである。
先日、池袋の映画館に映画を見に行ったときのことだった。
本編上映前の予告編で見慣れないアニメが流れていた。「夜子・バーバンク」と名乗る3DCGの女性キャラクターが、情報番組のような体裁で来月公開の新作映画を紹介をしている。こんなところにまでアニメが使われるようになったのか、という小さな驚きと、なぜわざわざこのような体裁で予告編を上映するのか、という違和感を抱きながら眺めていたが、どうも様子がおかしい。まず、映画館で流れるアニメとしてはキャラクターの動きが妙にぎこちない。口上もテレビで耳にするナレーターのそれとは程遠く、それらを真似た素人のような独特のたどたどしさがある。そこまで考えて、ああ、これは噂に聞くバーチャルYouTuberなのだと見当がついた。
2011年、YouTubeが広告プログラムを解放し、一般ユーザーが動画投稿を通じて収益を上げられるようになると、これを生業にしようとする人々が現れた。YouTuberと呼ばれるこれらのユーザーは自らがメインパーソナリティとなって、まさしく「やってみた」的なこととか有益な情報だとかを動画にして配信しているわけであるが、このご時世、なにもそういうことを生身の身体でやらなくても構わないと考えたユーザーが、モーションキャプチャとCGのモデルを使ってYouTuberをやるようになった。こうしたユーザーは、2016年12月に投稿を始めたトップランナー「キズナアイ」がそう名乗っていたことから、今ではバーチャルYouTuber、略してVTuberと呼ばれている。
興味深いことに、夜子某は特有の拙さにおいて直観的にはVTuberっぽいと感じられたが、しかし、その場でVTuberであると確信することはどういうわけかできなかった。よく考えれば、あらかじめ知らなければ確信しえないのだ。当該のキャラクターがモーションキャプチャによって動き、同じ身体から発せられた声をあてられているのか、あるいはアニメとして作られたものに後から声優の声がつけられているのかは、作業工程を明かされなければ知りえない。夜子某の存在が脳裏で宙ぶらりんになったまま家に帰って調べてみると、はたして、夜子某はVTuberであった。とはいえ、企業の広告案件として制作された動画が、普段の投稿と同様にモーションキャプチャで作られている保証だって、実はどこにもないのだった。これも、一種の哲学的ゾンビ問題である。
ハリウッド映画に登場するCGとは異なり、VTuberのモーションキャプチャの精度はそれほど高くないが、それでも無意識の動きがキャラクタとしての存在感を醸し出しているとも言われるくらいにはモデルがユーザーの身体運用を反映する。しかしだからといって、画面のなかで動くVTuberが、実際に身体を運用しているのか、はたまた別の身体によるモーションの複製を流し込まれているのか、実は我々には知りえない。最近では「キズナアイ」もテレビの音楽番組に現れて歌ったり踊ったりしているが、あれだって「中の人」がわざわざ現実空間のスタジオで動いているのか、初めから仮想空間のなかだけで処理されているのか、本当はわからない。
さらにややこしいことには、そもそもが仮想空間の中に存在するVTuberにおいては、身体運用ではなく肉体のほうを複製することも比較的容易である。すでに「キズナアイ」の肉体は、ネット上の別のユーザーによって素人目にはほとんど見分けがつかないほど精巧に複製され、3Dモデルデータとして広く流通している。「キズナアイ」の振付付きのオリジナル楽曲「AIAIAI」も、その振付がモーションデータ化され流通している。試みにYouTubeで「キズナアイ MMD」と検索してみれば、「キズナアイ」が「AIAIAI」を踊っている動画が無数にヒットする。もちろん、その大半はオリジナルの「キズナアイ」が投稿した動画ではない。こうした海賊版(というわけでは別にないのだが)と、音楽番組で流れる映像との違いを、我々は容易には指摘できない。というか、同じモデルが同じ身体運用を再生しているのだから、事実上そこにはほとんど差異がない。さて、目の前で動いているモデルの、「中の人」とはいったい何なのか。それは存在するのか、しないのか。哲学的ゾンビ問題は、ここにきてもう一段煩雑になっている。
しかし、VTuberではなく3Dモデルの立場で考えてみたならば、話は意外にシンプルなのかもしれない。ああそうか、存在しない身体を持つ者たちは、10年の時を経て、ついにヒトのかたちをしたオリジナルの「魂」を手に入れたのだ。言ってみれば、ただそれだけのことである。
そして人形へ
本稿では身体とその運用をめぐる現況を論じることを目的とし、その端緒としてMMDからVTuberまでを扱った。VTuberの人数は日に日に増えているようだが、多くのユーザーにとってはいまだ見るものであってなるものではない。仮想空間におけるAR・VR技術もまだ民主化されているとは言い難い。これらの技術がキャズムを超えるまでにはもう少しかかりそうだし、素人が未来予想をしてみたところでさほど面白いとは思えない。ここはひとつ、さらに過去へと遡ってみようかと思う。
存在しない身体を現前せしめること、そこに生命の息吹を吹き込むこと。こうしてVTuberとMMDを結んだ線を、そのままずっと過去へと伸ばしていけば、いったいどこへ行きつくだろう。素直に考えれば、その線がアニメーションのキャラクター、例えばまさに「初音ミク」のようなキャラクターの立体フィギュアを通らないことはあり得ない。秋葉原とかで立派な箱に入って店頭に並んでいる、あれである。残念ながら筆者は、この分野についてなにひとつ語ることができない。それでは、その線をさらに過去へ向かって伸ばしてみたらどうだろうか。そう、言うまでもなく、立体フィギュアの背景には「人形」という気が遠くなるほど広大な領域が、長い歴史が存在する。
と、言ってはみたものの、この領域についても筆者はなんら知見を持つものではない。しかし偶然にもまったく別の分野への興味から、この領域を論じようとした人物の著作にたどり着いた。
2018年に61歳で亡くなったその哲学者は、科学哲学や科学認識論を専門とし、バシュラールからカンギレム、フーコー、ダゴニエの仕事を日本に紹介した第一人者であった。
どういうわけかこの男が、晩年になって取りつかれるように研究したのが「人形」であった。当該分野に関しては全くの素人であったはずの彼は、2011年にゴーレムについての著作を出版している。ただの土塊が生命を吹き込まれ、ヒトそっくりに動き回るその魔法への憧憬が、人形への興味の端緒となったのか、あるいは初めから人形研究の準備だったのかは定かでないが、とにかくその後、彼は人形についての膨大な資料の収集にとりかかった。
その後起こった東日本大震災を経て、いまこの時世に人形なんぞについて語ることがアクチュアルであるとは思えない、という葛藤に何度もその筆を止めながら、しかし、それを論じることをどうしても諦められず、2018年になってついに1冊の本をまとめあげた。『人形論』と題されたその書物が、結果として彼の遺作になったのは、偶然ではなくなにかの必然であるような気がする。これが、この時代に、死を目前にしたこの哲学者によって論じられたことには、なにか意味があるような気がする。
その哲学者の名前は、金森修という。
[1]ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」野村修訳、多木浩二『ベンヤミン『複製技術時代の芸術作品』精読』岩波現代文庫、2000年、147頁。
(第1回・了)
<お知らせ>2025.1.23
本連載の書籍化が決定しました!
つきましては、連載2回目以降の公開を停止させていただきます。
大幅加筆・改稿を施し、鋭意作業中です。書籍版でまたお目にかかりましょう!
この連載は月1回(第3金曜日)更新でお届けします。
次回2021年6月18日(金)掲載