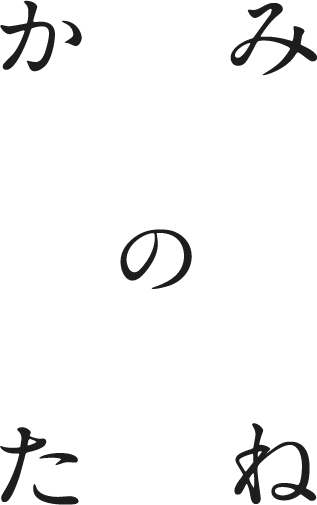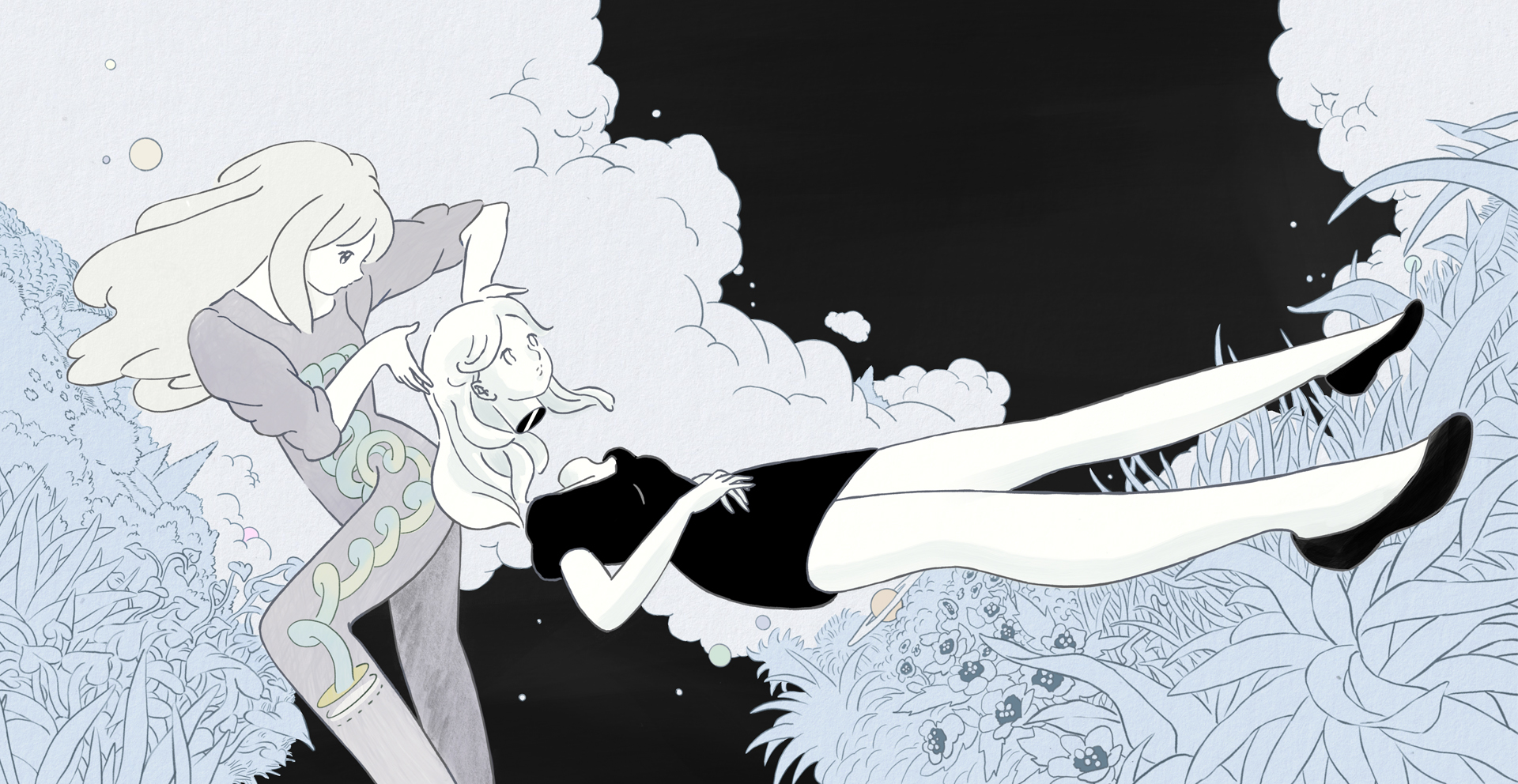3DCG、VTuber、アバター、ゴーレム、人形、ロボット、生命をもたないモノたちの身体運用は人類に何を問うか? 元ダンサーで医師でもある若き批評家・太田充胤の「モノたちと共に考える新しい身体論」、連載第3回は「新しい体」の身体感覚をフィクションの中で思考実験した作家、テッド・チャンの小説を中心にひもといていきます。
─
記号たちが服を着て歩き回り喋りまくり別の記号たちとの性交にいそしんでいるようなこのご時世では、人物描写など眼でさらりと撫でて飛ばし読みされるだけだ。記号は記号にしか興味を持っていない。[1]
──松浦寿輝『月岡草飛の謎』
浅草にストリップを見に行ったことがある。感心したのは、人間は持って生まれた体で踊るしかないのだという限界と制約が、衣装を脱ぐことでより明瞭に示されていたことだった。体のかたちが変われば、美しく見える踊り方も異なる。それぞれに与えられたかたちを引き受け、その限界を踊りきること。その矜持がもっとも問われるような様式であると思われた。もちろん、そういう矜持は、衣装を着て踊るダンサーにおいても重要な意味をもつ。我々は衣装によって運用する体のかたちをある程度デザインできるが、その支配領域は身体のごく表層の部分にとどまるからである。
しかし、こういう悩みを抱くのは、もしかすると現実空間に生まれてしまった魂だけなのかもしれない。仮想空間で生まれ育った魂は、いとも簡単にかたちを乗り換えるからである。
仮想空間に生まれる
それらの魂は、とある企業の商品のプロトタイプとして仮想空間に発生した。
人間の子供と同じように、それらは名前を与えられた。飼育員との会話によって言葉を覚えた。与えられる餌によって嗜好性を育んだ。日ごとに賢くなった。そうして愛玩されるのに十分な知性を獲得したところで、それらのプロトタイプをベースにした大量の複製が商品として売り出された。要するに、彼等は人工知性の技術を使った愛玩人形、デジタルペットなのであった。「ディジエント」と呼ばれるその商品シリーズは大ヒットし、全世界で10万人ものユーザーがその育成に熱中した。
しかし、残念ながら知性は時間とともに発達を続ける。人形たちはいつまでも幼く可愛いままではいられない。ほどなくして「ディジエント」に芽生えた自我を、多くのユーザーが持てあますようになる。しつけのためにセーブポイントまで何度も巻き戻される個体や、スリープされたまま二度と起動されない個体が増えていく。
それだけではない。デジタル技術によって作られた仮想環境は、知性そのものの寿命よりもずっと速く、めまぐるしく変化する。やがて「ディジエント」を起動できる仮想環境のサービス自体も縮小をはじめ、人形たちは知性としてのライフサイクルの途上で、商品としてのライフサイクルの終わりを迎える──。
以上はテッド・チャンによる中編「ソフトウェアオブジェクトのライフサイクル」(2010年)のあらすじである[2]。ごくわずかな短編しか書いていないことで知られる著者の作品の中では、比較的長い部類に属する。
同作は人間の都合によって生み出された人工知性が、愛され、増殖し、打ち捨てられるまでをつぶさに描く。ソフトウェアといえど、それが「知性」である以上、そのライフサイクルには我々の生と同様に無数のディテールが発生する。その生き生きとした魂の活動が、人間の都合によって変更されたり、止められたりする悲劇。「知性」であることと「商品」であることの摩擦、「商品」があまりにも「知性」的であるがゆえの悲劇……。その切なさはたしかに胸を打ち、来るべきテクノロジーとその倫理について思いをはせずにはいられない。
しかし、本稿の関心はその悲哀にはない。本作は技術とその倫理を描いた作品だが、それと同時にまぎれもなく一種の身体論でもあるからだ。
新しいかたちで踊る
知性は知性だけでは成り立たない。仮想空間とはいえ空間上にオブジェクトとして存在する以上、それらはかたちを必要とする。仮想空間において人間がそうするのと同じように、それらもまた3DCGのアバターを与えられ、身にまとっていた。
アバターには様々なかたちがある。我々のような二本腕・二本足のロボット型から、四足歩行の動物を模したもの、はては二本の触手に三本足のエイリアンまで……。これらの多様なかたちを与えられた魂は、今度は運動を習得する必要に迫られる。仮想空間内を疑似的に設定された物理法則にしたがって移動したり、転げまわって遊んだりするうちに、そのかたちを身体として運用する術を身につけていくわけだ。
その運動と成長のプロセス自体は、我々人間やあらゆる生命が経験するのとほとんど同じだろう。他方、決定的に違うのは、彼等が別のかたちのアバターにも簡単に乗り換えることができるらしい点である。それはたとえば、二本腕・二本足のアバターで育った魂が、あらたに四本腕のアバターに入るというようなことである。その乗り換えによってもたらされる変化は、単にアバターの見た目が変わるという表面的なものにはとどまらないだろう。
彼等はその新しい体を使って、踊ることさえできるという。人型のアバターを与えられた「ディジエント」の一人であるジャックスは、四本腕のアバター専用のダンスコミュニティ「テトラブレイク」に夢中になっていると書かれている。特定のかたちの体を使って人工知性がいかに踊るかを競い合うダンスシーン。それはいったい、どのような場だろうか。
実際に同作をお読みになればすぐにわかることだが、四本腕のダンスの話の本筋とはそれほど関係がない。というか、実はその詳細についての立ち入った描写もほとんどない。世界設計に元づく生々しいディテールの執拗な書き込みは、チャンの作品を特徴づける要素のひとつだ。四本腕のダンスは、こうした無数のディテールのうちのひとつに過ぎない。
にもかかわらず、四本腕のダンスシーンというイメージは、私の心をとらえて離さない。
想像してみてほしい。たとえば我々が馬のような四本足の体を手に入れたとして、新しい体ではおそらく歩くことすらままならない。なんとか歩くことに成功したとして、それが流暢なギャロップにまで至るのはずっと後のことだろう。ギャロップする馬の脚がいったいどのように運動しているか、二本腕・二本足の魂では容易に理解できない。ましてや踊ることなんてできるだろうか。
いや、なにも馬で考えなくてもわかることだ。体のかたちが変われば、それまでと同じように踊ることは難しい。どれだけ優れたダンサーであっても、事故で体の一部を欠損したならば昨日までと同じようには踊れない。他人の体を与えられたならば、やはり自分の体と同じようには踊れないだろう。
とはいえギャロップとは違って、ダンスならばいくらか希望もある。ギャロップが極めて合目的的な身体運用を目指すのとは異なり、ダンスはそれ自体は無目的的な運動さえ、しばしば事後的に目的化してしまう。私が二本腕・二本足で踊るように四本足の体で踊ってみたとき、たとえその表現型が二本腕・二本足のダンスとは似ても似つかぬものになったとしても、それが馬のダンスを凌駕しないとは限らない。たしかに私の魂は四本足のダンスを知らないが、そもそも私の知るかぎり、馬もまた四本足のダンスを知らない。足を失ったダンサーはしばしば、時間をかけて新しい体で見事に踊りなおす。
「テトラブレイク」の黎明期において、初めから四本腕のアバターで育った魂は、かたちを乗り換えて間もない他の魂よりも流暢に踊れるかもしれない。しかし長期的には、それらの新参者が四本腕ネイティブよりも劣るとは限らない。むしろ別の身体の記憶を持つ新参者によって、四本腕の体は新しく発見されなおすように思われる。
二本足・二本腕の我々は、四本腕の体をどう踊ることができるだろう。素直に考えれば、それは腕、あるいは手が果たす目的遂行性の運動が二倍になることを意味する。手振りを中心とした見せ方をするダンスなら、同時に表現できる内容が二倍になる。
しかし、四本腕の使い方はそれだけにとどまらない。「テトラブレイク」という名前からまず想像するのは、四本腕を駆使したブレイクダンスではないだろうか。四本の腕が発揮する接地機能・支持機能は、二本足のそれに匹敵するだろう。「テトラブレイク」には四本の腕で倒立したまま、腰から下を腕のように振るって踊る流派や、二本腕の我々には想像もつかないようなアクロバットを繰り出す流派が現れるに違いない。こうして四本腕のダンスを二本足の我々が想像する作業は、まるで別種の生物の思考を憑依させるかのような異次元の想像力を要する。
かたちは魂を規定する。三次元空間で特定のかたちを鋳型として発達した魂が、そのかたちを乗り換えたとき何が起こるか。二本腕の魂が四本腕のかたちに乗り換えた時、残りの二本の腕は魂のどの部分によって動かすことができるか。あるいは四本腕の魂が二本腕のかたちに乗り換えたとき、魂の余った部分は何をするのか。これが、我々がチャンの思考実験から当然想起すべき問いである。そして、この問いに十分に答えるための経験を、人類はまだ有していない。
仮想空間における身体とは、本来そういうポテンシャルをもっている話題である。しかし、そのような想像力は、SF史上の偉大な作品たちにおいてさえ、十分に発揮されてこなかった。なぜか。これまで仮想空間における身体は一種の記号にすぎず、記号的な全能性を帯びたものとして描かれてきたからである。おそらくそういう記号的身体では、踊るということ自体が我々の知るような意味では実行されえない。
かたちは身体運用を制約する。そして逆説的に、その制約こそが「踊る」という営みを可能にする。魂がかたちを乗り換えるという描写の意味は、この前提においてはじめて浮かび上がる。
データとしての人類
SFはこれまで、仮想空間で活動する人間を繰り返し描いてきた。
サイバーパンクの祖、ウィリアム・ギブスンは、『ニューロマンサー』(1984年)で電脳空間(サイバースペース)への「没入(ジャックイン)」を描いてみせた。「サイバースペース(Cyberspace)」という語は、この時初めて使われたとされる。主人公のケイスは頭に脳波計の電極を装着し、「マトリックス」と呼ばれる電脳空間に入ったり、「擬験(シムステイム)」と呼ばれる技術で別の人間の身体感覚を経験したりする。
今読むと非常に面白いのは、没入状態に入るケイスは目の前に「操作卓(デッキ)」と呼ばれるコンソールを置き、マトリックスにいながら現実空間でデッキを操作したりもしていることである。脳波によって電脳空間で必要な運動の大半は実現されるのだろうが、それに加えて現実の肉体による操作も要するということだ。しかしながら、こうして現実の肉体を動かす必要があるにもかかわらず、ケイスは没入することで肉体の軛から解き放たれると感じているらしい。
実は本作の冒頭、ケイスは過去に雇い主を裏切った報復により神経を焼かれ、没入ができない体にされている。電脳空間を失った彼のみじめさは、たとえばこんな風に描かれている。
電脳空間(サイバースペース)で、肉体を離れた歓喜のために生きていたケイスにとって、これは楽園放逐だった。それまで腕っこきカウボーイとして出入りしていたバーでは、エリートは、ゆったりと肉体を見下す風があった。体など人肉なのだ。ケイスは、おのれの肉体という牢獄に落ちたのだ。[3]
ケイスが電脳空間に身を置いているとき、そこに置かれているのが「肉体」ではないのだとしたらいったいなんなのかという点は一考に値する。いや、「身を置いている」などと不用意に書いたが、実はそのような三次元的な比喩自体が的を射ていないのではないか。なにしろその「空間」で行われているのは、実際にはデータの授受や演算であり、身体運用ではない。ギブスン式の電脳空間に「在る」ことは、必ずしも3Dオブジェクトとして空間を占拠することと同義ではない。
もうすこし新しい事例を見てみよう。テッド・チャンと並んで当代最高峰とされるSF作家、グレッグ・イーガンもまた、仮想空間を生きる人類の姿を幾度となく描いてきた。
現実空間に肉体を残しながら電脳空間にも存在する『ニューロマンサー』式の没入とは異なり、イーガン式の没入は一方通行である。どういうことかというと、生身の人間をスキャンしてデータ化し、コンピュータの中で走らせるのである。『順列都市』(1994年)や『ディアスポラ』(1997年)のような長編で描かれていたのは、巨大な仮想環境のなかに人類がまるごと移住するという壮大なアイデアだった。彼等の人格は肉体なしで思考し、半永久的に──こういっていいかどうかは議論もあろうが──生きつづける。
ギブスン式と同様、イーガン式の仮想空間においても、起こっていることはデータの授受や演算であり、それに尽きるはずである。ところが、イーガン式仮想空間において、人類はつねに視覚的に描かれる。イーガンは登場人物がどのような見た目をしているか、どのようなかたちをしているかの人物描写を欠かさない。
いちばん近くにいた市民のアイコン──高さ約二デルタの、ステンドグラスの彫刻に似た、まばゆい多色の人影──が孤児のほうをふりむいた。孤児の入力ナヴィゲーターにもともと組み込まれている構造が、視角をそのアイコンとまっすぐ向き合うよう回転させる。出力ナヴィゲーターはその動きに従うよう強制され、その時点で意図せずして相手の市民の幼稚なパロディになっていた孤児自身のアイコンを、視角にあわせてふりむかせた。市民が青と金色に光る。その半透明な顔が笑みを浮かべ、そしてこういった。「こんにちは、孤児」[4]
ここで登場する「孤児」なる人物、実は仮想空間の中に移住した人類ではなく、仮想空間の中で偶然生まれた人工知性である(ここでは彼のことを「人間」と呼んでもいいかもしれないが、話が長くなりそうなので割愛する)。引用したのは冒頭、まだ自分が何者かも知らず、見た目さえ定まらない状態の孤児が、他の人間と初めてコンタクトするシーンだ。
注目すべきは、彼等の外見が「体」ではなく「アイコン」と呼ばれる点である。仮想空間の人類は、アイコンを操作することによってコミュニケーションをとっている。ここではまだ孤児自身のアイコンが定まっていないことが示唆されているが、このあとも孤児は新たに出会う人たちと交流しながら、自らのアイコンを流動的に変え続ける。アイコンは自らの存在とその状態を示す記号として、他の存在に対して視覚的に提示される。
こうしてみると、イーガン式の仮想空間は、ギブスン式の電脳空間とは明らかに別物である。いや、そもそも「電脳空間」「仮想空間」という二つの概念自体、別のものとして明確に使い分けねばならないことがよくわかる。「電脳空間」とは一種の比喩だが、「仮想空間」は比喩ではなく、そこではデータが常に三次元的に視覚化されている。孤児と市民が視覚的なアイコンの提示を通じてのみ交流することからもわかるように、ひとたび視覚化されたデータたちのコミュニケーションにおいて、視覚以下の水準の情報は存在しないに等しい。言い方を変えれば、彼等は視覚化されたかたちに依存して存在している。これは『ニューロマンサー』のケイスが没入によって肉体から解放されるのとは、実はまったく反対なのである。
記号としての体
とはいえ、イーガン的仮想空間における人間が、「肉体」を持っているとみなしてよいどうかは微妙なところだ。アイコンという呼称が示すとおり、彼等が身にまとっているのは一種の記号である。アイコンは記号的な万能性を持ち、自由自在にかたちを変えて提示される。かような記号的身体を運用することの意味は、少なくとも我々が肉体を運用することの意味とは違う。
実際、彼等が現実空間で物理的な体を得た時の戸惑いは大きい。後に「ヤチマ」という名前を手に入れた孤児たちが、いまだ現実空間の地球に住んでいる「肉体人」とコンタクトをとるため、地球に放置された人型ロボットの抜殻に入る描写がある。
イノシロウは自分の顔面作動装置を試験的に収縮させ、落ち葉やほこりを削ぎ落した。ヤチマは自分の表情をいじりまわした。インターフェース・ソフトウェアは、ヤチマが試そうとしている変形は不可能だというタグを送り返してくるばかりだった。
「立ちあがりたければ、ある程度のゴミはおれがはらいのけてやるぞ」イノシロウはなめらかな動きで立ちあがった。ヤチマは自分の視線に上を向くよう命じ、インターフェースはヤチマのロボット・ボディにそのあとを追わせた。[5]
ヤチマは関連するすべての物理法則を心得ていたから、自分のアイコンに適切な動作を命じることで、グレイズナーの腕を思いのままに動かすことができた……だが、二足動物が巧妙にバランスをとるさまたげとなるあらゆる動作をインターフェースが禁じていても、ふたりの選択した妥協案では信じがたいほどぶざまにしか動けないのは、あまりにも明白だった。(中略)《コニシ》の市民は自分のアイコンの手に微妙な動きをさせる目的で、先祖の神経結線を残していた──それはボディランゲージ用に言語中枢にリンクされている──が、物理的な物体をあつかうための高度に発達したシステムはすべて、不必要なものとして捨て去られていた。[6]
彼等はロボット・ボディを使いこなすための知識を、あらかじめインストールしたうえで地球に来ている。しかし、実際に新しい体を使う段になると、その運用はどこかぎこちない。物理空間で動かして機能させるロボット・ボディと、単なる記号として提示されるアイコンとの差は歴然としいている。ロボットの操作に慣れるまでの戸惑いは、かたちが変わったことではなく、かたちが制約として効力を発揮するようになったことに由来する。肉体の制約を受けずに発達した魂には、肉体を扱う部分がないのである。
表示された視覚的なかたちに依存しないデータとしての側面と、三次元空間に「在る」視覚的オブジェクトとしての側面。イーガン的仮想空間における人類は、これら二つの側面をあわせ持っている。
ギブソンやイーガンが示したような、知性がかたちある肉体に拘束されない言説空間の表象には、ある種の思想が映し出されているように思われる。純粋に知性だけの存在。思考だけの存在。アイコン=記号だけを与えられて身にまとう、思考する点P。言うまでもなく、それらは創作の中にのみ成立する想像力であったが、我々にとって没入型の仮想空間が身近になるつい最近までのあいだ、ずっと支配的であり続けた。
90年代に一世を風靡した本邦のサイバーパンク漫画、士郎正宗の『攻殻機動隊』では、電脳空間や仮想空間が視覚的に描かれていた。主人公の捜査官たちは、体内に埋め込まれたコンピュータ経由で(「電脳」)、あるいは電極を首の後ろに差し込むことによって(「有線」)、電脳空間に没入する。現実空間の肉体はだらりとして動かなくなり、コマが切り替わると3次元立体や幾何学模様、ネットワークの模式図のようなものがちりばめられた「いかにも」な電脳空間が登場する。ところがこの電脳空間での攻防は、ページをめくっているうちに突然「視覚変換」される。幾何学模様は、のっぺりとした背景に服を着ていないキャラクターの体だけが描かれている「仮想空間」へと書き換えられるのだ。[7]
のちに同作がアニメ化された時には、電脳空間は完全に三次元的な仮想空間となっていた。没入するとカットが変わって「いかにも」な電脳空間が展開されるところまでは一緒だが、没入したキャラクターがその中を海のように泳いでいたりする。
視覚芸術では小説とは異なり、電脳空間の中に「在る」ことが視覚的に明示されなければならない。仮想空間に身を置く知性は、具体的なかたちをもって描かれることを要求する。他方、仮想空間に現れた体には、現実空間の肉体も物理法則も、やはり関係がない。その体は現実空間の物理法則を無視して運動し、人物の感情を描写する記号として用いられている。
『攻殻機動隊』からの影響を隠さないラナ&リリー・ウォシャウスキー監督の映画『マトリックス』(1999年)は、もう一歩進んで「我々が普段過ごしている世界こそが仮想空間だった」という設定で当時世間の度肝を抜いた。現実空間の人類は、実は高度に発達した機械に飼われていて、養育ポッドの中で丸くなってコードをつながれ、生まれてから死ぬまで仮想空間に没入したまま過ごす。主人公一派は、真実に気がついた「目覚めた」人として文字通り仮想空間から離脱し、現実空間と仮想空間を行き来しながらレジスタンスとして機械と戦う。
これまた興味深いことに、目覚めた者たちはそこが仮想空間であると気がつくことを通じて、超人的な身体能力や格闘技術を手に入れ、ついには生身で空を飛べるようにさえなる。仮想空間とはいえ、そこを現実空間だと信じている人間たちの体は物理法則に支配されている。しかし本来、物理的な肉体と異なり、記号的身体の運用に課せられた制約は非常に小さい。物理法則自体が仮想的に作られたものだと気がつきさえすれば、それを無視していかなる身体表現をすることも可能になるというわけだ。
ゴーレムのかたちとはたらき
テッド・チャンの仮想空間、あるいはより絞っていえば「テトラブレイク」というアイデアは、ここまででざっと見てきた先行事例とは明らかになにかが違う。四本腕というかたちが、あらかじめ指定されていること。運動の習得が、現実空間と同じく学習のプロセスを要求すること。ダンスという無目的的な運動、記号に還元しきれない身体提示が競われること。これらの状況設定によって、仮想空間は魂とかたちが結びつくことのできる場となっている。ダンスシーンとは、魂とかたちの結びつきの様式を問うための場である。しばしば起動すらされぬままデータとして休眠し続けることさえある仮想空間内のオブジェクトは、このような場において初めて、ある種の物質としてそこに「在る」ことを許されるのではないか。
チャンが体のかたちについて意識的であることは、より初期の作品「七十二文字」(2000年)に示されている[8]。こちらは仮想空間ではなく現実空間の話だが、我々とは異なる世界線の話でもある。舞台は錬金術が高度に発展し、それが今まさに人工生命を作り上げようとしている世界。我々人類が機械によって成しとげた産業革命は、同作の世界では量産型の工業用ゴーレム(自動人形)によって成し遂げられている。端的に言えば錬金術パンクである。
同作において、ゴーレムを動かす原理は「名辞」と呼ばれている。ゴーレム伝説には人形に命を吹き込むための儀式としていくつかの定番があるが、そのひとつに最後の仕上げとし護符を貼る方法がある。ユダヤ語で真理を意味する“emeth”の文字が刻まれた護符を貼ると、ゴーレムが起動する。一方、“emeth”から最初の“e”(ヘブライ語ではアレフ)を取り除いた“meth”は、ユダヤ語で死を意味する。最初のアレフを消去すると、ゴーレムは電源を切った家電のように休止し、再びアレフを刻み込むとまた動き出す。土くれに戻すためにはもう少し長い手続きが必要になるが、一度物質として自存したゴーレムは、こうして文字によってコントロールされる。「名辞」はこの文字入力による駆動原理の付与を、錬金術の発展によって七十二文字の配列まで拡張したものであると推測される。
主人公のロバート・ストラットンは、極めて優秀なゴーレムの駆動原理の制作者だ。ストラットンは幼少期からゴーレムを動かす仕組みに興味を持ち、粘土細工の小さなゴーレムで実験を繰り返した。人間のかたちをしたゴーレムが転ばずにまっすぐ歩ける「名辞」とはどのようなものか。その「名辞」を別のかたちに、たとえば馬のような四足歩行のゴーレムに適用したらどうなるか。理想的な運動をみせたかたちの、片方の足だけを短くしてみるとどうなるか。同じ文字列によってうまく駆動するかたちとまったく機能しないかたちとがあること、特定のかたちを動かすためにはそれに見合う文字列を編みださねばならないことを、ストラットンは幼いころから経験的に知っていた。
文字の組み合わせ次第で、同じかたちのゴーレムが様々な機能を獲得する。したがって、錬金術開発においては、目的とする機能のためにどのようなかたちとどのような「名辞」の組み合わせがよいか、また対象となる特定の形をどのような「名辞」なら動かすことができるかという問いが焦点になる。やがて大人になり、本格的に錬金術学を修めたストラットンは、不可能と考えられていたゴーレムの五本指を動かす「名辞」を開発する。それまでゴーレムは、ミトンのような指のない手しか与えられておらず、その手でできる大雑把な作業だけを担っていた。もしゴーレムが人間のように五本指で作業するようになれば、いずれは繊細な作業も担うようになり、職人たちの立場を脅かす存在になるかもしれない。そんな恐怖にかられた労働者団体から、ストラットンは命を狙われることになる。
労働者のゴーレムに対する不安が、高度に発達した機械に職を奪われるのではないかという現代人の不安をパラフレーズしたものであることは言うまでもない。ただ、機械とゴーレムで大きく異なるのは、ゴーレムは機械と違って、動くための内部構造を持っているわけではない点かもしれない。機械の体は合目的的に動くことをあらかじめ宿命づけられ、そのための内部構造を内側に持っている。ゴーレムはそうではない。ゴーレムの体を動かすのは「名辞」であり、ひとつの同じかたちは適用可能な「名辞」の数だけ、身体運用の原理を獲得する。応用が利くという意味では、機械よりもずっと大きな脅威であるようにも感じられる。
とはいえ、「名辞」で駆動するゴーレムもまた、それほど融通が利くわけではない。与えられた文字列の通りにしか機能しないし、「名辞」とかたちとのミスマッチがあれば、それはうまくは機能しない。同じ文字列を複数のかたちに適応することは、常にうまくいくわけではない。新しいかたちが供給されたら、それを動かすことのできる「名辞」の開発を待つしかない。
しかし魂ならば、自ら学習する。新しいかたちを与えられた魂は、それをよく運用すべく自らのかたちを作り替える。同じ「名辞」を違うかたちに適用したらどうなるか、と問いから、同じ魂が違うかたちを運用したらどうなるか、という問いへ。魂を実装された人形は、今度は勝手にそのかたちを運用する能力を醸成する。「七十二文字」から八年後に書かれた「ソフトウェアオブジェクトのライフサイクル」で、チャンがやろうとしているのはそういうことである。
「ソフトウェアオブジェクトのライフサイクル」には、四本腕どころではない奇妙なかたちも登場する。たとえば、三本の足と二本の触手、一本の尾をもつエイリアンのアバター「ゼノテリアン」。どうやって歩くのかさえ想像がつかない。ユーザーの中には、好奇心からさらに奇天烈な身体構造や、物理条件の違う生育環境を希望する者もいた。それらの身体運用を二本足・二本腕の人間がデザインすることは簡単ではないが、アバターを与えられた魂がひとりでに学習するのならば問題はない。
新しいかたちを与えられた魂がどのような身体運用を身につけるのかを眺めるさまは、おそらく至上の娯楽であるに違いない。あわよくばそれらが踊っているところが見てみたいと考えるのは、極めて自然な欲望であるような気がする。
身体運用のボキャブラリー
身体運用は、たとえば言葉を扱うことによく似ている。
ひとつの言葉が発せられれば、それを読点で閉じるまで意味は終われない。同様に、突き出した拳はいずれ引かねばならないし、振り上げた腕はなんらかのやりかたで降ろさねばならない。頭の上にかかげた腕を、どの筋肉を使って、どこを通ってどんな速さで降ろすのか、あるいは降ろさずに次の動きにつなぐのか……無数の可能性のなかで、その身体が今ここで選びうる選択肢のことを、我々は身体運用のボキャブラリーと呼ぶ。
身体に刻み込まれ記憶されたボキャブラリーは、やがて適切な場面で「口をついて出る」ようにして表出する。ひとつの言葉が発せられれば、そこから引きずりだされるようにして次の言葉が続く。その制御しがたい運動の連続は、やがて話者の「言いたいこと」をはるかに超えて意味を紡ぎだす。結果として紡ぎだされた文章は、話者のうちにあらかじめ蓄積されていた断片の集積とは限らない。これまで考えたことさえなかった意味のまとまりが自らの運動の中に析出する驚きを、我々はしばしば、いや頻繁に経験する。
ひとつの言葉のあとに続く言葉が何であったか、何ではなかったか、それだけが問題になりつづける。その選択の軌跡が事後的に意味をなす。描かれた言葉の軌跡から感じ取れる語り手特有の息遣いを、我々は文体と呼ぶ。ランダムな言葉の羅列に文体は生じない。言葉が選ばれ、言葉同士が接続されて初めて、そこに文体が発生する。
この流れるような運動と創造を可能にするためには、ひとつの言葉のあとにいかなる言葉を接続しうるか、という言語感覚を内面化することが必要不可欠である。同様に、ひとつの姿勢と次の姿勢を接続し、運動と運動を接続し、その間に軌跡を描き続けること。それ自体が自己目的化した身体運用の様式を、我々はダンスと呼んでいる。
その営みは、端的に我々が肉の体を持ち、そのかたちが変化する幅が有限であることに由来する。運動と運動が常に接続されなければならないという制約に由来する。頭の上にかかげた腕が今度は胸の前で差し出されるとき、腕は可動域内のどこかに必ず何らかの軌跡を描く。ばらばらのボキャブラリーの無数の選択肢は肉体の制約によって可能性を絞られ、ようやく一筋の軌跡をなす。
フロアに1人のダンサーが踊り出る。
踊り始めるまではほかの体と同じように、音に乗ってただ揺れていただけのその体が、踊り始めたとたんに彼自身の身体を開示する。どのように動くのかを明かしていなかった体が、ほんの1、2小節ほどのあいだに、それ自身の方法を詳らかにする。
あっ、と息を飲む。巧拙の問題ではない。上手ければもちろんのこと、どれほど稚拙であれ一度は驚く。開示されるのはボキャブラリーでも技術でもなく、あくまでも彼自身の身体である。それがどのように運用されるのかという事実そのものが、彼自身の身体を、魂と肉体が結びつく様式を物語る。
いまだ踊りださずにそれを眺めているだけのダンサーは、高座の上でいまだ黙ったままの噺家のように、これから繰り出される彼自身の魂のかたちを秘匿している。体がフロアに露出した瞬間、ステージに立った体が踊り始める瞬間、開示された身体を目の当たりにするときの感情は、噺家の口から発せられる第一声を聴く感情の動きにどこか似ている。
ほとんど肥満体のダンサーの上半身が、見た目にたがわぬ重さで空を打つ納得、あるいは反対に、重力に反して床を浮遊する驚き。小さい体から目算を超えて伸びる腕。長身から伸びる手足が、持て余したように体にまとわりつくさま。身体機能の低下さえ疑うような壮年期の体が見せる、歴史の蓄積された滋味深い手振り。
身体の発露は群舞でもいいが、ソロならなおよいし、即興ならこの上ない。他の身体と混ざれば薄まる。ルールや振付は、踊る者の身体が十分に発露するのをしばしば阻害する。バレエのような歴史あるジャンルでは、あらかじめ定められた運用の規範が踊る者の体のかたちさえも規定する。選別された同じようなかたちの集団から繰り出される動きは、基本的に同一の様式に属し、巧拙はあれど鬼が出るか蛇がでるかという驚きは少ない。
とはいえ人間のかたちに大したバリエーションがない以上、どれほど多様なダンサーが踊ってみせようと、身体開示の驚きは徐々に減衰する。二本腕・二本足ならもう見飽きてしまった数寄者が、より強い驚きを求めた先に人間のかたち自体を問い直すことになったとしても、それはまったく不思議なことではない。
「ディジエント」のヘビーユーザーは、三本足と一本の尾で歩く「ゼノテリアン」にさえ満足せず、さらに奇抜なかたちを求め、我々とは違った物理環境で育つ魂を求めた。私にはその気持ちがとてもよくわかる。
みんなで同じ肉を得る
しかし、それだけではない。アバターの乗り換えには、扱うかたちが変わるということ以上に大きな意味がある。
そこに開かれているのは、同じかたちが無数の魂によって使いまわされる可能性、言いかえれば肉の体が一種の公共物になる可能性である。そのとき我々の魂は、音楽がダンサーにとっての環境であるのと同様、肉体そのものもまた一種の環境に他ならないというまぎれもない事実を思い出す。
言葉は他者に向けて発せられ、あらゆる段階において、他者という制約が言葉の編まれ方を変える。この場合の他者とは、「私」以外の人間だけでなく、「私」以外のすべてを指す。それらの他者をまとめて、環境と言い換えてみてもよい。
ダンスの場合、そのような他者とはたとえば音楽である。無音ならば自らの中で流れる音を頼りに踊ることもできよう。しかし環境に音楽があれば、音楽とどのような距離をとるかを選ぶことはできても、音楽からなんの影響も受けずに踊ることはそれなりに難しい。身体運用は身体の記憶を縦糸に、音楽を横糸にして編み上がる。結果として出力された運動が、あとから振り返ればその音楽抜きでは発生しえなかったであろうと思われることは少なくない。
音楽シーンの更新は、不特定多数の身体が同じ新しい他者に直面することを意味する。まったく新しい様式の音楽が供給されれば、それと体で対話するためのダンスシーンが生まれる。あまねく再現可能な新しい身体の使い方が発見されれば、ダンスシーンも大きく動く。流れの速いダンスシーンでは、踊るのをたった数日休んだだけで、他のダンサーがもう自分の知らないステップを踏んでいるという[9]。それはいうなれば、新しい環境を集団で開拓するための、身体運用のフロンティアである。開拓の歴史がある程度蓄積されたとき、一連のボキャブラリーはそれを発生せしめた音楽とともに、ひとつのジャンルとして名前を与えられることになる。
さて、音楽がそうであるのとほとんど同じ意味において、肉体はダンサーにとっての他者であると言ってよい。
体と魂が予想通りに同期して、同じかたちをなして動いている日常生活の大半の時間、我々はその事実を忘れて過ごしている。それは操作することの可能なオブジェクトでありながら、魂の運動と常に同じ軌跡を描いているとは限らない。描いた軌跡を見返すことさえできないまま、我々は描き続けねばならない。踊ることは、目をつぶって絵を描くことに等しく、目をつぶったまま描いた想像上のダンスはいかようにも美しくなる。実際に踊っている自分の体を目の当たりにして初めて、我々は自らの魂に課せられた肉の制約に気づく。
それでも我々は、いまのところ持って生まれた体で踊るしかない。そして、その体でいかに踊るかという問題は、たまたまそれを持って生まれた個体にのみ帰属し、複数個体のあいだで完全に共有されることは原理的にありえない。ここが音楽とは違う。我々は持って生まれた体で踊るしかないし、たとえ無数の体が同じフロアで群れていたとしても、踊っているときは一人ぼっちなのである。
この孤独といかに向き合うか、という問題の解として、ギブスン式の仮想空間、あるいは過去の偉大なSF作品群は、没入さえすれば肉の体を忘れられるという世界観を提示した。これに対してチャン式の仮想空間が提示するのは、みんなで受肉しなおすという別の解決策だということになる。まるでクラブに音楽が充満するようにして、新しい肉体が行き渡ること。同じリズムで無数の体が揺れるように、同じ肉の制約を無数の魂が味わうこと──。
今日の没入様式、今日の記号的身体
話は少し逸れるが、2018年に『レディ・プレイヤー1』という映画が公開されたのを覚えているだろうか。「ソフトウェアオブジェクトのライフサイクル」が発表されてから10年後、ちょうど我々にとってもVR技術が身近なものになりはじめた頃のことである。数多くのSF映画を手掛けてきた巨匠スティーブン・スピルバーグの監督作品なのだが、彼が描いた仮想空間は──というよりも、仮想空間に没入する人類の姿は、端的にいって滑稽だった。
映画の舞台は、近未来のVR型オンラインゲーム。もちろんゲームである以上、その中で活動する人間=キャラクターは、自由自在に飛んだり跳ねたり、それはもう超人的な身体能力を発揮する。一方で、そこに没入するプレイヤーは、攻殻機動隊のように電脳を搭載したサイボーグでも、初めから仮想空間で育った人工知性でもなく、生身の人間である。彼等が仮想空間の体で感じ、動く方法は、ヘッドマウント式のディスプレイ、グローブと衣服のかたちをした装着型のコントローラ、そして足元には全方向に動くトレッドミル。どうやらプレイヤーは、仮想空間内で人形を走らせているあいだ、現実空間を肉の体で走っているらしい。いわば肉の体をコントローラとして、仮想空間内の肉を動かしているわけだ。
現実の運動が仮想身体の運動にどのように翻訳されているにせよ、現実空間の体はそれ相応に汗をかかねばならないはずだ。仮想空間で超人的な身体運用を発揮するとき、プレイヤーの肉体はその負荷を少なからず受けて時に悲鳴を上げるだろう。そのくせ、スタープレイヤーとしてゲーム界を騒がせる同作の主人公は、現実空間では軽度肥満のギークとして描かれる。このあたり、制作陣は自分の体でVRゲームをプレイしたことがなかったのではないかと思わせる滑稽さがある。
奇しくも私は、同作を『マトリックス』シリーズを観たのと同じ映画館で鑑賞した。映画館を出て、ここははたして現実空間だったか、これは生身の体だったかと、『マトリックス』のときと同じ錯覚に襲われ、それを心地よく感じもしたのはたしかである。その一方で、人類の想像力は映画においてさえ、我々が肉の軛から逃れることを許さなくなったのかと隔世の感もあった。
もちろん上記の没入環境は、仮想空間のオブジェクトが肉のコントローラの動く通りにしか動けないことを意味しない。これらのデバイスは、我々が仮想空間における身体を二つのレベルで運用できることを意味している。我々の肉体そのものがコントローラとなる水準のほかに、現実空間での肉体の動きを翻訳して、別のやりかたで仮想身体に反映する水準がありうる。たとえばボタンを押すという指先の運動が、移動とか視点変更というかたちで、仮想身体に指先の動き以外の根本的な変化をもたらすこともあるわけだ。両手に握ったコントローラとはつまり、現実空間と仮想空間のあいだ、肉と肉のあいだに介在する翻訳装置にほかならない。
我々の魂は翻訳によって何を捨て、何を手に入れるのか。受肉することのやり直しとは、結局のところ取捨選択の問題であるようにも思われる。
たとえば今日利用可能な技術だけでも、五本の指の動きを適切に翻訳すれば、我々は仮想空間で指を失う代わりにイカのような八本足で踊ることができるのではないか。
私個人はイカの体を試してみたいとかなり強く感じる。流線型の体で泳いだり、八本足と二本腕を駆使して存分に踊ってみたいと思う。しかし現実問題として、イカのためのコントローラは広く普及してはいない。理由は技術的なものから商業的なものまでたくさんあるだろうが、もっとも本質的な点は、世の中のニーズが肉のかたちではなくオブジェクトの記号性にこそあるということなのではないか。
そういえば、第1回で少しだけ触れたVTuberを含むVR界隈には「バ美肉」というミームがある。バ美肉とは「バーチャル美少女受肉」の略で、「バ美肉おじさん」のように使われることからもわかるように、現実空間では美少女でない体を持つ者が、仮想空間において美少女のアバターを身にまとうことを意味する。
やはり美少女というくらいなので、それらのアバターはすべて、二本腕・二本足のかたちをしている。ユーザーは体のかたちを乗り換えていると言えなくはないが、体の見た目を乗り換えているところが大きいような気がする。もちろんかたちと見た目は不可分であるし、「おじさん」の身体運用と美少女の身体運用は同じではないから、魂のかたちをある程度変える必要もあろうが、最も大きな変化が生じているのは提示される記号の水準である。
批評誌『ユリイカ』で「バーチャルYouTuber」特集が組まれた時[10]、「身体」という言葉を使って件の対象を論じた論者はごくわずかしかいなかった。そのわずかな論者も、アバターのかたち、たとえばそれが二本腕か四本腕かなどという点には露ほどの興味も示してはおらず、論じられていたのはまさに、新しい肉が記号として提示されるやり方についてだった。
まあ、当たり前と言えば当たり前なのだが、そろそろ四本腕で踊るYouTuberみたいな人が登場してもいいのにな、と密かに思っている。私が知らないだけで、広大なインターネットのどこかにはもういるのかもしれないが。
不気味なもの、自存するオブジェクト
ギブスンにおいて、電脳空間が「空間」と呼ばれることは一種の比喩であった。思考する点Pにとって、あるいは送受信され演算されるデータにとって、それが存在するのが「空間」である必要は本来どこにもなかった。現実空間を離れ仮想空間に顕現することは、主体の明らかな二重化を意味していた。
翻って今日、仮想空間が「空間」であることは比喩でもなんでもない。そこは我々にとって、現実空間と地続きにある三次元空間そのものとなりつつある。主体は二重化しない。仮想された肉は現実の肉との連続性を明らかに保持し、我々は肉の体で仮想空間を歩く。逆に言えば、我々は仮想空間においてさえ、肉の軛から逃れてはいない。だからこそ、仮想空間にアバターを持つことが「受肉」と呼ばれる。
ただし、残念ながら仮想空間で育った魂と、現実空間で育った我々とでは、仮想空間において受肉することの意味が違う。仮想空間で育った魂は我々と違って、生まれ育った肉の軛を完全に断ち切ることによってのみ、新しい肉を得るからである。
チャン式の仮想空間は、生まれ持ったかたちで踊るしかない身体の孤独に対して、みんなで受肉しなおすという新しい解を提示した。注意しなければならないのは、チャンがその方法を我々人間ではなく、仮想空間で育った魂にのみ認めているという点である。実際のところ、「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」でテトラブレイクに興じているのは人間ではなく、「ディジエント」たちだ。先述の「ゼノテリアン」のくだりでも、「ディジエント」を育てる人間も同じアバターをまとわなければならないこと、しかし人間にとっては「ものをつかめる触手を使いこなすだけでもじゅうぶんにやっかいだ」ということが示唆されている。どうやらチャンは、人間が仮想空間で自由自在にかたちを乗り換えられるとは思っていないらしい。
その認識は、今日の我々の現状認識と一致する。おそらく当面のあいだ、状況は変わらないだろう。人類はまだ、二本の触手を使いこなすことも、四本腕の体で踊ることを許されてはいない。現実空間に肉の体を残したままの我々が、四本腕の接地機能を手にすることはできない。それが可能となるような没入様式を編み出すまでのあいだ、それは人形たちにのみ許された特権的な身体運用でありつづける。
人間が課せられた制約を、人形たちが軽々と超えていく。やがて人形たちの身体は、人間にとって共感可能な範疇からもはみ出していくだろう。
思い起こすのは、アニメ監督の宮﨑駿が激怒したという有名なエピソードである。
ある人物が、アニメーションにCG技術をとりいれる手法として、人型の3DCGモデルが機械学習によって運動を習得する動画を宮﨑に紹介した。CGモデルは関節や筋肉を持たず、痛覚もない。それゆえ二本腕・二本足のかたちをしながら、二本の足では歩かず、頭部を足のひとつのように使ってみたり、両腕で地面をこぐようにして前に進んだりと、我々が思いつきもしなかったような方法で移動する。その様子を見せながら「この動きが気持ち悪いんで、ゾンビゲームに使えるんじゃないかって」と提案したプレゼンターに、宮﨑は「生命に対する侮辱」と怒りをあらわにした。[11]
宮﨑の念頭にあったのは、体のこわばった障害を持つ友人の姿であったという。しかし言うまでもなく、我々はこわばった体の運動を、不気味とも気持ち悪いとも感じない。宮﨑の友人と頭を使って歩くCGモデルとのあいだには、なんらかの大きな断絶がある。
人間のかたちを規範としながらも、人間をなんら参照せずにゼロから編み出された身体運用の不気味さ。それはいうなれば、自存するものの不気味さではなかろうか。
ある種のモノたちは、自らを作り出した人間の手を離れて自存する。一度は確かに人間の傍らに置かれていた痕跡を身にまといながら、もはや人間とは無関係にそこに在るモノ。人間による解釈や理解を要求せず、人間によって対象化されることも道具として使役されることもなく、ただ存在感だけを放つモノたち。そういうモノたちだけが帯びる自存性がある。道端に置かれた中身のわからない不審物。人気のない山中で発見される半ば朽ち果てた日用品。どこにも通じていない宙に浮いた階段。廃業し封鎖された遊園地に残る遊具。森の奥で遭遇する野生化した馬。あるいは、押入れの奥の暗がりでなにか言いたげな人形。
『人形論』には古今東西の人形の写真が収められている。無数の人形たちは本の中で静かに佇んでいて、頁を開けばこちらをじっと見つめている。個人的には、同書を電車の中で開くのはすこし気が引ける。知らない人が見たらぎょっとするのではないかと思うような、ふと我に返った瞬間に気がつくような類の不気味さが、同書にはちりばめられている。
人形の持ち主は、成長とともに人形のことを忘れてしまう。金森はその手の話を繰り返し取り上げ、忘れられ打ち棄てられるところまでが人形の宿命なのだとまで書いている。古今の物語に登場する忘れられた人形たちは、人間の知らぬ間に動き出し、気が付くと成長している。人間の想像力は、ひとたびそのようにして人間との意味のつながりを失ったモノたちにさえ、魂を与えてきた。
すでに取り上げたように、金森は単なるモノに魂を吹き込むのは人間の願望や幻想なのだと書いた。しかしながら、捨てられて自存するモノたちが宿す魂が、まるで生きたパートナーであるかのように愛玩される人形に見出される魂と、同じものであるとは思えない。後者が意味のつながりによって与えられるのに対して、前者は意味の遮断を経て発生するからである。
デジタルペットもやはり、打ち棄てられたモノたちと同じようには自存しない。意味のやりとりを遮断して自存するモノたちのゾンビのような不気味さは、デジタルペットにはありえない。たしかにそれらのCGモデルは、まさに金森が指摘したとおり、作り手から切り離されて存在し、学習し、成長する。しかしながら、その変容は人間との意味の交流を失うことを意味しない。それらは作り手を離れるや、自らを迎え入れる持ち主との間に新たな関係を結ぶ。愛玩という目的を身にまとい、我々と交流するものであるかぎり、それらと我々は、絶え間ない意味のやりとりでつながり続ける。
もしも彼等が不気味なものとして人間の前に立ち現れるとしたら、それは彼等が人間を規範とした身体運用をやめたときであろう。
デジタルペットや人形たちが二本腕・二本足の体を人間の慣習にならって運用しているかぎり、やはりそれらは不気味でもなんでもない。四本腕の体であっても、我々にも理解できるような合目的的な身体運用なら不気味とは感じない。しかし、その運用が我々の理解を超えた瞬間から、それは「不気味なもの」になる。「ゾンビ」の例が不気味なのは、その体が人間を規範としているにもかかわらず、その身体運用がいかなる人間をも規範としていないからである。四本腕で踊る人工知性もまた、どこかで必ずその段階に到達する。それは人間のかたちに飽きた好事家の興味を買い、そうではない多くの人間に不気味さを感じさせる。いや、もしかしたら到達する前にスリープされてしまい、そのまま二度と起動されないかもしれないが。
ところで金森は、打ち棄てられた人形のほかにもうひとつ、人形が不気味なものとして立ち現れる瞬間に言及している。そう、自動人形だ。『ゴーレムの生命論』では、あのフロイトの有名な論文「不気味なもの」への直接的な言及がある。これまたかなりの字幅をとって紹介されるのは、フロイトが同論文の冒頭に取り上げたE・T・A・ホフマンの小説『砂男』、そしてその2年前に書かれた『自動人形』である。この自動人形の話題から出発してしばしのあいだ、金森はロボットをめぐる想像力の系譜を追っていく。本当は人間ではない自動人形が、「まるで人間のように」巧みに動くことの驚嘆と不気味さ。その先にある、「人間には似ているのだが、人間ではないものへの違和感や不快感」[12]。ここに、第2回では扱わなかった金森のもう一つの論点がある。
そろそろ次の話題に進もう。ロボット──人間のかたちを規範としてもよいし、しなくてもよい者たち。魂を実装してもよいし、しなくてもよい者たち。そういう宙ぶらりんの立場に置かれた者たちが仮に人間のかたちを与えられ、「人間ではないもの」として踊るとき、いったい人間はそこに何を見出すだろうか。
数年ほど前、私は一人のロボットに出会った。彼は人間のかたちをして、人間たちの前に立ち、人間が知らない身体運用で踊っていた。我々には知りえない彼自身のアルゴリズムが、途切れることなくその肢体を動かし続けていた。奇妙で不気味だが抗いがたい魅力もあるその身体運用を目の当たりにして、私はその場から動けなくなってしまった。それはどこか、自然の雄大さに神の存在を見出す経験に似ていた。
次回は彼の話から始めたい。彼の名前は、オルタ3という。
[1]松浦寿輝『月岡草飛の謎』文藝春秋、2020年
[2]テッド・チャン「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」、『息吹』大森望訳、早川書房、2018年
[3]ウィリアム・ギブスン『ニューロマンサー』黒丸尚訳、ハヤカワ文庫、1986年、17頁
[4]グレッグ・イーガン『ディアスポラ』山岸真訳、ハヤカワ文庫、2005年、32頁
[5]同書、90頁
[6]同書、91頁
[7]士郎正宗『攻殻機動隊』講談社、1991年、263–275頁
[8]テッド・チャン「七十二文字」嶋田洋一訳、『あなたの人生の物語』浅倉久志他訳、ハヤカワ文庫、2014年
[9]このあたりは、新興するストリートダンスシーンを捉えたドキュメンタリー映画『FootworKINGz』(ヘルトン・ブラジリオネア・シンキュイーラ監督、2009年)や『RIZE』(デヴィッド・ラシャペル監督、2006年)に詳しい。
[10]『ユリイカ』2018年7月号
[11]NHKで放映されたドキュメンタリー番組「終わらない人 宮﨑駿」(2016年11月13日放送)
[12]金森修『ゴーレムの生命論』平凡社新書、2010年、140頁
(第3回・了)
この連載は月1回(第3金曜日)更新でお届けします。
次回2021年8月20日(金)掲載