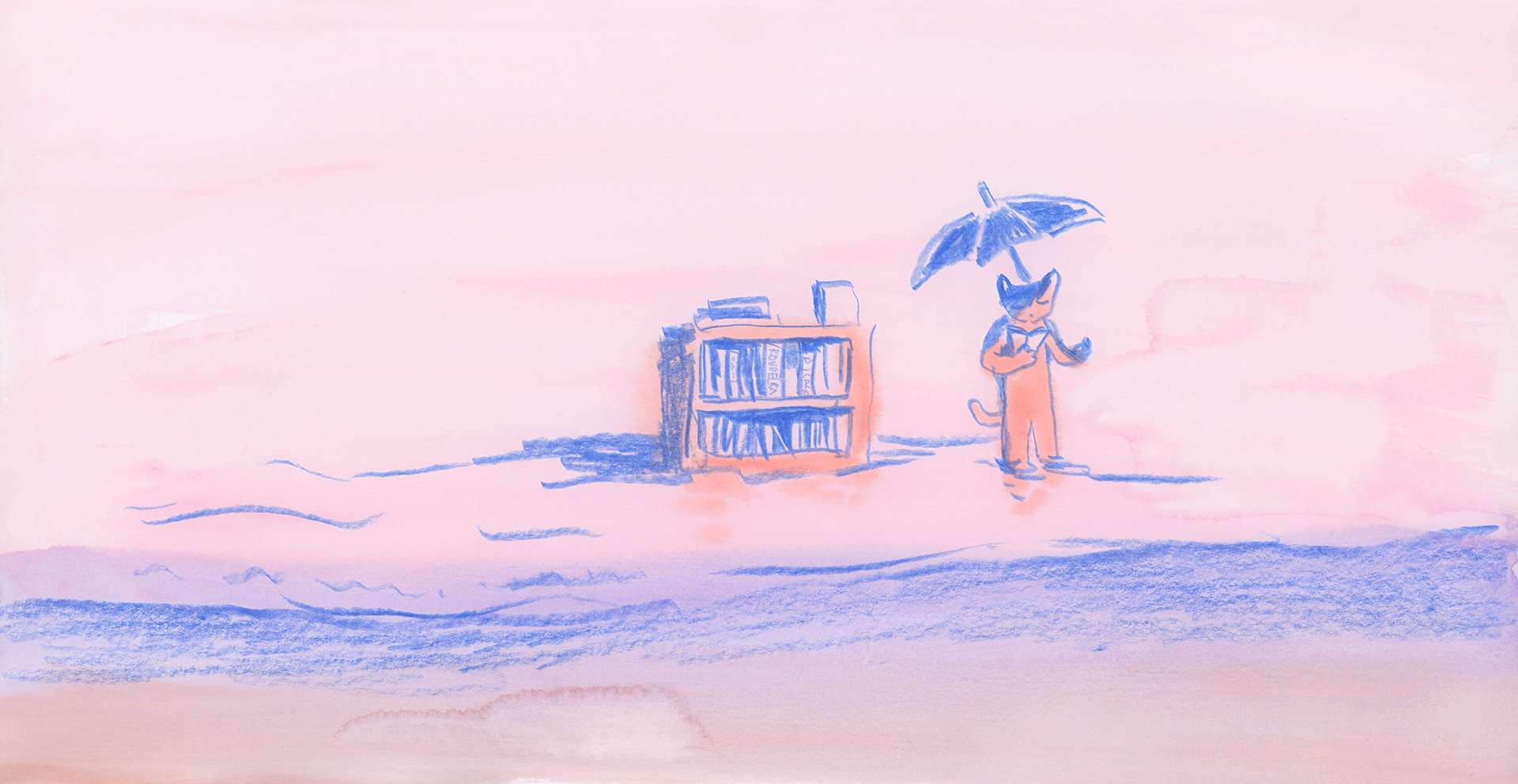2013年、東京・学芸大学の賑やかな商店街を通りすぎた先、住宅街にぽつんと、SUNNY BOY BOOKSは誕生しました。店主の高橋和也さんとフィルムアート社のおつきあいが始まったのはとても最近なのですが、ちょうど『ヒロインズ』を売りまくっていたり(250冊以上!)、企画展「想像からはじめる――Solidarity-連帯-연대――」が全国の書店を巻き込んだ大きなうねりとなって巡回されたり、すごいことを淡々と当たり前のようにやっていらっしゃる時期で、個人書店の底力というか、小さいゆえの機動力とか社会的な意義というか、改めて実感したのを覚えています。
以前のインタビューで「東京だからやっていける」とおっしゃっていた高橋さんですが、世の中の状況も変わり、決して楽観的ではないけれど、東京はもちろん地方でも本屋を始められる方がとても増えました。背景には、どこで買っても同じはずの本なのに、「大好きなお店を応援したいからここで買おう」と思う読者がすごく増えたことが大きいと感じます。SUNNYも特にコロナ禍初期に休業された際、心が折れそうなとき、お客さまからたくさんの激励を受け取って気持ちを保てたとのこと。だからこそ2021年2月に家族で沖縄に移住されることになっても、続ける意志が繋がれたのだと思います。
沖縄移住をすっぱり決断されたことといい、子供さんが生まれてからはより「生活」を大事にされる気持ちが強まったようにも感じます。ブレない軸を持ちつつも自然な流れに身を任せてきた高橋さんが、現実をどう受け入れ、これからどうなっていくんだろう、見守りたい方はたくさんいらっしゃると思います。高橋さんの考えややりたいことが少しずつ整理できるような連載になればいいなと思います。

少し前になりますが、先日の衆議院選挙のときにも投票に行くことを呼びかける投票ポスターの展開を行なっていた「表現と政治」チームによるオンラインのトークイベントに呼んでいただき千葉、鳥取、東京の独立系書店の店主さんたちとお話をしました(表現と政治 vol.3「本を届けること、読むことから考える表現と政治」)。新型コロナウイルスに台風、線状降水帯などによる自然災害といった10年、100年に一度レベルの災害や、真っ正面から受け止めることが難しいショッキングな事件が次々と起こり、そんななかでも立ち止まることなく生きていかねばならない社会に迷い、憤り、揺れているいま、どんな本を読み、どんな想いで本を届けているのかについて。それぞれの店主さんの視点、取組みにうなずきっぱなしの時間でした。
最後の質問コーナーで、現在は店舗を持たず出店やオンラインショップで本を届けている方から「アナーキズムやLGBTQの本(話の流れで紹介していたので)を揃えても地方では動かないし、逆に嫌厭されてしまうのではというおそれがあってどう取り扱っていくかが難しい」という声がありました。「本当に置きたいのならあきらめずに少しずつでも置いていくべき」というような回答がだいたいみんなからでて、自分も「お店によって経営状態は全然違うし、ましてや個人ではほしい本を全部入れられないだろうけれど、そのなかで必ず売れる本、売れている本、売りたい本、売れないかもしれないけど新しい風になりそうな本、みたいなもののバランスをとってやっていくのが本屋の醍醐味のようにも思います」と(いうような)返答をしました。
自分はそんな舵取りを楽しいと思っていたりしますが、優れたバランス感覚を持っているとは言えません。直近の売上や展示と連携して販売できるかなどを考えながら今月は仕入れを抑えなきゃとか、ちょっと多めに入れてみようかなといったことを一冊ずつ悩んで仕入れています。しかも今年からは人件費のことも考えなくてはならなくて、慣れないからか、ただ経営に向いていないだけなのか仕入れ過多になっている月が多くて泣けてきます。本屋をやっているだれもがそんなこと考えないで好きな本を好きなだけ入れて売りたい、と願っていることと思いますが、ある意味ではこういう縛りが個々の本屋における意志ある選書に繋がっているとも考えられるでしょう。またそれと同時に、個人店であってもどうしたってある程度は商業の域から出ることはなく、システムの一部として機能していると言えます。お金のことは出来るだけ考えたくないですが、そうもいかないのが現実です。
でもタイトルからしてわたしたちを励ます、管啓次郎『本は読めないものだから心配するな』で著者はこう言います。

「効率よく利潤を上げることを最大の目的として動く貨幣の「共和国」に対して、すべての書物を「共有物」とする第二の「共和国」は、反響と共鳴と類推を原理として、いたるところで新たな連結を作りだしてゆく。そこでは効率や利潤といった言葉は、口にすることすら恥ずかしい。人々は好んで効率の悪さ、むだな努力、実利につながらない小さな消費と盛大な時間の投資をくりかえし、くりかえしつついつのまにか世界という全体を想像し、自分の生活や、社会の流れや、自然史に対する態度を、変えようと試みはじめる。」
(管啓次郎『本は読めないものだから心配するな』、筑摩書房(ちくま文庫)、2021年、27ページ)
世界の複雑さを知り新しい態度を示そうとする読者と共にある本という存在を、お金のシステムの枠組みのなかにありながら届け続ける本屋の役割を想う時、日々一冊でも誰かに本を手渡せる喜びを感じずにはいられません。
とはいえ、そんなことをはじめから考えて本屋をやろうと思ったわけではありません。お店をやるなかで本を読み、ひとと話すなかでそうなっていっただけという感覚です。ではなぜ本屋になりたかったのか、というところは正直自分でもよくわかりません。でも本気でやろうというか、やっていいんだなと思い、前を向くことができたのは6年前に亡くなった祖父のおかげです。
祖父はぼくが小さい頃に大きな病気をし、リハビリを兼ねてよく散歩をしていました。一緒についていくとおもちゃ付のお菓子を買ってもらえるので、祖父がでかける素振りを見せるといつも追いかけていきました。このことは確かな記憶として覚えているわけではなく、「そんなこともあったよ。おじいちゃんもひとりで歩かずにすむのが嬉しくてあんたが可愛いってよく言ってたよ」と親から聞かされた話という感じだったので、今でも少しひと事のような気がしています。でも、そんなわけで祖父はいつもぼくのことを気にかけてくれて、飲食店でアルバイトをすれば定期的に食べに来てくれたり、会えば「和也くん、今日も元気ですか? 健康一番に頑張ってください」と声をかけてくれました。ぼくが今のお店をやる前、地元で本屋のまねごとみたいなスペースを友人たちとやっていたときも真っ先に来てくれました(ある意味初めてのお客さんです)。何かを買うわけでもなく、椅子に座ってあたりを見回していたとおもったら立ち上がって、もう帰るねといって一緒に来た祖母を促し帰宅しようとしました。友人たちと見送りに出ると、祖父はみんなに向かって「これからもひとつ、和也くんのことをお願いします!」と大きな声ではっきりと言って深くお辞儀をしました。
大学まで出て就職しないで(親には教育費を返せと言われながら)書店でアルバイトをしつつなんとなく自分で本屋をやってみようかななんて思っていた若造の背中を、こんな風に押してくれるひとがいること、そしていままでもきっとこうやって自分を見守ってくれていたのだろうなと思い胸が熱くなりました。直接的に「頑張れ」と言われて気合いが入るときもありますが、それは一時的なもので、祖父のようにずっと見つめてくれているひとがいるということは長く励ましになるのだと思いますし、事実このことはいまも自分の心を灯してくれています。
そんなわけでなぜやりたいと思ったのかはよくわからないままにして、とにかくやってみるんだという意志を持って”本屋になろう”とやってきました。ミュージシャンがモテたいから音楽をはじめました、みたいに理由なんかたいしたことなくていいこともあるはずで、そのなかで「いつのまにか世界という全体を想像し、自分の生活や、社会の流れや、自然史に対する態度を、変えようと試みはじめ」ていたのかもしれません。ぼくが考えつくことなんてきっと数多ある本の中にすでに書かれてあるはずですが、読んできた本に導かれ、それをひとつずつ実感として手にしていく日々もまた楽しいです。
(第4回・了)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。