失敗について

制作におけるコントロールにどのようなものがあるのか、どういったパラメーターを意識するべきなのか、あるいは控えるべきなのかという点について論じてきました。その成功した状態については決定することが困難であることもお分かりいただけたのではないかと思います。では、狭義の失敗についてはどうでしょうか。ここではひとまず制作物が持つ「失敗している良さ」については除外することにします。
失敗しやすい状態
「失敗」の定義についての議論は長大になりそうなものですが、ここではシンプルに「コントロールするべきパラメータを知覚出来なかった状態」あるいは「コントロールするつもりで取り組んだパラメータをコントロールすることが出来なかった状態」と定義します。
この定義において、失敗しやすい状態とは次のような条件がある場合と言えるでしょう。
・コントロールするべきパラメータが適切に制限されていない状態
・コントロールする方法が難解な状態
・パラメータが不明瞭な状態
最初の2つは以前例として出したEtch A Sketchで滑らかな曲線を書こうとするケースなどが分かりやすい例です。慎重に2つのダイアルをコントロールしなければすぐに直線が現れて曲線ではなくなってしまい、ミッションは失敗します。この失敗を「曲線を書こうとする計画が失敗している」と捉えるのは制作ツールや身体がもたらす制約を所与のものとして扱いすぎています。あなたが作りたいと考えるものを自在に作れないのは道具を扱う身体操作の習熟度の問題か道具の未熟さに起因するものでしかありません。この「ままならなさ」が制作における楽しさそのものに近いのは、永久に一致することがないことが明らかだからです。楽しさのために「ままならなさ」を意図的に保持する必要性はほとんどなく、再現なく自在さを求めながら、それでも残るままならなさに不平を言い続けられる状態に飽きることは難しいでしょう。
3つ目はユーモアなどが挙げられるでしょうか。ある程度分析可能でも受け手に強く依存するために制作者側がその結果を得るためにパラメータに還元することは難度が高い試みです。テクニカルな意味で「上手さ」を向上させることは出来ても実際に笑えるかどうかをコントロールするのは熟練した芸人ですら失敗を免れません。
制作において失敗しやすい状態を避けるべきかどうかは状況によりますが、操作に不慣れな人が失敗を可能な限り減らしたいという状況は存在します。
カシオはQV-10という民生用デジタルカメラの先駆けを開発したメーカーですが、彼らが2008年に発売したEX-F1という民生用ハイスピードカメラの開発者インタビューで興味深いコメントを残しています。

もっと言えばシャッター・ボタンは失敗写真を生む元凶の一つとさえいえる。ユーザーがシャッターを切らなければ手ブレなんか起きないし、カメラ側で正しくタイミングをとらえられれば決定的瞬間も逃さずに済むからです。(「本当はカメラにシャッターなんていらない」,カシオの超高速機,その狙いと先にあるもの(前編)https://xtech.nikkei.com/dm/article/NEWS/20080124/146109/)
シャッター・ボタンとフレーミングは他のパラメータが自動化できるようになった中でも長らく残っていたマニュアルな要素でした。一般人が写真で失敗しないことを道具の目的に設定した場合、絞りやシャッタースピードと同様にシャッター・ボタンもそれらと同様に排除されうる、とカメラの開発者が認識しているのは非常に興味深いです。フレーミングやフォーカスに関しても排除する方法はあり、フォーカスを後で合わせられるように複数の視点をマイクロアレイによって取得して合成するLytro社のライトフィールドカメラや、周囲をすべて撮っておけばどこでも切り出せるという思想で作られているInsta360のようなカメラも存在します。
決断を強制されるパラメータを減らすことや、留保し続けられるようにすることでより幅の広い制作が可能になるかどうかでいえば、答えはイエスです。しかし、そもそも制作者がそのように幅の広い強力な決定権など求めているのか、より強力な決定権はよい結果をもたらすかと問われれば相当に怪しいと言わざるを得ません。
このようなリスク回避に使えるパラメータの除去・留保をそのままリスク回避のために使用すると、下ぶれがないというだけの緩慢で緊張感のない結果を生み出すことが多いですが、浮いたコントロールリソースの余剰分を他に振り分けることで他にはない効果を生み出すこともあります。

こちらもやや本筋からは離れますが、コントロールが不在であることそのものが良さに繋がる例として定点カメラを紹介しましょう。定点カメラはシャッター・ボタンもフレーミングも放棄したフォーマットだからこそ、すべてのフレームが並置され、出来事の差分のみが標本化される魅力を持っています。
Box Camera – FalconCam Project LIVE
研究用の鳥の定点カメラに「制作」としての要素を見出すことはやや難しいですが、インターネット黎明期にケンブリッジ大学に設置されたTrojan Room coffee potはその目的がコーヒーの残量をチェックするという実利的なものであるにもかかわらず、きわめて迂遠な方法で些末なものを観測するという構造に美を見出さずにはいられません。

一方で、失敗する可能性やリトライのコストが高いということが明らかなフィルムカメラなどは、制作者に緊張感という形で一定の影響を与えます。前述のプロセスの留保が困難なものほどこの傾向は強く、その決断に制作者の体重が乗っているという質感が制作物に付与されることはよく見られる現象です。もちろん、その大胆な決断の痕跡が鑑賞者にも明らかな場合においてそれが強度として評価されることもあります。こうした決断の価値を制作物の軸にするかどうかは、しばしば魅力的な誘惑として立ちはだかるでしょう。
メイキングを公開することについて

メイキング、あるいはビハインドシーンと呼ばれるものを、我々はどう考えるべきなのでしょうか。そもそも、これらは制作物の一部なのでしょうか。私個人としては積極的に公開されるのであれば、それは制作物の従属物という形でその一部であると考えています。同様の議論は予告編やステートメントなどに対しても行うことが出来ますが、いずれも「制作しない・公開しない」という選択肢が制作者側にある以上はその判断も含めて制作物の一部とみなすべきだと考えています。
メイキングを公開することは次のような効果があります。
・棄却したアイデアが明らかになる
・最終成果物からは伺いしれない投入コスト、手数が明らかになる
・後続制作者に対しての教育的効果
制作物そのものよりメイキングのほうが主であると鑑賞者が受け取った場合、そこには主従の転倒があります。その転倒こそが主目的である制作物や教育目的などの例外を除けば、十分に魅力的ではない制作物だったか、制作者や鑑賞者が認識している主従がそもそも誤りであるかのどちらかです。
制作者はとりわけ前者の転倒が起こらないように努めますが、そうした制作者本人の努力に反してこうした転倒が起こってしまうこともあります。たとえば古い映画などの場合、制作プロセスが現代と異なっていることで当時よりもメイキングのコンテンツとしての強度が上がっていること、本編の内容が現代の基準では評価が下がってしまうことなどが重なるとメイキングのほうが主として鑑賞されることがあります。このことをポジティブな側面で捉えるのであれば、作品の当時持っていた魅力が時間経過とともに減衰してしまったとしても、その制作プロセスが貴重なものになっていくことで制作物の寿命が伸びる、あるいは第二の鑑賞フェーズに移行して延命される、と言えるでしょう。
イレギュラーなメイキングたち
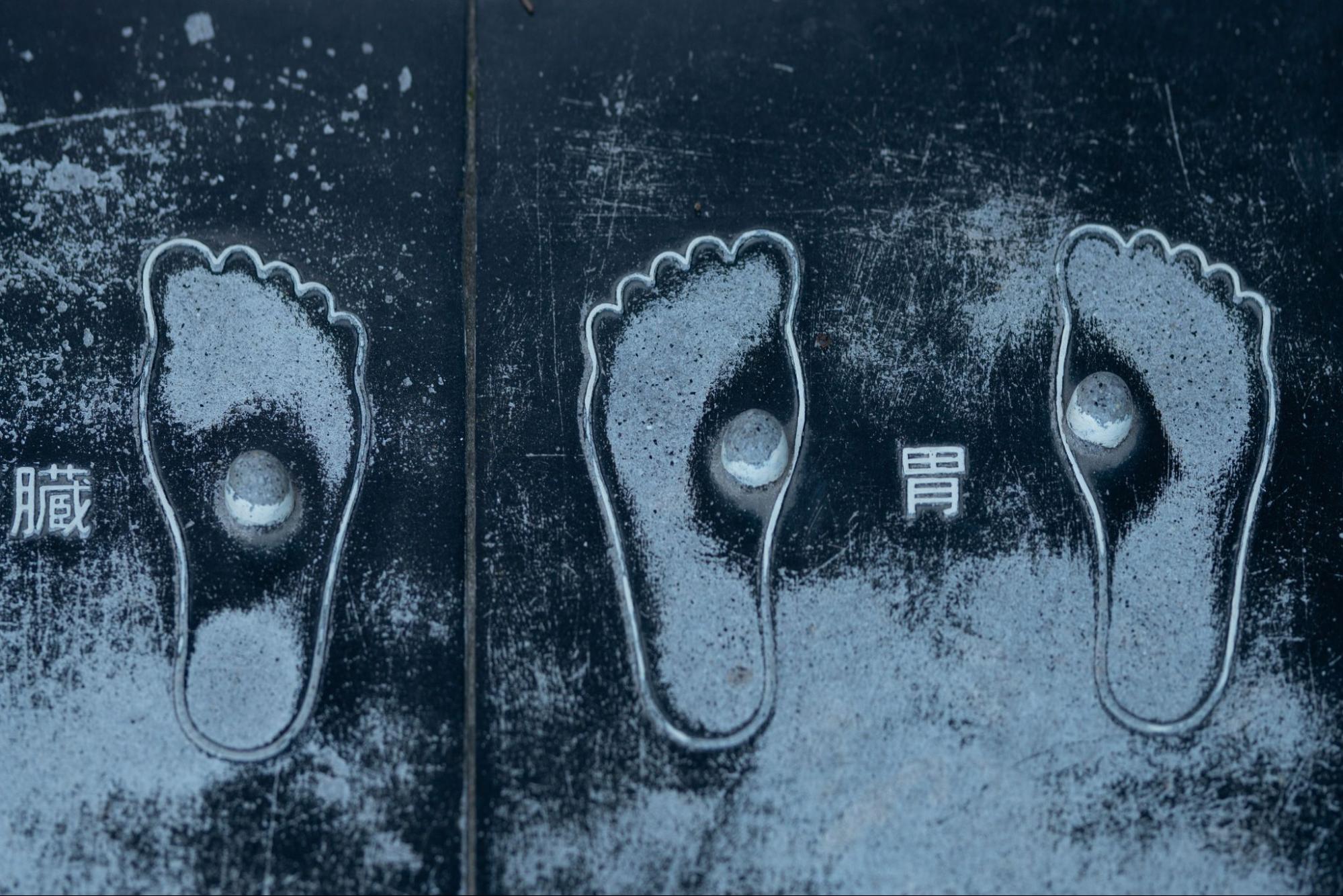
メイキングが制作物の一部であるという主張を補足するために、いくつかのイレギュラーなメイキングの例をご紹介します。本編の中に組み込まれているのかそうでないのかでまず分類するべきとも考えましたが、メイキングを見せる意志の強弱でしかないと判断し、分類の要素として除外しました。
フェイク・NGシーン
バグズ・ライフ(1998)のエンドクレジットにはCGで作られたキャラクターのNGシーンが流れます。この映画はCG映画ですから、本来のNGに相当するものはアニメーターが失敗したモーションなどが相当しますが、CGキャラクターが生きているかのような演出の一環として撮影現場を想起させる小道具(カチンコ)までモデリングして「キャラクターが演技に失敗したシーン」を新規に作成しています。アニメーションされた存在が生身の人間かのように扱われる構造はロジャー・ラビット(1988)や近年で言えば擬態するメタが制作した ビビデバ / 星街すいせい(official)(2024)にも存在します。しかし、pixarのNGシーンがこれらと異なるのはそうした演技をする俳優がいるという幻想のために本編が演技ではないという幻想を打ち消している点です。フルCGの映像が映画として成立するか懐疑的な黎明期に映画たらしめる要素として入れるというのは興味深く、アイデアとして作りたくなる動機はとても理解出来るのですが、この演出が作品の没入感を増大させるのか減少させるのかは議論の余地があります。
フェイク・メイキング
Coldplay – Strawberry Swing (Official Video)
Shynolaが2011年に制作したColdplayのこのMVはチョークで床に描かれたストップモーションを手法として採用しており、床に寝転がった演者とチョークの手描きによる表現の組み合わせが当時高く評価されました。
このMVで最も注目すべき点は、最初と最後に挿入されるメイキングショットです。注意深く見ると、実際にストップモーションとして撮影されているのは一部のフレームと演者のみで、その他の部分はチョークのテクスチャをマスクして制作されていることがわかります。
チョークや砂を使ったストップモーションの表現的特徴は、前のフレームからの変更が完全には消えずに強調され、変更していない部分がそのまま維持されることで独特な見た目が生まれる点です。しかし、この映像ではその部分がテクスチャで部分的に再現されているものの、ほとんどがマスク処理で合成されているため、手法特有の特徴は見受けられません。さらに、時折画面下部にスタッフが写り込んだフレームがアリバイとして挿入されていることからも、手法から得られる特徴よりも手法に伴う工数がいかに想起されるかが重要視されていると考えられます。
メイキング公開の効果として挙げられる「最終成果物からは見えない投入コストや手間が明らかになる」という要素は、前述の社会性、特に「大きなコストを支払ったことが明らかであること」を強調しています。こうしたクリエイティブなアイデアを情熱で実現したという見せ方は高い社会性を持ち、フェイク・リアル問わず広く支持されますが、社会性を重視するあまりフェイク・メイキングを行う制作者が増えると、実際に手法から得られる特徴を獲得するために工数をかけた制作者がそうした動機なのではないかという疑念を持たれることになります。その反動として、工数をかけていないことを強調することが社会性の否定として別の社会性(≒価値)を持つ場合すらあります。しかし、これもまた社会性という要素に過剰に適応した結果であり、環境の表現選択に収斂を引き起こすと言えるでしょう。こうした社会性との適切な距離感を保つバランス感覚が求められます。
というよりも、本来は環境に適応せずシーンの収斂に抵抗する態度こそがあるべき社会性なのではないかと考えています。
メイキング・ライク
コララインとボタンの魔女(2009)はLaikaスタジオによって制作されたストップモーション・アニメーション映画で、多数のメイキングが公開されている映画の一つです。通常のメイキングに加えて実際の映画には使用されず、新規にメイキング映像のために作ったアニメーションが存在します。
このアニメーションが特殊なのはアニメーターが人形の動きを調整している様子のストップモーションでありながら、その動かしているキャラクターがアニメーターを鬱陶しいと退ける演技が入る点です。これは漫画家が漫画のコマの中にいてキャラクターが語りかける構図と似ていますが、漫画の場合はあくまでもその漫画家の画は制作物であって制作者自身ではない点で一線を画します。
そして、この映像が独特のトーンを獲得しているのは、一つの動画の中に2つの時間が流れているからです。滑らかに動くキャラクターとコマ落としで動くアニメーターが異なるタイムラインを超えて干渉するように見えることが一層映像を魅力的なものにしています。正直な感想を言えば映画本編よりもこの短いシークエンスのほうが興味深く感じます。これは、ストップモーション・アニメーションがしばしば直面するジレンマであり、制作手法そのものがあまりにも魅力的であるがゆえに生じる問題です。
ストップモーションのように膨大な工数を要求する手法が経済的合理性を満たすことは非常に困難です。一方で、こうした手法の担い手が継続的に存在するためには、経済的な面でも技術継承の面でも定期的にある程度の規模の作品が制作され続ける必要があります。その点でLaikaスタジオが担う役割は大きく、積極的にメイキングを公開することも継続的な手法の担い手を増やすことの一助になっているという点もメイキングのポジティブな側面として見過ごせません。
メイキングを公開する(しない)という美意識
メイキングの公開についてやや消極的な話が続きましたが、公開自体は決して悪いことではありません。両者の動機について整理してみましょう。
公開する動機
・後続制作者に対しての教育的効果で貢献することでシーンや社会にとってポジティブな存在でありたい
・制作プロセスを秘匿することで発生する神秘を可能な限り取り除きたい
・制作者の意図はより正確に伝わったほうが望ましい
公開しない動機
・シーンや社会にとってのポジティブさを武器にしたくない
・投入コストが明らかになることによる評価の底上げを防ぎたい
・制作者が伝えたいことは制作物の範囲内で伝えるべきだ
ほとんどは相反するポリシーですが「こんなに簡単に出来るのか」というタイプの制作プロセスの開示は投入コストが鑑賞者の想定より低くなるのでどちらにも属さないものと言えそうです。そして、こうしたポリシーとは無関係な要素として「マメさ」という属性があります。私自身はマメさが欠落しているのでどちらかと言えば公開する美意識側のスタンスでありながら公開しない美意識であると誤認されても仕方がないと諦めている立場です。
工数が不安を紛らわせる

工数の可視化が鑑賞者に対して評価の保証材料として機能することは、社会性の項目で説明しました。しかし、この効果は鑑賞者だけでなく、制作者にも影響を及ぼします。制作者もまた、工数によって心の平穏を求めるのです。
制作プロセスを「アイデアの創出」と「実装」に分けて考えると、最終的な制作物のクオリティは、どちらか低い方のレベルがその上限を決定します。アイデアの段階は事前検証が難しい一方で、実装の精度向上や規模の拡大は比較的リニアな改善が可能です。そのため、制作者はアイデアの妥当性を信じつつ、実装の精度向上や規模の拡大に工数を投入せざるをえません。このプロセスは不安を伴うため、制作者は工数をさらに投入することで安心を得ようとします。実際にはアイデアに工数を投入することもある程度リニアに効果があることを過去の完成した経験から制作者は学習しますが、同時にそれが「打率の向上」であることも知っています。より手堅く制作物のクオリティを上げるには後者に投入するほうが低リスクであり、「打率の向上」によって期待値が上がると知っていても「失敗したくない」という気持ちは低リスクな選択を後押しします。こうした理由で制作の不安を紛らわすためには実装への工数の投入が選択されやすいのです。私自身もまたこの実装への工数でアイデアの貧弱さや制作の不安を誤魔化しながら制作してきた経験がたくさんあります。とりわけ、作業工程の中に効率化が難しい単純作業が含まれている場合、その作業を進めている間は「着実に進んでいる≒質が向上している」という感触を感じながらアイデアの部分への不安から目を背けることが出来て居心地が良い、という経験は何度もあります。
これらのことから分かるのは、アイデアの不確実性からくる不安という要素によって本来前者により投入するべき工数が後者に偏ってしまっているのではないか、というバイアスの存在です。
「心理的安全性」という概念は、集団内での個人の内心の開示に関連して使われますが、工数の可視化によって制作者と鑑賞者の双方が共犯関係を持ちながら「安全性」を確保している場合、一見した手堅さとは裏腹に制作者の心理的安全性が低い環境であると言えます。特に、シーンや作家が精度の向上や規模の拡大に過剰に重きを置く傾向が見られる場合、それは心理的安全性の低下を示す黄色信号と考えられます。たとえば日本のテレビアニメーションにおける作画コストの際限ない上昇は象徴的です。いわゆる「クリエイターもの」と呼ばれるジャンルでは、その制作物がこの価値観自体に言及しうるという構造から、あらゆることを度外視して何かに打ち込む姿を同様の度外視した工数によって美化するということが行われやすく、制作者・鑑賞者双方にとって深刻なフィードバックループをもたらしています。
心理的安全性が高いということは多くの人にとって「良さ」が分かりづらい制作物が許容される環境であるということを意味します。しかし、どの程度の人に届いたのかが明確に数値化されてしまう現在の状況では、多くの人に受け入れられやすい要素が制作物に備わっていることが求められます。
より多くの人に評価、期待されることから生み出される不安が大多数へ寄り添ったアプローチへの収斂を招くのであれば、「すべての人に受け入れられなくてもよい」「ステークホルダーを増やさない」という選択が制作の幅を拡張する重要な要素となるでしょう。
とはいえ多くの場合は実装が不足している

制作における「煮詰まり」が実装への偏りという形で逃避されることがあるというケースについて書きましたが、実際にこれが現実的な課題として発生するのはある程度経験を積んだ手の早い制作者に限られるでしょう。なぜなら、その領域の初学者が単位時間内に投入する工数やその精度は経験を積んだ制作者に比べて少なく非効率なため、ほとんどの凡庸なアイデアに対しても工数で改善できる余地が残るからです。ですから、初学者に対しては安心して実装の速度と精度の向上に偏って構わないと断言することができます。

