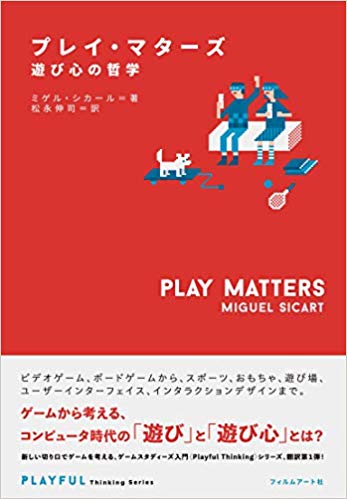広義の「遊び」に焦点を当て、ゲーム、インターフェースデザイン、おもちゃ、場所、アート、政治などをつなぎ、コンピュータ時代の新しい遊び論を提示する『プレイ・マターズ 遊び心の哲学』。
本書の刊行を記念して、訳者である松永伸司氏と、ゲストには吉田寛氏を迎え、ゲーム研究者として最前線に立つお二人(じつは公ではレアな顔合わせ)によるトークイベントが開催されました。
本書をわかりやすくかみくだきながらクリティカルに切り込む『プレイ・マターズ』読解と、現代のゲームスタディーズの潮流とそこから本書はどう位置づけられるのかを検討した、本書の理解がさらに深まる、アクチュアルで刺激に満ちたお話となりました。
・この記事は2019年6月11日にジュンク堂書店池袋本店にて開催されたイベント内容を再構成したものです
・[ ]は編集部による補足を、[ ]内数字で示した脚註は編集部による註をあらわします
- 吉田寛氏
- 松永伸司氏
松永:今日は『プレイ・マターズ』刊行記念イベントとして、東京大学の吉田寛先生にお越しいただきました。吉田先生は東大で『プレイ・マターズ』の原書の講読の授業をされているということもあり、今日は『プレイ・マターズ』のことについていろいろおうかがいしながら、またそこから広げて、現代のゲームスタディーズがどうなっているのか、といったことも話せたらいいなと思っています。
吉田:松永さんとはゲーム研究の仲間で、たぶん8年くらい前から知り合いですが、公の場でこうして二人で話すのはこれが初めてだと思います。松永さんは本書の訳者なので本の内容を一番知っているわけですが、逆にこの本の読者としてまだ経験の少ない私の方がポイントをつかみやすいということもあるかと思いますので、今日は私の方から、読者代表のような立場からいろいろ質問するかたちで進めたいなと思っています。
松永:まず、この本がどういう本かみたいな話を先にしたほうがいいですかね。
この本の副題は「遊び心の哲学」としているんですが、原書には副題はついていません。日本語訳するときに、タイトルが『プレイ・マターズ』だけだと何の本なのか意味がわからないということで「遊び心の哲学」という副題をつけました。この本は、シンプルにいうと「遊びとは何か」みたいなことをひたすら論じている本なんですね。ただ、ここで言う「遊び」は、従来考えられてきた「子どもの遊び」とか「ゲームをプレイする」とか、そういうわかりやすいかたちでの遊びだけではなくて、ふつうはあんまり遊びとは言わないようなもの──たとえば、遊び心を発揮するとか、遊び心を発揮したデザインとか──、そういうより広い意味での遊びとは何かを考えている本である、と。ということで「遊び心の哲学」という副題をつけています。
全部で8章あるんですけども[章タイトルは順に、遊び、遊び心、おもちゃ、遊び場、美、政治、デザインから建築へ、コンピュータ時代の遊び]、だいたいこういう論点だというのがわかるように章が組まれています。本書の特徴でわかりやすいところだと3章の「おもちゃ」とか4章の「遊び場」ですね。従来は遊びとかゲームと言うときに、どちらかというとルールが定まった遊びとか、実際の活動としてはっきりとかたちが定まったものとしての遊びが扱われる傾向があったんですけども、この本ですと、たとえば「おもちゃ」の章では、物として遊びとかおもちゃとか、それを使うことでどんなふうに遊ぶのかはプレイヤーの自由になるものなどが扱われています。また「遊び場」の章では、空間、それもはっきりと遊ぶかたちが決められていない、自由に使ってよいというかたちの空間、遊ぶ場というのが問題にされていたりする。なので、どちらかというと従来あんまり扱われてこなかったような遊びの側面というのが扱われている傾向にあるかなあと思います。あと6章では、遊びと政治の関係の話をしていて、これはなかなか今までになかった論点かなと思います。
ゲームスタディーズのなかの「遊び」の位置づけ
吉田:この本のタイトル『プレイ・マターズ』(Play Matters)は、「遊びが大事、遊びが問題だ」という意味ですね。この本の一番のポイントは、遊びの哲学を21世紀に向けてバージョンアップしようということです。その前提には、最近ゲームスタディーズは盛り上がっているのだが、そこでは遊びがほとんど考察されていない、という認識があります。ホイジンガ、カイヨワ以来の、あるいはいくつかの社会学的な遊び論はあるわけですが、それだけで止まっているという状況があり、ゲームスタディーズのなかで遊びが置いていかれていることに対する挑戦として、著者のシカールはこの本を書いた、と言えると思います。
松永:その通りだと思います。それでちょっと補足すると、ゲームスタディーズ自体は2000年前後くらいから制度化の流れがでてきたというか、学会とかジャーナルができてくるんですけども[1]、最初から「ゲームと遊びについての学際的な研究」という看板を立てているんですよね。だから、最初から遊びというのがひとつの対象として扱われているべきなのに、これまでは基本的にはゲーム、とくにビデオゲームが主な対象として扱われてきた。それに対するたぶん反発というか、それだけだと不十分だということなんだと思います。
吉田:そうですね。「play」と「game」は英語だと違う言葉になるし、日本語でも「プレイ」と「ゲーム」ってカタカナで言えてしまうから違う言葉なのですが、この二つが区別されない言語もあるわけです。なので、常にそこの区分は問題になるし、あとビデオゲームとゲーム一般の関係もじつは問題で、ゲームスタディーズが実質的には「ビデオゲーム・スタディーズ」になっているという批判もあったりするんですよね。ですから、プレイとゲームの関係と、ゲームとビデオゲームの関係が曖昧に重なったところにゲームスタディーズという領域がぼんやりと存在している。いろんな人が参加していてそれなりに受容されているにもかかわらず、ゲームスタディーズのなかのどこからどこまでがビデオゲームの話で、どこからどこまでがゲーム一般の話なのかとか、ゲームとプレイの境界はどこにあるのかということは、実はそんなに考察されていないことなんです。なんとなくビデオゲームを中心にゲームをとらえていて、それを現代における遊びの代表とみなしてしまっている傾向があるんですよね。この本は、著者のシカールは「ゲームではなく遊び(プレイ)が重要だ」と言っているんだけども、読むほうとしては自分の経験のなかでいろんな実例を参照しながら読むわけです。そうするとビデオゲームの例はすぐに思いつくんだけど、例としてはむしろ不適切なのかな、と思ったりして、読者として何を例に想定して読めばいいかというのがわからなくなることがたびたびあります。でもそれもこの本の魅力のひとつなのかなと思います。
ゲームと遊びの自己目的性
吉田:シカールは「ゲームは遊びの特権的形式である」と言っています。つまり、ゲームは形式化された、きわめて特殊な遊びであり、それは遊び全般からは切り離して考えられるべきだ、ということです。ではゲームという遊びがもつ特殊性とは何かといえば、この本では、自己目的性と形式性があげられています。これについてはどうですか? シカールはゲームは自己目的的でかつ形式的だと言っているのですが、ただ1章にあるように、遊びの定義のひとつに「自己目的性」が入っていますよね[後述]。ですから、ゲームだけがとりわけ自己目的的ではないという気がするんですけど、自己目的性ということに関して、ゲームと遊びの関係がどうなっているか、松永さんはどうお考えですか? 形式性に関してはわかりやすいと思うんですよ。ゲームは遊びと違ってルールがあって目標があるし、より形式がしっかりしているのが遊びとゲームの違いだというのはわりと古典的な論点なんですよね。それに対して、自己目的性というのは、どうとらえたらいいかなということなんですけど。
松永:シカールの言っていることに従うと、とりあえず遊びの特性を7つ出しているんですけど[文脈依存的 contextual、カーニバル的 carnivalesque、流用的 appropriative、撹乱的 disruptive、自己目的的 autotelic、創造的 creative、個人的 personal]、そのうちのひとつに自己目的性というのが入っている。自己目的性というのは何かというと、ある活動がまさにその活動をするためになされるということです。他の何かの目的とか成果を目指してなされるのではなくて、まさにその活動をするために何か活動をするということが自己目的的ということなんですが、遊びはその特徴を持っているとはっきり言っているんですね。もちろん、ゲームもその特徴を持っている。ただ、遊びには「遊び心」という側面もあって、その場合は自己目的性がないことがあるというような話がされています。シカールは「遊び」と「遊び心」を分けています。遊び心というのはそれ自体は遊びの活動ではなくて、すでになされている活動、たとえば仕事であったり、勉強であったり、そういう遊びではない活動に対して、一定のふざけた姿勢を持って接するということです。シカールは、遊び心は「態度」だという言い方をしています。遊び心には自己目的性は必ずしもない。勉強であればいい点を取るとか、仕事であればお金を稼ぐとか、まず現実の目的があって、それをやるうえで遊び心を発揮するというかたちになるので、もとの目的は失われていないというか、そのまま普段の生活の目的が維持されているということになる。そういう意味で、遊び心の場合は自己目的性は必ずしもないということが言えるのかなと思います。
遊び心の21世紀的バージョンアップはなぜ必要?
吉田:ここから第2章の「遊び心」の章に移れると思うんですが、遊びと遊び心を分けたことがこの著者と本書のひとつのオリジナリティですよね。ただ、遊び心が何かというのは、私には斬新すぎてまだよくわからないところがあります。シカールの説明によると、遊びが活動(activity)であるのに対して、遊び心は態度(attitude)であり、だから遊び心はいろんな活動に態度として入れていくことができるということなんですよね。そこに遊びと遊び心を分ける意味があります。第2章は遊び心(playfulness)が主題となっていますが、とくにコンピュータ時代における遊び心が何なのか、そこが読者としては気になるところです。つまり、「遊び心の21世紀的バージョンアップ」がなぜ必要なのか、「遊び心の哲学」の本がこの時代に書かれる意義はどの辺りにあるのか、という疑問です。遊びが人間にとってある程度「普遍的」な現象であるからこそ、遊びをめぐる状況が、この100年くらいでどう変わったのかを考えなくてはならないはずです。
シカールはどうやら、コンピュータシステムへの抵抗が今の時代には必要だと考えていて、そのことが、彼がこの本で遊びの哲学を展開した背景にあるようです。コンピュータというのは真剣かつ厳密な挙動をする機械であって、それに日頃われわれは接しているわけですよね。そういう状況で、そこに遊び心を入れていくと、Twitterのボットとか、フェイクニュースを作る自動化したサービスとか、面白い、変なものが出てくる。シカールはそれをカーニバル的攻撃と呼んだりもするんだけど、とくに第2章では現代はコンピュータの時代だからこそプレイフルな態度が必要なんだと言っている部分があって、そう考えると、21世紀型の遊びの哲学として、今まさに必要とされている思想なのかなという気もするんですよね。われわれはますますシステムによってがんじがらめにされている、だからこそ、そこに遊び心を入れて抵抗していく、というような。
松永:それもあると思います。この本では、これからは遊びをコンピュータに代表されるようなシステム的なものに入れていくことが大事だという話をしている部分が結構あるんですよね。そこはそうだと思うんですけど、一方で今の21世紀の時代は、全体の雰囲気が遊びの方向に向かっているみたいな書き方もしていて。「21世紀は遊びの世紀」みたいなことが言われているらしいんですよ、本当かどうかわからないけど(笑)。そういう、現代の雰囲気としての遊びとか遊び心みたいなのを結構重視しているところがあるかなと思っていて。具体的にいうと、コンピュータの話で、この人はアップルが結構お気に入りなんですね。僕は嫌いなんですけど(笑)。ようするに、アップルのデザインというのは、従来は工業的な機械であったパーソナルコンピュータをより身近な、個人的なものにするということで、デザインをかわいくしたりおしゃれにしたわけですよね。あとユーザーインターフェイスについても、ウィンドウを閉じるときに変形するというか、モーションのエフェクトを入れるのがアップルのOSでありますが、そういうのが遊び心のあるデザインの例として出されてますね。そういった本来システム的ではあるんだけど、それに遊びをかませているような文化が実際に最近出てきているという見立てがあるのかなと思います。

吉田:なるほど。今言われたアップルのデザイン、いわゆるユーザーフレンドリーデザインは、ドナルド・ノーマンの思想とつながっていますね。松永さん選書のブックリスト[『プレイ・マターズ』マターズ:遊びの大事さを理解するための21冊]にもあがってますけど、ノーマンの『誰のためのデザイン?』[2]をどう評価するかは、たぶんデザイン研究やプラットフォーム研究ではかなりクリティカルな問題のはずで、遊び心を入れているからいい、ということにはならないのだろうと思います。むしろ逆かもしれません。政治的議論にもなると思うので今日そこにつっこむのはちょっと難しいんだけども、遊び心のあるデザインについてはいくつかの評価の文脈があることを認識しておくべきかなと思うんです。ノーマンは認知科学者ですが、ユーザーエクスペリエンスの設計者としてアップル社に入り、アップルの先端技術研究所の副社長もやった人ですよね[3]。ボタンをできるだけ減らせというのがノーマンの思想で、そこからiMacなどが生まれたわけです。だから80年代から90年代にかけてのノーマンのデザイン思想は、Macintosh黄金期のアップルのデザインに流れ込み、そのまま今のiPhoneにつながっているんですよね。そのアップルは、周知のように、いまやGAFAの一角を占める企業となっているわけです。まあアップルという企業をどう評価するかというのは大きな話ですけども、いくつか複数の意見があり得るということですね。
松永:基本的に、デザインの機能主義みたいなものに対するアンチ意識がシカールにはかなりあって、それとアップル好きというのが一応シンクロしているのだと思います。いずれにせよ、この論点はデザインにおける機能主義みたいな話が結構絡んでくるということですよね。
プレイヤーが自由に遊べる場を作る=アーキテクトとは?
吉田:それと関連するのが「アーキテクト(建築家)」ですね。シカールは第7章で、「ゲームデザインは死んだ、これからは遊びのアーキテクチャの時代だ」と書いています。第7章のタイトルは松永さんの訳では「デザインから建築へ」となっていますが、原書ではシンプルに「Architects」です。この章では、作家性やトップダウン的なデザインが仮想敵になっていますね。それに対して、彼は、これからはアーキテクトの時代であるべきだと言うわけです。しかし他方でアーキテクチャは、ローレンス・レッシグや東浩紀が環境管理型権力を論じる際のキーワードでもあったわけで[4]、やはり権力装置としての側面を無視できない。強制や命令ではないかたちで権力が作動する機構がアーキテクチャと呼ばれてきたわけですが、しかし『プレイ・マターズ』のなかではそこについての議論がないままアーキテクチャの話がされるので、読んでいて何か足りないなと思いました。
松永:そうですね。シカールを代弁すると、われわれは「ゲームをデザイン」するという言い方をするわけですけど、その「デザイン」というのは結局のところゲームデザイナーが特定のゲームの仕方をプレイヤーに押しつけているという発想である、と。なので、そうではなくてもうちょっとプレイヤーが自由に遊べるような場を提供するべきだということを言っていて、まあかなり規範的な主張なんですけども。それで、その考えが「遊びの建築」とか「アーキテクト」という言葉で表されているんですが、ただ今おっしゃったように、建築を作るにしろ、場を作るにしろ、結局その作り手がいて意図的に場を設計するわけじゃないですか。ある意味でプレイヤーの方向づけをしているというか、その意味ではあまり変わらないんじゃないかなと思っていて。だから、ここで「デザインからアーキテクトへ」ということで、作家主義やトップダウンの設計を批判しているんですけど、あまり実質的な批判になっていないような気がする。たぶんそこは吉田さんの違和感と共通するところだと思います。
吉田:ゲームのデザインをアーキテクトとかアーキテクチャにたとえる思考パターンは昔からあるわけですが、そことの関係や類似はどうでしょうか? 典型的にはジェンキンスによる2004年の「ナラティブ・アーキテクチャ」論(「Game Design as Narrative Architecture」)がありますよね[5]。ゲームデザイナーが作るものは物語というよりも環境やスペース(空間)だというのがジェンキンスの主張のポイントです。これは当時存在したナラトロジー対ルドロジーという対立構造のなかで出てきた議論で[6]、ナラトロジーとルドロジーの間を取ろうとして、ジェンキンスはスペースに着目したんですよね。だから、シカールの言うアーキテクトとは少し議論の前提が違うのかもしれないですけど。ゲーム空間のようなかたちで、まさに空間の比喩でゲームのデザインの対象をとらえるということは昔からありますよね。

松永:ゲームはアーキテクチャにすべきという話はそんなに新しくないんですよね。だからどういうことなのかというはちょっとわかりづらい。ただ、このジェンキンスの論考について言うと、具体的にジェンキンスは「環境ストーリーテリング(environmental storytelling)」という話をしていて、論点は結構ごちゃごちゃしているんですけど、一番そこでポイントとなっているものは、ジェンキンスが引いているドン・カーソンという人が言っていることなんですが、ディズニーのテーマパークとかで物語を語るというやり方を、ゲームデザインに使えないかという話なんですよ。事例として出ていたのは「パイレーツ・オブ・カリビアン」のアトラクションだったと思います。ただ、そういう意味での建築って、テーマパークってまさにわかりやすいですけれど、作られたもの、作られた場じゃないですか。その点でいうと、たぶんシカールがほめているような建築とか遊び場とはちょっと違っている。
アーキテクチャというときに二通りあって、建築家の青木淳さんの『原っぱと遊園地』[7]という本があるんですけど、そこで近い話をしています。青木淳さんは空間を原っぱと遊園地の二種類に分けていて、原っぱというのは要するに何もものが置いていなくて、プレイヤーが自由に遊べる場として作られているような空間である。一方で、遊園地というのはすでに遊ぶ道具が置かれているわけです。つまり遊ぶ方向性が決められているような空間として設計されている。それを対比しているんですが、それは建築一般の話なんですけども、場を作るといったときにそういう二つの作り方があるんじゃないかなと思うんですよね。
吉田:なるほどね。この本でも遊び場(playground)が4章のテーマになっていて、そこで遊び空間(play space)とゲーム空間(game space)の区別と議論が出てますけど、今言ったような原っぱのようなものってシカールの本には出てきましたっけ?
松永:「冒険遊び場」というのがたぶんそれに近くて、一応物が置いてあるんですけれども、ただその物でどうやって遊ぶのかというのは決められていないような、そういう空間が重要なものとして出されている。
吉田:本のなかにもデンマークの公園に置いてある船の写真がありますね。
松永:そうですね。青木淳さんの話もそうですが、『ドラえもん』の空き地ってあるじゃないですか、土管が置いてあるやつ。冒険遊び場ってそれに近いものなんですよ。タイヤとかが置いてあるだけで、どうやって遊ぶかは自由にしてくださいという感じのものなので、たぶんそういうのを想定している。
吉田:それとテーマパークは明らかに全然違うだろうということですね。
物への注目としてのおもちゃ論
吉田:この本のもう一つの特徴として、オブジェクト、物、物質への注目があります。そこから3章ではおもちゃに一章が割かれています。シカールは、これまでの遊び論者が[ブライアン・サットン゠スミスを例外として]おもちゃを論じてこなかったと指摘し、ヴァルター・ベンヤミンやスーザン・スチュアートなど、批判理論や文学理論の論者に依拠しながら玩具論を展開しています。たしかにシカールの言うとおり、ゲームスタディーズのなかでもおもちゃ論はあまりみかけない、という印象は私にもありますね。
松永:少なくとも、「おもちゃ」というタームで議論されていることはあんまりなさそうですよね。一応『SimCity』とかはソフトウェア・トイと言われることはあるんですよ。開発したウィル・ライト自身がそう呼んでいるんですが、それが何か理論として深められているという感じはあまりないですよね。
吉田:おもちゃのデザインとゲームのデザインって違いますかね。というのは、使い方の手がかりみたいなものをデザインすることはできるのか、という疑問が私にはありまして。
松永:多くのゲームのデザインは違うと思います。おもちゃ的なゲームはありますけど。
吉田:話が少し拡散してしまうかもしれませんが、シカールは「遊びは流用」だと言っているわけですよね。流用とは、別の目的に使われることが普通にありうる、ということです。そうするとたとえば、デザイナーの仕事ではなくてユーザーの仕事なのか、あるいは流用を誘発するようなことがデザイナーの仕事なのか。他方で、デザインというのは、なるべく流用されないように限定してやるのがデザインの仕事だという一般論があるわけですね。だから、デザイナーが何をすべきか、プレイヤーが何をすべきかということについて考えると、おもちゃという物体は、結構ややこしいなと思っているんです。おもちゃのデザインって何をどこまでやるのかということについては、どう思いますか。
松永:僕はおもちゃデザイナーじゃないのでそこはわからないですが(笑)。僕はあまり普段子どもと接しないですけど、吉田さんはお子さんいらっしゃるので、そこでたぶんおもちゃにわりと触れる機会があると思うのですが、子どもがおもちゃに触れるときにどういう行動するのか。一応おもちゃごとに想定された遊び方ってある程度あると思うんですけど、けっこう無茶苦茶じゃないですか。小さい子どもほどあんまり従わないというか。
吉田:そうなんですよね。それでいうと、「プロシージャルなおもちゃ」というのも論点として面白いなと思ったんですよ。プロシージャルなおもちゃってどういうものかというと、ピタゴラスイッチみたいなやつですよね、たとえば。
松永:『のびのびBOY』という、『塊魂』の作者の高橋慶太さんが作ったアプリがあるんですけど、それが事例として出されていますね。
吉田:働きを外から観察するというやつですよね。まあ『のびのびBOY』はインタラクティブでもありますが。
松永:『SimCity』も例として出されています。『SimCity』はどういう例かというと、ほっといても街がどんどん発展していくとか、ほっといたら原発が爆発するとか、ようするに放置していても勝手に動くおもちゃであり、動いているのを見るだけでも楽しい、みたいな遊び方もできる。
吉田:シカールがベンヤミンやサットン゠スミスを引いて、おもちゃは世界の縮図であり、子どもはそれを繰り返し遊ぶことで、世界の振る舞いを理解する、と述べているのを読んだとき、私がまっさきに連想したのは、ピタゴラスイッチのようなものでした。たとえばドミノ倒しなどもそうですが、最初の一手はプレイヤーがやるにせよ、あとは勝手に展開していってそれが小さな世界を作っていき、その進行を見ているのが面白い、というタイプのおもちゃがありますよね。この本のなかでそうしたプロシージャルなおもちゃが重視されているというのは結構面白いなと思いました。おもちゃなんだけどプレイヤーは基本的に機械の動きを観察するだけで、自分が触る機会はほんのわずか。そういうのを典型例としておもちゃの物質性に注目する議論は新鮮でした。
松永:ポイントはたぶん、そのオブジェクトというか、物から遊びが発生するという発想なんですよね。遊びというのはあくまでプレイヤーがやる行動、あるいは態度なんだけれども、それを誘発するのは物なんだという。それでいくつかの誘発のバリエーションが語られているという感じなんだろうと思います。ビデオゲームってプログラムなわけですよね。機械として実装されているわけで、ある意味でおもちゃと言ってもいい。その機械を使ってどうやって遊ぶかというのはわりとプレイヤーに委ねられている。古いところだと中沢新一さんが「バグと戯れる」っていう話をしているじゃないですか[8]。これは『ゼビウス』が具体例ですけど、バグというのはようするに機械の内にすでにあるものです。作り手は想定していない、それが正当な遊びだと思ってはいないんだけれども、ただ機械の内にもうそれが物として存在しているので、プレイヤーはバグを使って遊べる。その意味で、おもちゃで遊んでいるのに近いのかなという気がしました。作り手が想定していないような遊びって、ゲーマーが普通にやりがちなことじゃないですか。チートとかハックとかもそうですけど。
吉田:確かにそうですね。そうすると、デザインの余白みたいな、隙間みたいなものにおもちゃ性があるみたいな感じになる。
松永:はい、隙間性を持っているのがおもちゃという感じですね。
吉田:わかります。そういうふうにうまく説明できるかなと思っていました。
松永:でも、結局それも、隙間を生むためのデザインみたいな感じで意図されちゃうわけですよね。たとえば『マインクラフト』みたいな。そうなると、またそれでいいのかという話になるかもしれないので、そこはいたちごっこというか、どこまでいっても作り手が常についてくるというか、あるいはどこまでいってもプレイヤーが常に作り手から逃れていくというか、そういう追いかけっこのような気もしますね。
吉田:シカールも言っていますが、ゲームスタディーズのなかでは、どうしてもゲームを、遊びという行為を外側から枠付けるものとしてとらえる傾向が強いんですよね。たとえばシステムや形式、ルールといったかたちで。しかし玩具論では方向が逆で、物から出発して、物が何を可能にして何を不可能にしているのかというように考えが進んでいくので、そういう意味でも玩具論は一読者として新鮮でした。デザイナーがいてプレイヤーがいるのがゲームですが、おもちゃの場合、ゲームよりも作者性が希薄だと思うんですよね。物があるだけで十分で、その物を誰が作ったかということは遊ぶ人にとってはどうでもいいんですよ。ただしシカールは、前出のノーマンの「アフォード」の概念を、おもちゃのデザインにも適用しています。たとえば、バウンドさせたり転がしたり投げたりできることは、ボールという物質の基本的設計に組み込まれていますが、他方、遊び方や使い方は極めて限定されたかたちでしかおもちゃのなかにデザインできないんですよね。そのように物質的な制約や限界から、遊びを考えることができる点で、玩具はとても示唆的だなと思いました。
松永:たぶん遊び場の話もそれに近いんでしょうね。つまり、遊び場とおもちゃというのは結構似たような話で、おもちゃの場合はオブジェクトとしてもうあるやつですけど、遊び場は空間全体をおもちゃというか遊び道具として作って、自由に遊んでもらうという話なので。似たような話の流れなのかなと思います。
遊びの「美」とは新しい世界を見せてくれるもの
吉田:第5章では「美」がテーマになっています。私も美学芸術学研究室というところで仕事をしているので、「美」がそう簡単には説明できない厄介なものであることは分かっているつもりですが、この書は「美」を相当広義にとらえているなというのが私の印象です。シカールは、「美」が指すものを意図的に拡げているようにもみえます。5章で主に論じられているのは、関係性の美学と対話の美学、パフォーマンスの美学の三つです。人間関係を生み出したり、対話によって人と人との関係を深めたり、ある関係を別の関係へと転化したりするようなことも含めて、彼は「美」と呼んでいます。「美」という題をもつ章でこうした議論が行われることについてはどう思われますか?
松永:僕も美学が専門だとか言っていますけど、こういう「美」の使い方は結構変だと思いますね。そういう文脈があるんだろうとは思うんですけど、あまり普段接しないような使い方だなと。具体的に言うと、この人は、新しい世界を見せてくれるものみたいなものを全部「美」と呼んでいるんですよね。だから、たんに「快い」とか普通の意味で「美しい」みたいなことだけじゃなくて、とにかく新鮮な見方で世界を見られるようにしてくれるものを「美しい」と呼んでいる。だから、場合によっては虐待的なゲームであったり、痛みを伴うようなものが「美しい」ものとして語られている。
吉田:そうですよね。そうとしか読めないというか。
松永:そうとしか読めないですね。
吉田:たとえば1章では遊びの定義が7つ出されていて、そのそれぞれが後の各章で応用されているじゃないですか。5章の場合、そうした他の章とのリンクのようなものはどうなっていますか。
松永:正直、5章が訳してて一番つらかったところで(笑)、何を言っているのかわからなくて。
吉田:なんかその答えは想定内で、5章はちょっと特殊な感じがしたんですよね。
松永:そうですよね。5章は訳を読んでもわからないかもしれない、訳者がわかってなくて。ただひとつ言えるのは、シカールは「遊びの美」って言い方をしているんですけども、それは遊びのひとつの様態であって、遊びの定義の話ではないのかなという気はしています。つまり、「遊びとは一般にこういう特徴を持っている」というのが1章の内容なんですけども、5章では、そうした遊びの中でとくに美しさを持った独特の種類の遊びのあり方が論じられていて、具体的にそれは、新しい世界を見せてくれるものだという議論なのかなと思っています。
批判的に物事を見る態度
吉田:最初にご紹介がありましたように、私は現在、自分の大学のゼミでこれを学生と一緒に読んでいます。今日会場にもその何人かが来てくれています。そのときに議論になったのが、5章で例にあがっているいじめごっこです。いじめごっこは、本当のいじめと区別がつかないことが多いわけですが、それを遊びとしてどう評価したらいいのだろうか、ということです。シカールは「Fat Man Down」という、その場で一番太っている人をからかうゲームを「対話の美学」の例にあげていますが、それを日常の中に位置づけるのは難しい気がしています。つまり、遊びは「ごっこ性」を含むわけですが、たいていのいじめは「いじめごっこ」から始まるんですよね。というより両者は連続しています。だから、最初は遊びでやっていたいじめごっこが本当のいじめに直結してしまう、という現象は、ほぼすべてのいじめにあてはまるもので、そういうことを考えると、わざとからかうことや「心の痛み」のようなものを、遊びの文脈に置いてよいかどうかは少し疑問です。
松永:具体的にいじめゲームの例として出されているのって、北欧のいわゆるノルディックLARP(ライブアクション・ロールプレイングゲーム)の一種でジープフォーム(Jeepform)ってジャンルのゲームなんですけど、かなりラディカルなケースですよね。具体的には、太っている人をいじめるごっこをするというゲームなんですけど、その太っている人役をする人は実際に太ってなきゃいけないというルールがあって、ようするに実際に太っている人をいじめるということになるんですよ。結果として、そのプレイヤーは嫌な気分になるだろうという議論なんですけども、たぶんいま吉田さんが懸念していたのは、それを本当に無邪気な子どもたちがいじめを楽しんでやっちゃうみたいなことで、そういう場合はよくないものとして機能するんですが、ただある程度大人というか、反省的な態度でそういう遊びをやってみると、あ、これはよくないんだ、と批判的な物事の見え方になるということで、この章の事例として出されているんじゃないかなと思います。
吉田:位置づけとしてはそうですよね。そういうものまで「美」に含まれているんですよね、この本では。
松永:ただ、やっぱり線引きは難しい。やっていることは普通のいじめと一緒なので。だからそこで何が違うのかというと、結局それをどれだけ批判的に見るかという観点の問題、態度の問題で、ゲームそのもののあり方がどうというよりはそれをどういう態度でやるかみたいな、そういう話になっているのかなという気はします。
吉田:そうですね。また、通常のゲームプレイとしてはありえないような退屈や苦痛の経験をもたらす「虐待的ゲーム」も、この「美」のチャプターの中で論じられているんですよね。
松永:具体的には『Desert Bus』とかですよね、例として出てきたのは。
ゲームスタディーズにどう跳ね返るのか
吉田:本書はゲームではなく遊びと遊び心を主にした本ですが、この本がゲーム研究にどのように跳ね返るのか、何かフィードバックがあるのかということを考えるとすると、ひとつはそういう虐待的ゲームのようなものをこういうかたちで拾うのは面白いなと思ったんですよね。私はメタゲーム、つまりゲームについてのゲームという観点から虐待的ゲームに注目していて、『Desert Bus』についても論じたことがあります[9]。でもこの本では、それとは違うアプローチで、脱自己目的的ゲームや脱形式的ゲームを扱っています。これは「美」のチャプターに限った話ではないんですけど、この本はゲームという枠組みを越えようとしているからこそ、ボーダーライン上にあるゲームをうまく拾えているんじゃないかなと思います。ゲームのボーダーラインとして考えられるのは、目的や形式がなかったり、希薄だったりするゲームですが、それらは遊び論のなかにうまくはまります。それらをメタゲームと呼ぶよりも、遊びに近いゲームとしてとらえたほうがいいかもしれない、と思ったりもしました。

松永:おっしゃる通りで、昔ながらのゲームというのもやっぱり引き続きありますけど、もっと多様化しているんですよね、今のビデオゲーム文化は。そういういろんなゲームのあり方をどうやって拾うかといったときに、従来のゲーム観だと不十分で、具体的にいうとまさにイェスパー・ユールの『ハーフリアル』[10]がゲームの定義論をやっているわけですけど、『ハーフリアル』で言われているような古典的なゲームっていうのは、いまの状況にそんなにぴったりあてはまらないようになってきている。それに対して、シカールの言っているような遊びという観点から見ると、いろんなものがより見通しが良くなるということなのかなと思います。まあそれがどこまで成功しているかわからないですけど、でもひとつの見方を与えているとは思います。
行為をすること、飽きること、対象の移り変わり
吉田:「美」のところに話を戻しますが、これに関連して、松永さんが2018年に出された『ビデオゲームの美学』[11]のなかで提唱されている、美的行為論のお話もうかがいたいと思っています。松永さんの構想する美的行為という言葉と、シカールの言うbeauty(美)というのは関係あるのかないのか、また松永さんのこれからの仕事としてこの本がどう役に立つのか、どうしてこれをこのタイミングで翻訳しようと思ったのかというようなこともおうかがいできれば。
『ビデオゲームの美学』については、私もまだきちんとした応答ができていなくて、こんなざっくりした言い方になってしまって申し訳ないのですが、この本の骨子は「ビデオゲームを行為の芸術として定義する、ゲームプレイを美的行為として位置づける」ということなんですよね。そして松永さんは最後に、それを「遊びの哲学」につなげていきたいという構想を語っておられます。『ビデオゲームの美学』の最後にはシカールが引かれていて[12]、そういう意味ではこの本を翻訳する伏線はすでにあったわけですけど、そのようにゲームが美的行為であるという考え方を取る松永さんにとって、あるいは松永さんの構想する遊びの哲学にとって、この本の意義やインパクトというのはいかがでしょうか。
松永:一応、意図としてはですね、この本を訳すことによって、美的行為をめぐる遊びの哲学が進展するんじゃないかという期待を持って訳したんですけど、たぶんあんまり進展していなくてですね。むしろ僕が想定していたような美的行為とは違うかたちでの遊びの姿を見せてくれたという感じで、ある意味でありがたいし、ある意味でちょっと困惑しているところがあって。『ビデオゲームの美学』の一番最後の章のタイトルが「そして遊びの哲学へ」というんですが、まあ「そして伝説へ」のパクリですけど(笑)、まさに、次は遊びの話をしたいと思っていたんですよ。それでこの本を訳したんですけど。
ただやっぱり僕が想定していた美的行為というのはあくまで行為の一種なんです。美的行為と普通の行為とがどう違うのかというと、たとえば、ふだんわれわれは、「今日は池袋に電車に乗ってきました」とか、「さば定食を食べました」とか、「スタバでアイスココアを飲みました」とか、普通の行為をしますよね。それに対して、ゲームとか遊びをするときの行動とか行為というのは、独特の微細な感覚とか、ちょっとした身体の動かし方とか、すごい煮詰めて考えるとか、そういう何か特殊な能力を発揮しなきゃいけない、そういう独特な経験をしていると思うんですよ。その独特さを「美的」と呼んでいるんですけども、なぜ美的と言うかというと、ようするに美的経験とか美的判断、たとえば芸術作品を見るときとか、音楽を聴くときとかに発揮する能力って、それは知覚の能力が主ですけど、かなり繊細なところに注意を向けるわけじゃないですか。あと、デザインの見た目とかを気にするときも、1ミリ違ったら全然違うものに見えちゃうとか、評価が変わるとか。そういう微細な感覚みたいなのが一般に「美的」と呼ばれるものなわけですが、それを知覚のレベルだけじゃなくて行為のレベルの方にも適用できるんじゃないかという発想なんです。

吉田:そうすると、「美」という言葉にそんなに引っ張られなくてもいいわけですね。われわれが何かいつもと違う鋭敏な態度になるとか、ちょっと違う視点を持つとか、という意味での美的行為は、5章で言われているような美の話と結構つながるかなと思います。
松永:つながる部分もあると思います。ただ、結局この人がポイントを置いているのは、そういう行為を通じて新しい世界を見るというところなので。僕はむしろ、新しい世界を見るかどうかはどうでもよくて、とにかく能力の行使の仕方が独特であるというところに注目したかったので、ちょっと違うかなと。まあ原因と結果の関係かもしれないですけど。
ひとつ、美的行為につながる話なんですけど、僕の遊び観だと、遊びというのは常に飽きるものだと昔から思っているんですね。同じものはずっとやり続けられない。たぶんそれにはいろいろな原因があると思うんですけど、とにかく遊びというのは対象が移り変わっていくというか、あるものに飽きてまた次のものに飽きて、という感じで、どんどん対象が移り変わっていく特徴を持っているなとずっと思っていて。たぶん美的なものというのもそれに近い性質を持っていて、やっぱりある能力を行使していくと慣れちゃうんですよね。パターン化しちゃって、今までは難しかったものが簡単になっちゃう、というのが飽きるという状態で、それでまた対象を変えていくという流れがあるものだと思っているので、そこらへんはわりとシカールが言っている遊び観とつながるところがあるかなと思っています。
吉田:その点は私も興味があります。私は最近「トイフィケーション」という概念を提唱していて[13]、それは「おもちゃ化する」という意味なんですけども、シカールのこの議論からも大いに影響されたんです。つまり、ゲームに飽きたときに、勝手にルールやシステムを流用して別の目的のために使うということをわれわれは日常的にやっているんですよね。ひとつのゲームのなかでもトイフィケーションは起こっていて、それはクリエイティヴィティというよりはむしろ「飽き」から出てきている部分も多いと思うんです。これを同じようなことを井上明人さんは「焦点の移動」という言葉で表現しています[14]。井上さんは『ファクトリオ』というゲームをとりあげて、プレイヤーがある作業をし、その作業が飽きた頃にはそれがうまく自動化して次の作業にフォーカスを持てるようになるというわかりやすい構造があるゲームの例として示している。つまり、ゲームのデザインにとっては、プレイヤーが飽きそうな頃合いで、作業をまとめてパッケージ化し、自動化できて、プレイヤーの関心が別の段階に移行できる、というのが重要なんですが、そうした「焦点の移動」ができているゲームとできていないゲームがある、というのが井上さんの指摘です。同一のゲームの中でも「作業感」がある部分とやりがいがある部分は分かれていて、しかもそれが時間とともに変化していくんですよね。ゲームに飽きたら、次はどうするのか。言葉使いや問題設定は違いますが、多くの論者が似たようなことにいま興味を持っているのだなあと感じています。
松永:『ハーフリアル』にもそういう話がありますよね。ユールはチャンク化という言い方をしていますけど、チャレンジ(挑戦)がどんどんチャンク化[15]する、つまりいままでチャレンジだったものがパターン化されてしまってチャレンジじゃなくなって別の対象にまたチャレンジを求めるっていう。基本的にゲームのプレイというのはそういうダイナミズムの中にあって、やっぱりひとつのことをやり続けるというのはなかなかなくて、どんどん対象が移り変わっていくというのが普通なんじゃないかな、と。まさに、流用とはそういうことですよね。「縛りプレイ」とかがわかりやすい例で、自分で何か縛りを設定することによってチャレンジを作るということで、それもある種の流用として理解できるのかなと思います。
吉田:ありがとうございます。だいたい、ちょうどいい時間じゃないですか。
松永:フロアに投げましょうか。なにか喋りたい、聞きたい人がいましたらなんでもどうぞ。
質問1:先ほどおもちゃの話が出てきたのでそれに関連しておうかがいします。おもちゃのデザインとデザイナーの仕事についてお話がありましたが、非常に面白くなおかつ難しいテーマだと思いました。おもちゃには遊び心からプレイヤーの中でできあがってくるというパターンもある気がします。たとえば、子どもの遊びのなかで石ころがおもちゃになったり、拾ってくる木の枝がおもちゃになる。それは、木の枝を拾ったことでそこから空想のごっこ遊びが始まるというパターンももちろんありますけど、冒険ゲームをしているなかで木の枝を拾ったことがきっかけで、木の枝が剣のおもちゃの代わりを果たすようになるような、遊び心からおもちゃが生まれるということがあると思います。そうなるとデザイナー視点ではないおもちゃも出てくる可能性があるんじゃないかなということが気になりました。
あと、もう一点別の質問で、シカールさんは今回この本で、遊び心というものを導入することで、遊びの概念の枠を広げようとしているのか、それとも新しく考察の対象として遊び心というものを別に作ろうとしているのか、どちらが近いのでしょうか?
松永:二つ目をお答えすると、この本には明晰に書かれていないので、訳者からしてもよくわかりません。というのは、遊びという言葉がいくつかのカテゴリーに適用されているんですね。あるところでは「活動」とはっきり言っているんですけど、一方では「存在のモード」みたいな微妙な言い方をしていて、それがどれだけの広がりを持っているのかとか、具体的にどういうものを想定しているのか、結構わかりづらく書いているんですよ。だから、どっちなのかとか、遊びはどこまでの範囲なのかみたいな、そういう分析的な考えで読まないほうがいい本だと思います。
一点目に関しては、本のなかにも、おもちゃというのは最初からおもちゃとして作られているパターンと、おもちゃになるというパターンがあるという話はちょっとだけ出てきます。だから一応は両方拾っているということは言えるけど、ただそんなに議論は展開していないですね。
吉田:ちなみに、おもちゃにもいろいろありますが、例えば任天堂がもっともライバルとしてきたおもちゃは何かというと、この本でも出てきますけど、LEGOなんですよね。LEGOはデンマークの会社です。ちょっとおまけのおまけみたいな話ですが、デンマークには一回だけ行ったことがあります。シカールが教えているコペンハーゲンIT大学に呼ばれて研究発表を行いました。ただそのとき彼はサバティカルでいなかったんですけど、彼の同僚にたくさん会いました。本の31ページに「ニンジャ」をプレイしている様子の写真が載ってますが、これがコペンハーゲンIT大学の建物です。このなかにシカールも所属するコンピュータゲーム研究センターが入っているんですけど、そのとき彼らはLEGOの会社と共同研究を始めるというようなことを言ってましたね。ゲームではないし、ビデオゲームともまったく違うカルチャーなわけですが、デンマークには強力なおもちゃの伝統としてLEGOがあって、それはこの本にとっても大事な背景かなと思いました。
松永:この人自身はデンマークの人ではないですけど、やっぱり今コペンハーゲンに勤めているからか、デンマークの例いっぱい出てきますよね。冒険遊び場もそうですし。デンマークの文化的な背景みたいなものは結構効いているのかもしれないですね。
吉田:LEGOについてもう少し話すと、私は自分の子どもと一緒に名古屋のLEGOランドに行ったことがあります。LEGOのブロックにはもう60年以上の歴史があるのですが、60年前のブロックと今のブロックが組み合うんですよね。つまり、おじいさんやおばあさんが遊んでいたような、当時のブロックと今のブロックを一緒に混ぜて遊ぶことができる。それがLEGOのすごいところだと思うんです。いわば、まったくOSレベルでの変更がなされていない。そうした息の長さは、コンピュータプログラムでは真似できない部分かなと思ったりもします。
あと、これは立命館で一緒に仕事をしていた頃に元・任天堂の上村雅之さんが言っていたことなんですが、任天堂がLEGOのどこをすごいと思っているかというと、ブロックをはめるときもはずすときも、ゆるすぎず、きつすぎず、絶妙に作られていて、しかもその手触りがフィジカルに気持ちいい、ということなんです。
松永:気持ちいいということですよね。一部スカスカのものがありますけど、あれ気持ち悪いですよね。わかりますそれは。
吉田:60年前のブロックと今買ってきたブロックをくっつけて遊べる。手触りの感覚も当時から変わらない。それはおもちゃの理想のかたちかもしれません。
松永:その玩具論の話のところで最後にちょっと出てきますけど、物質的な気持ちよさみたいなものも結構重視していますよね、この人。おもちゃを考えるときにたんに機能に注目するだけではなくて、そういう身体的な気持ち良さみたいなのも含めて考えようというのが、わりとマニフェストとしてあるのかなと思います。

質問2:ゲームの哲学というときにアリストテレスの倫理学が参考になると話している人がいたのですが、この本もアリストテレス的な路線が念頭にあるのかな、と。人間が種子のように持っているプレイフルなものを、遊びとかゲームとかいろんなかたちで徐々に開花させていくという感じで見たときに、そういう発想が「ロマン主義」ということとも著者の中でつながっていくのかな、と。あと本の最初の方で幸福論につながっていくところありますよね。遊びや遊び心というのは、善ではなくて、人間の幸福を作っていくために積み上げていく徳のようなものとしてシカールは考えているのかなと思いました。
あと、さっき、遊びというのは飽きるという話もありましたけど、もしかしたらその反対が中毒なのかもしれない、と。シカールは前衛芸術というのは遊びの要素を持っていて、それが既成の制度の転覆的な要素になっていたという話をしているので、遊びというのは常に芸術のなかの反体制的な要素であるかもれない。そうすると、従来の普通のゲームに対して、そのゲームを罠にかけるようなものをすごく凝縮したものをプレイフルと考えているのだとしたら、純粋にプレイフルなものが常に遊びとして長く成立するようには思えないので、普通の「いわゆるゲーム」みたいなものが世の中に支配的にあって、それを時々破壊したりずらしたりするようなある種の革命的な契機としてのプレイフルというようなものを彼は肯定しているのかなというふうに読めた。そこで考えていったときに、遊びというものをシカールは「世界内存在」の存在様態だというような話をする。「世界内存在」の在り方というのは普段隠れているんですよね。普段は「Das Man」として人間が埋もれているんだけども、ある種の契機では「世界内存在」として際立つという、そういう存在論的なことを考えると、プレイフルなものというのはやっぱり普段隠れざるをえないというか、日常の中でやっぱり支配的なものとしては成り立ちにくいものではあるのかなというような、そんなことを思った次第です。
吉田:ありがとうございます。最後の締めとしていい質問だったと思います。存在のモードとしての遊びがあって、それは今おっしゃられたように常に顕在化していなくて、潜在的にはあるということで、最後は松永さんにまとめていただきたいんですけど(笑)、この著者はそういうような幸福論とか、人間の定義のひとつとして「遊び」ということを考えているわけですよね。
松永:遊ぶことこそ人間だみたいなこと言っていますよね。ただ、おっしゃったように、たぶんほどほどに遊べっていうことなんですよ、この本で言っているのは。常に遊んでいたらやっぱりダメで、遊びというのは、たまに普段の生活から、人間の存在の本質みたいなものが現れるんですよね。たまに現れるという、そこにやっぱり重要さがあるのかなという気がします。そういう感じの本なのかなと。テキトーですけど(笑)。
〈編註〉
[1]学会組織としては、DiGRA(Digital Games Research Association、2003年にフィンランドを本部として設立)、学会誌としては『Game Studies』(2001年に創刊したオンラインジャーナル)など。松永伸司「ゲーム研究の全体マップ」(松永伸司編『ゲーム研究の手引き』所収、文化庁、2017年、3–17頁)参照。同冊子は以下よりダウンロードできる。https://mediag.bunka.go.jp/mediag_wp/wp-content/uploads/2017/05/guide_to_game_studies_v2_public.pdf.
[2]ドナルド・ノーマン『誰のためのデザイン?──認知科学者のデザイン原論』(増補・改訂版)岡本明・安村通晃・伊賀聡一郎・野島久雄訳、新曜社、2015年。
[3]ノーマンは1993年から1997年まで、アップル社のフェロー兼最先端技術研究所である「Advanced Technology Group (ATG)」のバイスプレジテントを務めた。同研究所は1997年に閉鎖。
[4]ローレンス・レッシグ『CODE──インターネットの合法・違法・プライバシー』山形浩生・柏木亮二訳、翔泳社、2001年。東浩紀の「環境管理型権力」についての議論は多くの著作に及ぶが初期の一例としては、「情報自由論──データの権力、暗号の倫理」(初出『中央公論』2002年7月号‐2003年10月号連載)http://www.hajou.org/infoliberalism/index.html、東浩紀・大澤真幸『自由を考える──9・11以降の現代思想』日本放送出版協会(NHKブックス)、2003年など。
[5]Henry Jenkins, “Game Design as Narrative Architecture,” in Noah Wardrip-Fruin and Pat Harrigan (eds.), First Person: New Media as Story, Performance, and Game (Cambridge: The MIT Press, 2004), 118–130.
[6]「初期[2000年前後]のビデオゲーム研究は、物語論[narratology](ゲームを物語として研究する)対ルドロジー(ゲームを固有のものとして研究する)の論争として考えられることが多かった。この論争は、たんに表面的な言葉の争いでしかない場合もあれば、重要な論点についての真剣な議論になる場合もあった」(イェスパー・ユール『ハーフリアル』松永伸司訳、ニューゲームズオーダー、2016年、26–27頁)。
[7]青木淳『原っぱと遊園地──建築にとってその場の質とは何か』王国社、2004年。
[8]中沢新一「ゲームフリークはバグと戯れる──ビデオゲーム『ゼビウス』讃」(初出『現代思想』1984年6月号)『雪片曲線論』中公文庫、1988年、174–197頁。
[9]吉田寛「メタゲーム的リアリズム──批評的プラットフォームとしてのデジタルゲーム」東浩紀編『ゲンロン8 ゲームの時代』所収、ゲンロン、2018年、76–98頁。「単純な課題を与えてプレイヤーがそれにどの程度耐えられるかその忍耐力を試すもの」という「虐待的ゲーム」の典型例として『Desert Bus』が言及されている。
[10]イェスパー・ユール『ハーフリアル──虚実のあいだのビデオゲーム』松永伸司訳、ニューゲームズオーダー、2016年。
[11]松永伸司『ビデオゲームの美学』慶應義塾大学出版会、2018年。
[12]『ビデオゲームの美学』の終章の結び近くの註記において、短くシカールへの言及がある。
[13]一例として、立命館大学ゲーム研究センター2018年度第7回定例研究会(2019年3月)、吉田寛「メタゲーミングとトイフィケーション──〈ゲーム〉はどこにあるのか?」。http://www.rcgs.jp/?p=13.
[14]井上明人「ゲームはどのように社会の問題となるのか」東浩紀編『ゲンロン8 ゲームの時代』所収、ゲンロン、2018年、136–156頁。
[15]「一連の作業を遂行する効率がよくなる」こと。ユールの引いているヒルデ・ハイダーとペーター・フレンシュの論文引用箇所より(『ハーフリアル』、127頁)。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。