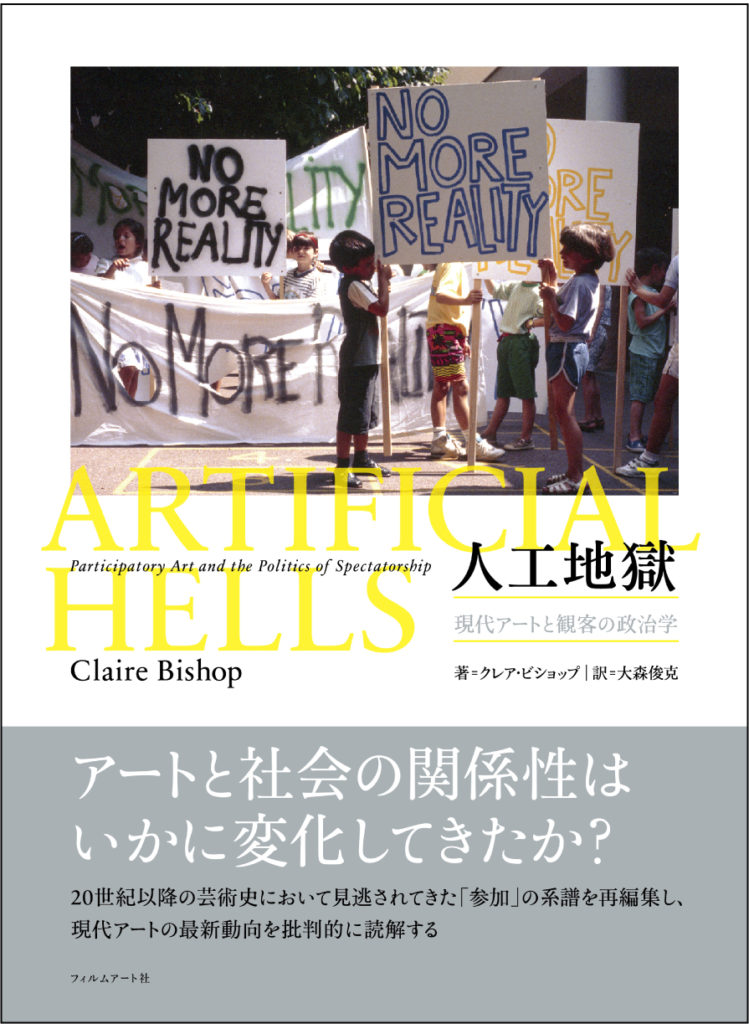本対談は、2009年のテート・モダンにおける未来派の展覧会にあわせて、定期刊行誌「TATE Etc.」に掲載された、クレア・ビショップとボリス・グロイスによるディスカッションである。今日の美術批評において最重要存在であるビショップ、グロイスの両名が、主に未来派による一連のパフォーマンスを「参加」の観点で評価しながら、その後続となった各時代・各国の「参加」をめぐるアートの事例を挙げ、現代における参加型アートを読み解くヒントとしている。 本対談で挙げられた各事例はいずれも、ビショップが『人工地獄』で詳述し、ひとつの歴史として編み上げているものである。さらに終盤の参加型アートの「失敗」をめぐるビショップとグロイスの議論は、両者の立場の相異を明らかにすると同時に、『人工地獄』の後半の章においてより深く掘り下げられている。現在でも色あせない二人の議論は、『人工地獄』のもうひとつのイントロダクションとして読むことができるだろう。
※対談内の関連する図版は、原文(英語)が記載されている下記のサイトでご覧いただけます。 http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/bring-noise
- 「事を構える(ブリング・ザ・ノイズ)」
- クレア・ビショップとボリス・グロイスによるディスカッション
- 収録:2009年5月1日
- 初出:Tate Etc. 2009年夏(第16)号
- 翻訳:大森俊克
【概要】
未来派は、その前衛的な絵画作品が語られるとともに、市民を挑発し、敵意を煽ろうとしたパフォーマンスもよく知られていた。ときに鑑賞者との相互交流を引き出した未来派は――ダダやシチュアシオニストの運動、アラン・カプローの「ハプニング」から今日の表現に至るまでの――参加型アートの先駆けとなった。テート・モダンでの未来派の展覧会の期間に合わせて、『Tate Etc.』誌は2人の美術専門家を招き、その歴史について詳しく論じてもらった。
ビショップ:今日私たちが参加型アートというと、たいていは合意に基づいたり協働したりというかたちを思い浮かべるわけです。しかし立ち戻って未来派のアーティストについて考えてみると、彼らが考える参加とは市民を挑発し、怒らせ、あるいは煽り立てることを狙いとしたものでした。これは「娯楽演芸宣言(Variety Theatre Manifesto)」(1913)といった当時の印刷物からもよく分かります。そこで紹介されている、鑑賞者を混乱させるための提案をいくつか挙げてみましょう。「強力な接着剤をいくつかの座席に塗りたくり、この結果、観客の男女は引っついて立ち上がれず、人々の嗤笑を誘う」。「同じ席のチケットを10人に売りさばき、八方塞がり、口論に次ぐ口論が起こる」。「不安定で激しやすい、札付きの変わり者の紳士淑女に招待券を配る。すると卑猥な身ぶりをともなった大騒ぎが起こり、ご婦人たちは眉をひそめ、いざこざがいくつか起こるだろう」。「座席にホコリを撒いて、痒みとくしゃみを人々にくらわす」。これらは子供じみた挑発なのでしょうか。それとも、未来派の政治的な意図と結びついたものだったのでしょうか。
グロイス:未来派が企てたイベントについての記述を読むと、彼らがつねに身ぶりや行動、スピーチによって反感を煽ろうとしていたことがわかります。もっとも知られる未来派宣言の1つが、「戦争は、世界の唯一の浄化手段だ」というものですね。こうした姿勢は市民の怒り、そして不快感さえ引き起こしました。そこで意図されたのは、19世紀には芸術を鑑賞する者の立場として一般的であり、かねてから続いていた、観客の当たり障りのない沈思黙考の振る舞いを終わらせることでした。目標はアーティストが企て、最終的なコントロールを握ったイベントへと、鑑賞者を巻き込むことでした。ただし、その関係性は敵対というかたちをとったわけです。鑑賞者を安全圏に置くよりも、彼らの「敵」となるほうを重視したのです。
ビショップ:その手立てとしてパフォーマンスを活用していた点は重要ですね。とくに、未来派が娯楽演芸を(夜に公演されたパフォーマンスである)「夜会(セラータ)」のモデルとして活用した点です。まず夜会の特色といえば、さまざまなパフォーマンスの断片的なエピソードです。例えば、娯楽演芸やキャバレー(演劇的な催し、詩や宣言文の朗読など)。そして次に、娯楽演芸とは下層階級の娯楽形態だということ。それは伝統に倣うブルジョワの演劇よりも、はるかに相互交流の性質をそなえていました。ここであらためて、「娯楽演芸宣言」からマリネッティの言葉を引いておきましょう。「娯楽演芸は、観衆との協働を求める唯一のものだ。観衆は、とぼけた覗き魔のようにひとところに留まらず、活動や歌に騒々しく加勢し、オーケストラに加わり、不意の行動や風変わりな対話を演者と交わすのだ」。彼は別の箇所で、観客席でタバコを吸う人たちについて語っています。それによって舞台と観客の間に、統一された雰囲気が醸されました。
グロイス: 20世紀のはじめに人々が持っていた芸術観には、19世紀を特徴づけていたロマン主義的な伝統の要素が残っていました。芸術の目標は、愛や敬服といった観客の魂の奥深い感情に訴えかけることだったわけです。とりわけ芸術が真に迫り真正性を有するとすれば、鑑賞者は圧倒されることになります。しかし、19世紀末には次の点が誰の目にも明らかになりました。つまり、人々はえてして完全に中立的で、芸術に心を動かされずにいたということ。この傾向が如実にみられたのが、芸術を愛でるという慣習を持たずにいた――あらたな民主主義のもとにある――鑑賞者でした。ゆえに未来派はふたたび鑑賞者から深い情動を引き起こそうと試行錯誤したわけです。ただしそれは、敬服や愛ではなく、むしろ憎しみや怒り、嫌悪といった感情でした。とはいえ、その目指すところは同様にロマン主義的な目標のままでした。鑑賞者の穏やかな気持ちをかき乱して、有無を言わさぬ感情がそれを圧倒するに任せるということですが、ただしその感情とは負の感情なのです。
ビショップ:マリネッティは、大衆的な鑑賞者は書物を通しては得られないことを強く確信していました。彼は、イタリア市民の90パーセントは劇場に足を運ぶと記しています。ゆえに人々に接触する手立てとして臨場的なパフォーマンスが意図的に選ばれたのであり、そしてそれを支えたのが、イベントのほぼ直後にプレス・リリースやレビューを頒布するというメディアの宣伝活動です。
グロイス:未来派はしばしば自らを道化として提示したということもまた、銘記すべき点です。彼らは自身をさまざまな色に塗って、訳のわからない言葉を叫び、「ノイズ・ミュージック」をつくりました。彼らなりのやり方で、「コンメディア・デッラルテ(即興の仮面劇)」という中世の伝統にあらたな命を吹き込もうとした。ロシアの未来派も同様のことをしました。彼らは、コマ割りの漫画に似た「ルボーク」という中世ロシアの民俗的な伝統を援用したのです。彼らは自身の顔にペインティングを施して、ハンカチの代わりに大きな木のスプーンをポケットに入れて街を練り歩き、通行人を怯えさせました。
ビショップ:ロシアの未来派もやはり、それをメディアの注目によって強化させたのでしょうか。
グロイス:ええ、もちろん。とくにそれに長けていたのが、ダヴィド・ブルリュークです。彼はイベントを敢行する前にプレスの文章をまとめて、物議を仕掛けました。もし世間を騒がせるようなことが起きなかったときは、ブルリュークはジャーナリスト向けにそれをでっち上げたのです。
ビショップ:ですが彼らは、イタリア未来派が国粋主義の使命とかかわったようには、政治的スタンスと結びついてはいませんでした。
グロイス:その通りです。ロシア未来派が国粋主義とまったく無関係だったとは言いません。というのも、彼らは聖画やプリミティブ絵画、民間伝承の詩、ロシアの地方主義を称える風潮について知っており、それらに影響されていました。未来派は、国民文化のはるか遠い過去――考古学的とさえいえるような時代に光を当てることを欲しました。ただしそれらは、軍国主義に彩られたものでも、国家を重視するものでもなかった。むしろ、政治面でロシア未来派と一定の共通性がみられたのは、ロシアのアナーキズムです。政治的アナーキズムとは、ロシアでは非常に伝統があるものなのです。
ビショップ:イタリア未来派には、2つの段階があるといえます。1つは1917年ころまでの初期。もう1つは、いっそうファシズムと歩調を合わせて、表現に陰りがみえてきたそれ以降の時期です。
グロイス:それはある程度は事実でしょう。ただしマリネッティの未来派宣言には、すでに1909年までにはファシズム的なテーマに貫かれた最初の表明があります。あたらしくて力強く、近代化ならびに産業化されたイタリアがヨーロッパに台頭するという展望がそこにみられます。ロシア未来派の詩人や画家において、国家を誉め称え、それを戦時体制に持ち込んで軍国化することを望む存在は、当時はまったく考えられませんでした。
ビショップ:しかしそれはある意味で、ルネッサンス以降のそうした強い歴史的伝統に覆われ、そこから逃れようとしていたイタリア芸術の到達点でもあった。
グロイス:ええ、その点は言うまでもありません。一方でロシア芸術は、当時のあらゆる芸術の例に漏れず、学究的な体制と自然主義に統べられていました。
ビショップ:私が考える未来派の3つの特徴は、政治、挑発、そしてメディアの活用です。その後の時代の芸術において、これらが同じ割合で存在するというのは珍しいことです。
グロイス:未来派は、全体的な――全体主義的とさえいえますが――空間を切り拓こうと努めました。人々が逃れることのできない空間です。それは、後年にミハイル・バフチンが語ったカーニバル的空間のようなものです。その一部と化すとき、打ちのめされる、侮辱される、蔑まれるといったことから逃れることはできません。人々は能動的な立場に押し出されます。それしか選択肢はないのです。彼らは観客として、いつしかアーティストに対して自分の立場を主張していたことに気づき、このとき芸術表現の一部となるのです。これは本当の意味での新機軸だったと思います。観客の中立的な立場を切り崩してしまい、第三者でいるという可能性を許さないことで彼らを引き入れるのです。
ビショップ:おっしゃる通りだと思います。私が関心を持っているのは、いかにしてイタリア未来派のパフォーマンスがダダに発展したかということです。というのも、ダダの(フーゴ・バルが立ち上げた)ナイトクラブ「キャバレー・ヴォルテール」で繰り広げられた内容に、同様のパターンが顕在していることがわかるからです。ただしそこには、確固たる政治的スタンスはありませんでした。彼らはじつに、ニヒリズムと無意味さを受け入れることで既存のスタンスを拒絶しました。とりわけ挙げておきたい、1つの(後期の)ダダ・イベントがあります。そこでは、キャバレーでのパフォーマンスという従来の方法が放棄されました。アンドレ・ブルトンやトリスタン・ツァラたちは、1921年4月にパリのサン・ジュリアン・ル・ポーヴル教会をめぐるツアーを企画しました。より正確に言うと、その教会の庭をめぐるツアーです。そこは当時、ゴミ捨て場として利用されていました。彼らはそのイベントのフライヤーで、「存在理由のない」場所への「散策と探訪」の音頭を取ることで、「疑わしい案内の無能さを正す」ことを求める――そうした複数の計画済みのツアーの1つとして、それを宣伝しています。風光明媚なところ、または歴史的関心や情緒を誘う場所へと注意を促す代わりに、ガイドツアーという社会形式の意義を脱臼させることにその目的があったわけです。ダダのグループはまた未来派同様、メディアの注目を集めるために広告とプレス・リリースを巧みに利用しました(例として、1920年初頭のイベントではチャーリー・チャップリンの登場が告知されました)。未来派との違いという点で決定的となった契機は、ブルトンがこのイベントの分析に取りかかったときです(彼は、このイベントを失敗として――そして、皆の意気消沈を招くものとしてとらえました)。ブルトンは、もはや市民の反感を買うことの必要性を感じなくなっていました。そしてこれは、ダダからシュルレアリスムへの変遷、その重要なきっかけとなりました。ブルトンはもはや挑発行為に関心を持たず、代わりに倫理的なスタンスの構築に興味を抱いたのです。
グロイス:ええ、ダダにはある種の政治的アナーキズムに共通するところもありました。フーゴ・バルの『時代からの逃走』を読めば、この点はとくに明らかです。やがて政治的アナーキズムに幻滅していったのち、バルもまたダダの運動から離れました。しかし総じて、未来派とダダのキャバレー・ヴォルテール、またはシュルレアリスムには相容れない要素がありました。未来派の活動はたいてい、自由な公共空間でなされました。キャバレー・ヴォルテールの場合、人々はチケットを買って積極的に参加に臨んだと考えられます。例えばそれは、ダリとブニュエルの『アンダルシアの犬』の上映にあたり、騒々しい反応を示したような者たちのことです。
ビショップ:これと似た芸術表現への接し方が今日あるかといえば、想像しにくいですね。1920年代のアヴァンギャルド作品を前にしてのそうした騒乱の報告には、尾ひれが付いているのかもしれません。しかしおそらく、鑑賞者は挑発行為に反発して騒々しく応じるということ――ほかでもなくその「喜び」を目的として、そうしたイベントに参加したということも事実なのだと思います。
グロイス:感受性が違うのですね。例えば、芸術作品の体験をしたためたあらゆる時代の日記に目を通すと、面白いことに、あまりにラファエロやレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画に感銘を受けて、卒倒したり、食欲をなくしたり、眠れなくなる人々がいました。キャバレー・ヴォルテールのイベントの記録では、気絶したり診察を要したりする人々という、多くの事例があります。当時のロシアにもやはりそうした鑑賞者がいました。マヤコフスキーが「プーシキンは、同時代という船から投げ出されるべきである」と喝破したそうですが、このとき何人かがあわや気を失いかけました。
ビショップ:感情面での結びつきがあったということでしょうか。ショックによるものや、享楽によるものといったふうに。
グロイス:人々はきわめて長きにわたってこう信じていました。人類の文明や社会、また日常生活にさえ依って立つ一定の宗教的、精神的、倫理的、ならびに美学的価値が存在するのだと。彼らの考えでは、これらが疑問視・攻撃され、喪失するとなれば、自らの本質的な存在基盤は打ち砕かれてすべてが崩壊し、そしてこの全面的なカタストロフィを乗り切ることはできないのです。今日では、イデア的価値が私たちの文明の基盤をなすと信じる者はいません。人々を卒倒させるのは、せいぜい金融危機のニュースくらいでしょう。かつて人々は、ある種の魔術的な方法を介して、芸術が彼らを殺すといったことがありうると信じていました。そうして芸術は、一定の方法でそれ自体と鑑賞者の距離を超えて、彼らの心を動かし衝動を与えるようになった。19世紀初頭に求められていたのは、観客を釘づけにするほどの美的対象の創造です。もしくは、必ずやショックを受けるほど恐ろしく、醜悪で不快感を与えるようななにか。しかしこれらの目指すものが別かというと、私はそうは思いません。その目標は、中立的で穏やかな沈思黙考の余地を奪い去る、それほど力強い対象をつくり上げることだったのです。
ビショップ:ここ数十年間の参加型アート、例えばハプニングについて考えてみると、それらもまた強制的であったことがわかります。例えばアラン・カプローのいくつかのハプニング作品では、行動は筋書きに沿ってなされ、すべての人々が批評的考察の余地なく共同参加しました。これは――「漂流(デリーヴ)」を分析・検証した現存するいくつかの報告を読むと――協働的なイベントに向けたシチュアシオニストのアプローチとわずかに異なります。とりわけ1960年代にギー・ドゥボールが理論構築したようなシチュアシオニストの集いでは、芸術の超克が求められました――ただし、芸術を「生」として実現させるという目的のもとに。これを観客というスタンスの抹消のもう1つの手立てとみなすこともできるでしょう。一方のグループが行動し、他方のグループが別の者たちの作品を観察、鑑賞してそれについて思索するということを、重視しなかったのです。1960年代を通して、さまざまな参加の形式が芸術として行なわれました。そしてそのすべては、「解放」という名目で複数の方法によってなされた。ジャン=ジャック・ルベルが手がけ、そして理論を施したフランスのハプニングの場合、それは身体の性的な解放です。カプローの参加の場合、それはむしろ、参加者が世界に対するいっそう知覚的にして共鳴しやすいアプローチを持ちうる、そうしたある種の実存的な覚醒だといえます。
グロイス:言うなれば、あらゆる事象はつねに解放にかかわるものなのです。近代のヨーロッパ文化全体には、解放という要素が底流しています。ただ私が思うに、そこで問われるべきは「なにから解放されるのか」ということ。1940年代後半と50年代でいえば、それは全体主義的な空間からの解放です。重要なのは、実存主義――真正の自己の発見といったことにかかわる問いでした。そして1960年代にはにわかに、全体主義という過去、また全体主義的な経験の懐柔(domestication)のプロセスを再編するという潮流が出てきます。それはリベラル・デモクラシーの堅固な枠組みのうちになされ、個人主義からの解放、西欧のブルジョワ社会の諸条件のもとにある個人を疎外から解放することであるとみなされました。
ビショップ:では、リベラル・デモクラシー以外の体制下での挑発的な参加――あるいはじつに(あなたが用いた表現でいえば)「懐柔された」参加についてはどうでしょう。西欧では、参加はつねにスペクタクルの社会と対置関係にあります。これを(右派の軍事独裁政権のもとにあった)中南米、そして(共産主義下の)東欧とロシアにおける参加型アートと比較することは有効でしょう。とくにオスカル・マソタとオスカル・ボニーが1966年と68年にブエノスアイレスで行なったパフォーマンスのような、アルゼンチンのケースです。それらはきわめて暴力的なもので、例えばサンティアゴ・シエラのより近年の表現の先駆けとなりました。さらには、独裁政権がふるった圧制的な社会体験をなぞるかのような、グラシエラ・カルニヴァレのアクションもあります。1968年にロサリオでの「実験芸術サイクル」の最後の作品となったカルニヴァレのアクションでは、鑑賞者が画廊に閉じ込められました。カルニヴァレは彼らが外を見られないようにそのスペースの窓をポスターで覆ってしまい、鍵を持って立ち去ったのです。そこで関心が寄せられたのは、どんなことが起こるか――鑑賞者がどうやってその状況から自身を解放するかを目撃すべく、待機するということです。カルニヴァレは、結末が明らかでない幽閉=投獄のひとときをもたらそうとしました。結局、窓を割って皆のために逃げ道をつくったのは、中にいた人物ではなくて路上にいた人でした。私が公の場でこの表現について話すと、一連の実験的な芸術表現というかたちでこうした有無を言わさぬ行為をアーティストが行なうことに対して、一部の聴講者は恐怖を感じます。東欧は東欧で、やはり別種の方略があります――公共空間とプライベートな空間の関係性が独特であり、そしてじつに作品は共産主義を背景として生まれるということを理由として。
グロイス:そしてそれは、芸術実践の背景としてはきわめて異質なものです。
ビショップ:モスクワを拠点に1976年から活動している「集団行為」は、共産主義における参加型アートの好例ですね。そのパフォーマンスは通例、鑑賞者であり参加者となる人々を電車でモスクワ郊外に数時間連れ出すというものでした。その辺鄙な土地はときに、マレーヴィチの白の絵画群を彷彿とさせる雪景色の野原でした。一部の参加者たちはそこで、謎めいた体験にさらされることになります。そしてそれが、この集団による事後的なディスカッションと分析行為の焦点とされました。これらの分析は、「集団行為」の理論を担う中心人物、アンドレイ・モナスティルスキーが編纂した計8巻の刊行物『郊外への移動』にまとめられています。あなたはこれらの行為に何度も参加したわけですが、その1つに《出現》(1976)があります。それは、参加した鑑賞者たちが遠くはなれた野原になにかが現われるのを待ち、それを目撃するように指示を受けるというものでした。このときモナスティルスキーはすべての目撃者を写真に撮って、そしてのちにこう説明しました――彼ら全員が、モナスティルスキーのために現われたのだと。あなたはこうおっしゃっています。つまりこうした数々の出来事は、批評的な客観性と観客性の場を立ち現すのだと。その場とは端的に言って、共産主義の諸条件のもとには存在しなかったリベラル・デモクラシーの空間です。共産主義ではすべての人々が参加者であり、観客性と批評的分析のための「外部」となる空間がありませんでした。
グロイス:最初に釘を刺しておかねばならない点だと思いますが、共産主義とは独裁政権ではないのですね。独裁政権という概念で前提となるのは、国家から独立した市民社会の存在です。この市民社会は国家とは別の存在であり、そして国家による抑圧を受けます。ソビエト連邦では、誰も抑圧のもとには存在しませんでした。なぜなら全人民はそもそも国家機構の一部であったからです。全人民が国家に資する存在だったのです。ソビエトという国家とその市民の関係は政治的なものではなく、政治的抑圧の関係でさえありませんでした。それは雇用者と被雇用者の関係だったのであり、それ以上のものではありません。ソビエト連邦において抑圧されるには、まずそのためのきっかけをつくらねばならない。そして「集団行為」の参加者が為したのは、こういったことなのです。この点において、彼らのプラクティスは西側諸国の参加型アートの向こうを張るものです。キャバレー・ヴォルテールから1960年代のハプニングに至るまで、アーティストたちはリベラル・デモクラシーや個人主義化、美学における懸隔を回避しようと努めました。それはロマン主義が崇高を希求したように、全体主義的な体験を希求したわけです。ただし参加型アートの場合、それは個人としての属性の棄却の経験、また熱狂的でディオニソス的、かつ全体主義的な場における主体性の破砕の経験――政治的崇高の経験です。フーゴ・バルの言葉を借りれば、それは「大衆の喧噪の中で、個人の表明手段の消失を経験すること」なのです。これらのハプニングに出向くということは、19世紀にスイスの山岳地帯に行くようなものだった。全体主義的な昂揚に身をさらすということは、西欧国家では諸条件に保護された上でのものでした。当時のモスクワでは、この昂揚は生活の中にくまなく浸透していました。ゆえにそうした状況で人々は、むしろ社会全体に欠けている観客という立場を人為的に(artificially)つくり上げようとしたわけです。
ビショップ:つまり「集団行為」は、客観性と外在性の創出に腐心していた、と。
グロイス:彼らは客観性や観客性を構築し、そしてリベラル・デモクラシーの真空地帯をつくろうとしたのです。なぜならソビエト連邦が、すでに参加のための1つの強大な装置だったのですから。その空間の内部で、私たちはいわば未開の土地、雪の積もった荒れ地に赴き、それによってアーティストと観客の二分化に立脚しつつリベラル・デモクラシーの人工的な位相を切り拓こうとしました。それはいわば、虚無の空間です。国家の手の及ぶところではなかった。その本質においてプライベートな場なのです。しかし、破壊行為と参加型アートには明らかに親近性があります。未来派のアクションが旧態依然とした形式の芸術を打ち壊すとき、それはまたすべての観客に対してその破壊行為への参加を誘発します。というのも未来派のアクションは、いかなる固有の芸術的な技倆をも必要としないからです。この意味では言うまでもなく、共産主義よりもファシズムのほうがはるかに民主主義的です。それは、私たちすべてが参加可能な唯一の形態なのです。したがって西欧の参加型アートというのは、完膚なき破壊行為という遂げがたい夢へと向けられた、ノスタルジアの表明なのです。そして同時にそれは、全面的な消費行為でもあります。なぜなら1960年代の革命とは、消費をめぐる革命だったからです。消費とは、破壊行為でもある。ではソビエト社会とはなんだったのかというと、それは消費なき生産社会だったのです。そこには観客も消費者もいなかった。すべての人々が生産プロセスに携わっていたのです。したがって「集団行為」や当時のそのほかの一部のアーティストの役割は、消費の可能性、共産主義を享受しうる外在的なスタンスの可能性をつくり出すことでした。それは反体制的なスタンスでも、ソビエト権力に抗うスタンスでもなかった。ソビエト権力に本格的に抵抗した反体制派もわずかながら存在しましたが、彼らは実のところ身を持て余してしまいました。
ビショップ:破壊行為と参加といえば、それについて思い浮かぶ近年の表現が、ポーランドのアーティストであるアルトゥール・ジミェフスキの《ゼム(Them)》(2007)という映像作品です。その中心要素となっているのは、「青年ユダヤ会」、「青年社会党同盟」、「ポーランド国家主義同盟」、そして「カトリック教会」という4つのイデオロギー集団による一連の絵画ワークショップです。各グループは、自分たちの信条を象徴する視覚物をつくり出します。そしてそれぞれの視覚物は、ほかのグループによって改変されるのです。このゲームの唯一のルールは、誰であれほかの人たちによる視覚物に対して、全員が干渉、改良、手直しを施し、またはそれを破壊してよいというものです。言うまでもなく、それは最後には手の施しようのない騒動と化しました。ラストシーンでは、アトリエ内に煙が立ちこめて参加者たちが建物を去っていきます。ジミェフスキの実際の意図は、革新的な出会いの場の実現にあったのだと思います。ただし彼はそれを、4つの集団をたがいに衝突させるという倒錯した手立てで為しました。しかしもちろん、それはすべて演出されているわけです――リアリティ番組の手法によって。このように、これらの出来事には脚本がなく、人々はジミェフスキが設けたゲームを自由に行なうことができたにもかかわらず、彼の立場は支配的なものにとどまりました。
グロイス:支配権(sovereignty)はここできわめて重要な語だと思います。なぜならアーティストの支配が、こうした破壊行為が行なわれる場をコントロールするからです。フランス革命やロシア革命でも同様の事態がみられました。ロベスピエールやレーニンは、集団による自発的な破壊行為が生じる場をコントロールしたのです。
ビショップ:そうですね。ジミェフスキのような表現で、どういった作者的な属性が作用しているのかを見出すのは簡単なことではないと思います。アーティストはそこでゲームのルールを設定し、それが展開していくさまをうかがいますが、はっきりとは行為の舵取りをしません。采配は参加者に任されているのです。しかしもちろん事後的に、アーティストの編集という大幅な整序の作業がある。撮影された行為のすべての映像は、明瞭な語り口と視点を持つ30分間の映像作品として命を吹き込まれます。
グロイス:ええ、アーティストが支配的立場にいて君臨するということは、彼らが逐一なにかを行なうということではないのですね。アーティストはあくまで、ほかのすべての人々が行為に携わる場を象徴しつつそれをコントロールするわけです。彼らはそうしたほかの人々が行なっていることに権限を与える、本源的な作者なのです。
ビショップ:今日に未来派の系譜で表現を行なっている別の存在として、イタリアのアーティストであるマウリツィオ・カテランが挙げられるでしょう。彼はメディアを同様の方法で活用し、挑発を行ないます。ただし彼の場合、未来派に欠かせない政治的スタンスはみられませんが。一例となるカテランの作品が《サウザン・サプライヤーズFC》(1991)です。彼は全員が黒人の移民であるというサッカーチームを結成し、彼らをサッカーリーグに参加させました。このチームは試合をこなしましたが、とりたてて強かったわけでもなく、結局そのすべてに負けました。この作品において、協働という側面やサッカーリーグの即時的なシステムの援用よりも重要なのは、全員が黒人のイタリアのサッカーチーム、その流通するイメージです。これは政治的にみてきわめて両義的なものです。つまり、それは一方では画期的であり(全員が黒人のサッカーチームがあってはならない理由はありません)、他方で全選手は「ラウス(Rauss)」(ドイツ語で「出て行け」を意味するラウス[raus]の語呂合わせ)という言葉があしらわれたTシャツを着ています。この語は架空のスポンサーという設定なのですが、それはこのイメージをみたアンチ移民の多くの国粋主義者たちが思いつきそうな承服しがたい現実態を示してもいます。このようにそれは、定まった方法によっては明確に解釈できない厄介なイメージなのです。
グロイス:私たちは最初に、未来派とは過激でありつつ非常に道化的でもあったという話をしました。カテランにも明らかに同様のことがいえますね。未来派は、馬鹿馬鹿しいと思われることをまったく恐れていなかった。そして、それは真なる解放だったはずです。というのも、〔今日の〕コンテンポラリー・アートはきわめてシリアスで、公的な印象を気にするようなものと化したからです。カテランに加えて私が挙げておきたいのは、オレグ・クリクです。クリクの初期のアクションは、人々に噛みつき街頭で彼らにちょっかいを出すなどして、凶暴な犬になりきるものでした。ただし彼は同時に、道化のようなエンターテイナーでもあった。未来派に大きく共通する点ではないでしょうか。
ビショップ:ええ、ただその場合もやはり思うことがあります。こうした挑発とメディアの注目にかかわるすべての事例には欠けている要素があって、それはなにかというと、どの例も明白な政治的スタンスと結びついていないということです。
グロイス:その点には同意です。これらが持つ結びつきというのは、あくまでノスタルジックなものなのだと思います。先ほど申し上げたように、それはいわば全体主義的な崇高との戯れです。ただしその全体主義的な崇高には、つねに危険性というものがありません。
ビショップ:未来派とは、最初の右派のアヴァンギャルドだったのでしょうか。
グロイス:ええ、ただ、初期のドイツ表現主義の一部には国家社会主義との係累がみられました。
ビショップ:そこで1つの問いが浮上するわけです。つまり、今日のグローバルな環境にみられる芸術の構成体のうち、どのスタンスに依って立つものが右派であると考えられるのか――また、そのうちのどれがアート・マーケットであるのか。
グロイス:リベラル・デモクラシーと市場経済は右派ではありません。これについては今後どうなるかというあたりですね。共産主義には当初からリベラル・デモクラシーに共通するところがありました。双方ともに、物質面での人々の幸福が第一の課題となるためです。だからこそ、それらの戦争は冷戦となったわけです。政治参加の真なる場を創出するためには、人々は自身のプライバシーを――そして極論からすれば、自らの人生を犠牲にしなければならない。しかし今日、なにかを厭わずに犠牲に捧げる者などいるのでしょうか。今ならイスラム原理主義がそうでしょう。しかし西欧文化では、純然たる犠牲という伝統はまずもって右派のファシズムの伝統なのです。それは、「生」にもっとも高い価値があると主張するリベラルの生政治(bio-politics)に取って代わる、唯一の存在です。じつに未来派を、芸術による――いわばテロ行為のリエナクトメント(再演)だと、そう考えることもできるのです。実際、イタリアには19世紀からテロ行為の長い歴史があり、ロシアにおいても同様です。このようにその2つの文化では、実際に伝統としてテロ行為が生まれ、そしてテロ行為はまた概念として規定されることになりました。こう考えると、ロシア未来派とイタリア未来派は、19世紀のテロ行為のある種のノスタルジックなリエナクトメントだといえるでしょう……。しかし今日のテロ行為となると、これに対してアーティストは引けを取ります。未来派が希求したのは、ハリケーン・カトリーナのようになることであり、そこから身を守るシェルターのようになることではありません。未来派の表現はいずれも、建設的であることや目的を持つことの否定、無意味さだといえます。今日のアーティストは次のような不服を述べ立てます。つまり、彼らは社会に対して実践的なインパクトを与えずにおり、自分たちのプロジェクトが失敗に終わり、世界を変えられないと。しかし本質的に、あらゆる表現は無意味であり、あらゆるプロジェクトは失敗するのです。アーティストとそうでない者の唯一の違いとは、アーティストでない者が自身のプロジェクトに失敗したとき、それを次のプロジェクトにはつなげられないということです。アーティストにはそれが可能なのです。芸術とは、ユートピアの失墜についての思索が可能となる、驚異的な領域です。そこでは芸術の失敗が果てしなくくり返されますが、それは芸術以外の領域ではほとんどなし得ないことです。
ビショップ:そうでしょうか、私は確信が持てないのですが。
グロイス:いえ、それはなし得ないのですよ。なぜなら、芸術以外の領域では失敗には価値がないのですから。失敗というのは文字通り失敗にしかなりません。けれども芸術において、失敗は芸術的達成へとほぼ直結します。少なくとも、芸術をそうしたものとして売ることはまったく不可能ではありません。
ビショップ:確かにその通りですね。ただ、実際にはそこまで簡単な話ではないのではと、頷きがたい気もして。
グロイス:ええ、ですがこのことは未来派にも当てはまりますよ。彼らのアクションは例外なくしくじったのですから。彼らはあらたなイタリアを築くことも、近代的な生活様式を打ち立てることもなかった……。
ビショップ:ただ、彼らがその潤滑油となった政治的構想に関しては、変化を達成したし、近代化を果たしたわけです……。
グロイス:その結果といえば? ムッソリーニが権力を握ったのです。ではその後については? ムッソリーニは、失敗したのです。そして現在ではムッソリーニに肯定的な目を向ける者はいませんが、未来派は愛されている。なぜなら未来派はファシズム運動の一端であるにとどまらず、ファシズム運動の失敗に対する美学的な予見でもあったからです。未来派は前もって、ファシズムが為したことの道化的な側面や不条理性、内実の不在を表わしていました。未来派はすでに、ファシズムのキッチュな側面や現実生活における実効性の完全な欠如を予描し、そしてそれを反映させていた。こうした点から、私は次のように言いたいのです――未来派は、ファシズムの美学を築いたのだと。同時にそれは、その美学の不可能性を立ち現し、そしてその失敗を予見した。そしてこれを理由として、私たちは今日ファシズムを否定するにもかかわらず、未来派を愛することができるのです。
(了)