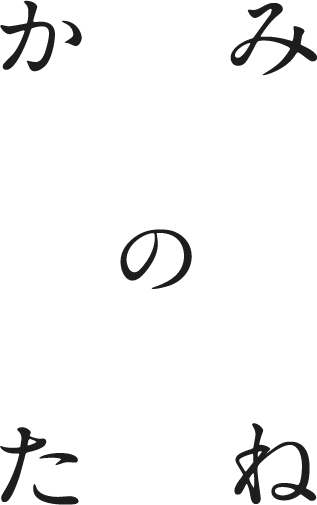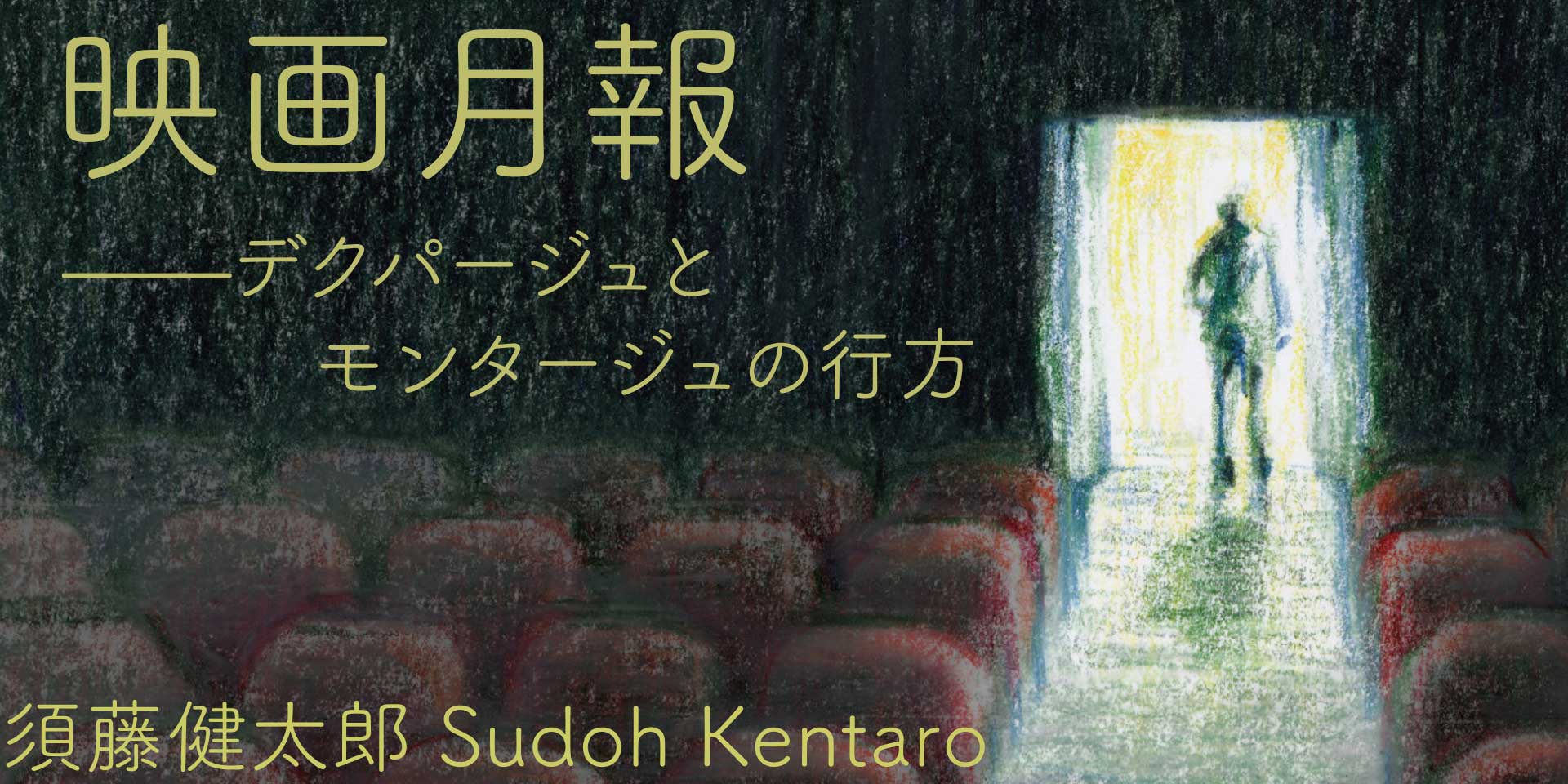映画批評家・須藤健太郎さんによる月一回更新の映画時評。映画という媒体の特性であるとされながら、ときに他の芸術との交点にもなってきた「編集」の問題に着目し、その現在地を探ります。キーワードになるのは、デクパージュ(切り分けること)とモンタージュ(組み立てること)の2つです。
今回は名実ともにジョージアを代表する映画監督ナナ・ジョルジャゼの『蝶の渡り』。本作での「ジョージア」という場所をめぐるイメージの捉えられかた/紡がれかたについて、27年前に同じくジョージアを被写体としたオタール・イオセリアーニのドキュメンタリー作品『唯一、ゲオルギア』とともに考えます。
すべてを比喩として機能させる。『蝶の渡り』はすみずみにいたるまでそんな意志に貫かれ、比喩に比喩を積み重ねていく。モンタージュの主要な機能のひとつに立脚した作品といえる。
タイトルの「蝶」がジョージアの人々が置かれている現状を表すための形象であること、比喩はまずそこからはじまる。コスタがいくらお金を積まれようとも、これだけはと手放そうとしない大切な絵。山を渡るべく風を待つ蝶の群れを描いたもので、《蝶の渡り》と題されている(画家ギオルギ・マスハラシュヴィリがこの映画のために描いた作品で、原題をそのまま訳せば「蝶の強制移住」の意味になるという)。戦禍に見舞われ社会が混迷を極めるなか、故郷を離れることを選び、移住の機会をうかがうジョージア人の姿をここに見ないのは難しいだろう。実際、この映画に出てくる人たちはみな風に乗って飛び立っていく。コスタのかつての恋人ニナを筆頭に。ニナはコスタのもとに帰還したのも束の間、裕福なアメリカ合衆国の美術コレクターに見初められ、彼と結婚して渡米することになる。

『蝶の渡り』©STUDIO-99
ニナは風を待つ蝶の一匹であるだけではない。コレクターが絵画に向けた「美しい」という形容詞をすぐさまニナへと向けてみせるように、ニナは彼にとって美術品と同じ性質を持つ存在でしかない。彼女は蝶でありながらさらに美術品に比され、比喩に比喩が重ねられる。
ニナの渡りは、また別の渡りを引き起こす。コスタと同居し、衣服作りに精を出していたロラは自ら進んで「蝶」となる。蝶もまた美術品と同じような収集の対象なのだから。ロラは蝶を愛するイタリア人の著名な昆虫学者に照準を合わせ、博物館から失敬した貴重な蝶の標本で彼の気を惹こうとする。昆虫学者はジョージアの珍しい蝶に魅せられるものの、蝶は生まれた環境でしか生きられないのだから、自分がこちらに移住すると言い出す。たぶんそれはジョージア人にも当てはまる真実なのだろう。昆虫学者が結局はロラを連れてイタリアに帰ることになるとしても。
女性が美術品や蝶の標本になぞらえられて、男性のコレクションに加えられる。なんともおぞましい事態だが、ナナ・ジョルジャゼは自分の力ではどうしようもない現実を受け入れた者に特有の、どこか達観したような視線ですべてをあっけらかんと描いているようだ。ニナとロラはコスタをめぐって争うこともなく、2人は結婚にあたって葛藤もない。2人が自分のもとを次々と離れていくにもかかわらず、コスタはそれを気に病むこともない。ミシャは老母を置いてはいけないとためらいはするが、ムラのなんとかなるさのひと言ですんなり依頼に応じることになる。ミシャとムラの2人は何者だかよくわからぬアメリカ人女性に大金で雇われ、いまやネイティヴ・アメリカンの居住地を巡る旅に同行している。みながみな起きることを受け入れ、それに逆らうことはない。ときには人を戸惑わせるほどに。そう、まるでカメラのように?

『蝶の渡り』©STUDIO-99
画家のコスタが暮らすのは、祖父母の代から受け継いだ半地下の家である。そこは昔から仲間たちの溜まり場だった。ヴァイオリニストのミシャ、ピアニストのムラ、ビデオを回して友人の姿を収めるナタ、そして元バレリーナのニナ。地上に居場所を失った芸術家たちの避難所のような場所。コスタは風が吹き入れられるように窓を蹴り割り、誰もが気軽に入ってこられるように鍵を壊して玄関を開けておく。人が立ち寄るたびに、ここでは出会いが起こる。ニナとスティーヴ、ロラとマルコ、ミシャとタナ……。いつしか噂が広まり、縁結びを期待して年配の娼婦が訪れる。組み合わせが実現する、ここはいわばモンタージュの空間だ。
コスタの家は過去と現在が出会う場でもある。いまは修道院に暮らすが、かつては写真家だったナタはビデオカメラで何でも記録してきた。彼女は新たに住人となった服飾デザイナーのロラに1991年の新年を祝ったときのビデオを見せている。浮かれ騒ぐ、若き日のコスタたちの姿。折しもソ連からの独立の機運が高まり、その年の4月にジョージアは独立を宣言するが、その後に市民同士の抗争が激化し、首都トビリシは戦場と化した。黒海に面する保養地で知られたアブハジアでは、ジョージアからの分離独立を巡って紛争が勃発した。映画はナタの幸福なホームビデオから戦禍を捉えたモノクロの記録映像へと移り、陽気な声はいつしか恐怖に喘ぐ叫びに変わっていく。「アブハジア戦争から27年後」の字幕。これから語られるのは、1990年代初頭の戦争と地続きの現実であることがこうして示される。

『蝶の渡り』©STUDIO-99
『蝶の渡り』の開巻、ソ連からの独立にともないレーニン像が倒される映像には見覚えがあった。オタール・イオセリアーニの『唯一、ゲオルギア』(1994)だ。ジョージア出身のイオセリアーニはソ連政権によるたび重なる検閲に耐えかね、1982年にフランスに拠点を移したが、祖国が独立後に見舞われた悲劇を受けて、故郷ジョージアの歴史と文化と伝統をまとめ、戦禍に見舞われる現状に警鐘を鳴らしたのだった。
3部構成で、合計4時間に及ぶ大作ドキュメンタリー『唯一、ゲオルギア』は、「ボルシェビキの暗い時代は、現在の悲劇に直結している」との断言から始まる。ロシア帝国の支配下にあったジョージアは1917年の10月革命による帝政崩壊後に独立したが、1921年2月にボルシェビキに侵攻され、ソヴィエトの政権下に置かれた。イオセリアーニは1991年12月に始まるトビリシ内戦、アブハジアと南オセチアで激化した分離独立をめぐる戦争が、ソ連によるジョージア支配の延長上にあることを決然と示す。
既存のフッテージのみで構成されるこの作品は、記録映像だけでなく、ジョージアで製作された劇映画を同じく歴史の証として引用してみせる。現実はたしかに虚構の中にも記録されてきたが、だからといって、ドキュメンタリーとフィクションがここで同等のものとみなされているというのではない。第3部冒頭でジョージアの伝統である多声合唱(ポリフォニー)が紹介され、それぞれの声部が独立した旋律とリズムを維持していることが強調される。ポリフォニーは古来より多様な宗教を受け入れてきたジョージアという国の理想的なあり方を示すと同時に、あたかもこの映画全体の構成原理を示すメタファーのようだ。『唯一、ゲオルギア』は性質の異なる複数の映像と音声をモンタージュしながら、記録と虚構を、歴史と現在を、山岳風景と市街地を、戦車や武装兵の姿と食卓の団欒を、リゾート地と参謀本部を独立させながら映し出していく。第2部の末尾、コーカサス山脈を見晴るかすのどかな風景に銃撃戦の痛々しい音響が重ねられ、両者の不一致が際立たせられている。こうして、血で血を洗う戦争状態に陥った「現在の悲劇」を扱う第3部が準備される。

『蝶の渡り』©STUDIO-99
『蝶の渡り』は『唯一、ゲオルギア』から27年後の作品である。ナナ・ジョルジャゼは、ナタのビデオと現実のフッテージの間にむしろ差異を設けない。ナタが撮影するビデオの画面上には録画中を示す「REC」の文字列にバッテリー残量を示すアイコン、そして四隅にフレームが見える。ところが、これらはモノクロの記録映像に切り替わってもそのまま維持されている。いや、そればかりか、記録映像ははじめこそ動画だが途中で静止画へと切り替わり、戦争写真が次々と映されていく構成へと続いていくのだが、各写真の上にも始終「REC」とバッテリーのアイコンに加え四隅のフレームまでもが健在なのである。
ナタのカメラはカラーとモノクロを区別せず、静止画もまた動画と同じであり、フィクションだろうがドキュメンタリーだろうが何でも一緒くたに扱う。ここでは異なる由来、異なる質感、異なる意味内容を持つイメージがすっかり一面に均されている。編集のあり方として、それはイオセリアーニ的なポリフォニック・モンタージュの対極にある。ここでは、複数のカメラで撮られた映像をどう共存させるかではなく、あらゆる映像を撮ることのできるカメラを持つことに力点が置かれているということだ。
『蝶の渡り』では、ナタという名の赤毛のカメラマンに監督ナナ・ジョルジャゼの分身が託されている。ナタは最後に「撮れるものはすべて撮った」「次はあなたの番だ」と言って、ニナからもらった新しく高価なカメラをたまたま通りがかったにすぎない見知らぬ少年に渡す。その含意は説明するまでもないだろう。ひとつのカメラにすべてのカメラを統合することができるなら、この新しいカメラにはこれから撮られることになるすべてのイメージが収められていくはずだ。
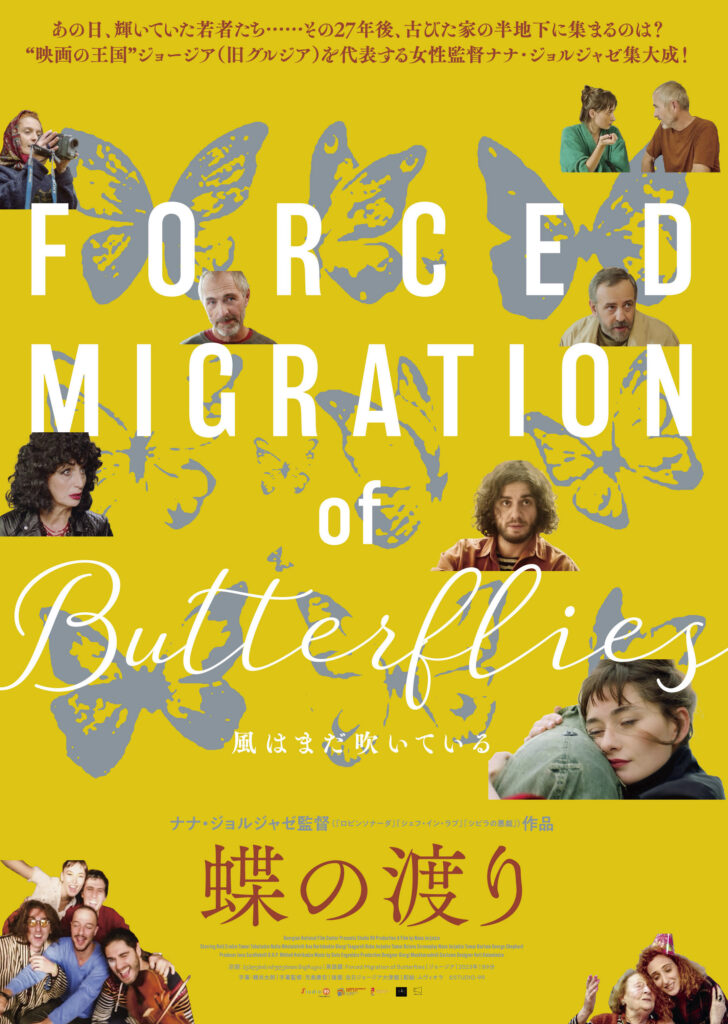
『蝶の渡り』
原題:პეპლების იძულებითი მიგრაცია
英語題:Forced Migration of Butterflies
2023年|ジョージア|89分|
監督:ナナ・ジョルジャゼ
脚本:ナナ・ジョルジャゼ、タマル・バルタイア、ジョージ・シェパード
撮影:ミヘイル・クビリカゼ
編集:ナナ・ジョルジャゼ、ギオルギ・バルタイア、イメダ・テトラゼ
出演:ラティ・エラゼ、タマル・タバタゼ、ナティア・ニコライシュヴィリ
字幕:磯尚太郎|字幕監修:児島康宏|
後援:在日ジョージア大使館
配給:ムヴィオラ ©STUDIO-99
https://moviola.jp/butterfly/
新宿武蔵野館ほか全国順次ロードショー
バナーイラスト:大本有希子 @ppppiyo (Instagram)